2020年に世の中を騒がせた入試改革ですが,センター試験が共通テストに変わっただけでなく,各大学が実施する個別入試も改革されたことについても知っておく必要があります。
実際は「個別入学者選抜改革」と呼ばれていたのですが,厳しい非難の的となった成績提供システムなどと比べるとあまりに地味で,記憶に残っている方はほぼいないでしょう。
とはいえ,上記改革によって生まれた「学校推薦型選抜と総合型選抜」はすでに大学入学者の半数以上が利用するほどにまでなっていて,学生生活に大きな影響を及ぼしています。
当記事を読むことで,これらの選抜が生まれた経緯に加え,かつての推薦入試またはAO入試との変更点について理解するようにしてください。
大学の個別入試における過去の問題点

2020年の入試改革により,かつてのセンター試験は共通テストへと生まれ変わりました↓
記述式問題の導入こそ見送りになったものの,判断力や思考力そして表現力を問う出題は共通テストの随所に登場することとなり,有識者からの評価は想像以上に良いものでした。
ところで,「共通」という文字によく表れているのですが,上記テストにおいては全受験生が同じ問題を解くことになるわけで,これはつまりどの大学の新入生においても期待される資質・能力が評価されることになります。
優秀さに関わる好ましい能力であると考えてください。
ですが,共通テストで測ることができない資質・能力もあるわけで,例えば才能に関わる特殊能力だったり,社会性や人間性に関わるものだったりが挙げられますが,そうしたもののうち各大学が特に評価したい資質・能力を問う役割を担う試験が個別入試というわけです。
大学が個別入試で採用している方式としては主に3つあり,かつては以下のように呼ばれていました↓
- 一般入試
- 推薦入試
- AO入試
3つ目の「AO」とは「アドミッションオフィス(admissions office)」の略で,和訳すると「入学事務局;入試担当事務局」などとなります。
なんともイメージしがたい名称ですが,大学の特別な部署が実施していたと理解しておけば十分です。
さて,これら方式のうち,2つ目と3つ目のいずれかを利用して入学した生徒はどのくらいいたのでしょうか。
2017年度のデータによれば,推薦入試を利用して入学した学生は国立大学で12.2%,公立大学で24.4%,私立大学では40.5%でした。
そしてAO入試はそれより少なくなるものの,国立で3.3%,公立2.4%,私立で10.7%となります。
私立大学に限れば,実に半数以上の新入生が一般入試以外の方式で合格していたということで,当時からすでに大きな影響力を及ぼしていたことは確かです。
ですが,以下のような問題点が指摘されていたことを述べておかなければなりません↓
- 極端な能力しか問われず,一部の受験生は楽に受かってしまう
- 推薦合格した生徒が早期に勉強の情熱を失い,同僚に悪影響を与える
確かに英語だけが異様に得意だったり,スポーツで良い記録を残したようないわゆる「一芸」を持っていた生徒は特に受験勉強をすることなしに合格し,その発表時期も早かったため,一般の生徒が勉強している横で推薦組が遊んだり車の免許合宿に申し込んだりしている光景をよく見かけたものです。
もちろん誰しもがそうであったわけではないですし,ちゃんとした高校は生徒がそうならないように何らかの策を講じていたわけですが,2020年の大学入試改革では国が主導となり,これらの点も含めて見直しを行うことになりました。
次章で,具体的にどのような変更がなされたかについてまとめることにしましょう!
推薦とAO入試はどう変わったか
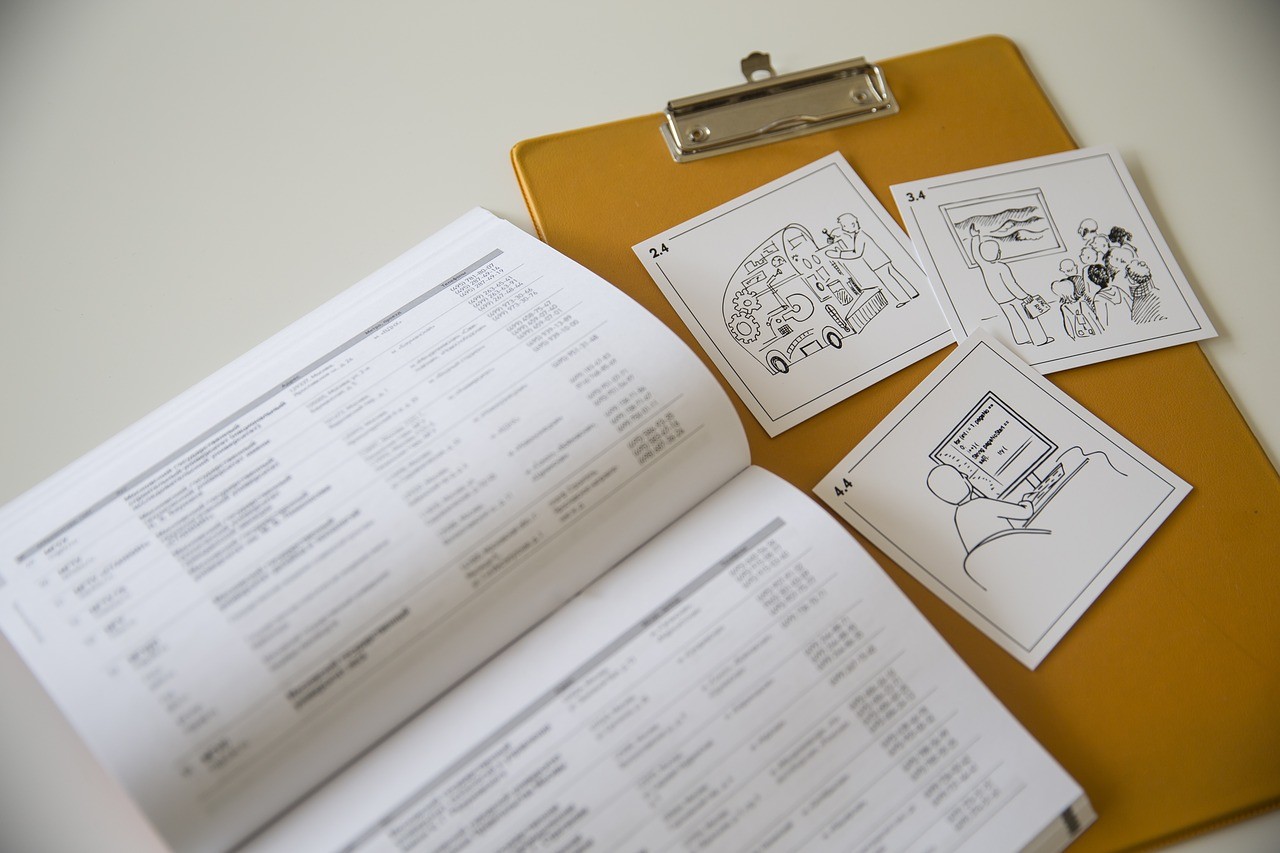
昔から各大学は「本校に望ましい能力を高いレベルで保有する受験生を高く評価する」といったアドミッションポリシーを明確に掲げているものの,入試で評価した能力が入学後の大学教育を行う上で大いに役立つものでなければなりません。
その一方で高校生はそうした入試問題を解けるようになるために3年間を費やすわけですが,努力に見合った結果が得られないようであれば,
「受験に役立たない授業をどうして真面目に受ける必要があるのか?」
などと学習意欲が低下してしまうのは当然です。

その他,大学からの合格発表が早すぎるようでは,判明した日から大学に入学するまでの間は空白期間となってしまい,これも好ましい状況ではありません。
定期テスト後の空気感と言えば伝わるでしょうか。
もう学ばなくて良いのだとしたら高校に通う意味は見当たりませんし,一般受験をする生徒との温度差に気を遣ったり,逆に心無い言葉をかけられて嫌な気持ちになることも少なくないのです。
さて,こうした問題に対する国の答えはいかがなものだったでしょうか。
全部で3つの変更点がありました。
名称が変更された
先ほど示した3つの試験の名称ですが,特に「AO入試」という呼び名が分かりづらかったように思います。
名前を聞いても一体どのような試験を行うかイメージしづらく,特性をより明確にした名称が採用されることになりました↓
- 一般選抜(かつての一般入試)
- 総合型選抜(かつてのAO入試)
- 学校推薦型選抜(かつての推薦入試)
「入試」という言葉すら曖昧だということで「選抜」に形を変え,件のAO入試も総合的な受験者の能力を評価するといった意味合いの「総合型選抜」へと名称を変え,大変わかりやすくなったように思います。
推薦入試に関しては,誰が推薦するかといった主体がはっきりしました。
内容面が改善された
もちろん,中身の変更も行われています。
以前のAO入試と推薦入試は,出題科目が少なかったり試験形式が特殊だったりで,英語では4技能を総合的に評価していないことも問題視されていました。
もっとも,かつての実施要項の中にも「知識・技能の修得状況に過度に重点をおいた選抜とせず(AO入試)」といった注意書きが見られたわけですが,今回の変更では「原則として学力検査を免除し(推薦入試)」という記載とともに削除されています。
その代わり「調査書などの出願書類だけでなく,各大学が実施する評価方法など,または大学入学共通テストのうち少なくともいずれか一つの活用を必須化する」といった具合に明文化されました。
下線を引いた評価方法の例としては「小論文・プレゼンテーション・口頭試問・実技・資格や検定試験の成績」などが挙げられています。
もちろん,この文1つで何かが大きく変わることはないのですが,全体的な意識が総合的能力の方に向けられたことは確かです。
実施面で改善が見られた
発表時期が早すぎると生徒自身のモチベーションに悪影響があると言うのであれば,なるべく遅い時期(正確には,教育課程に基づいた学習を終えるタイミングにできるだけ一致させた時期)に出願や合格発表を行うのが適切でしょう。
そこで国は総合型選抜の時期を以下のように定めたわけです↓
- 出願時期は9月以降とする
- 合格発表は11月以降とする
かつてのAO入試での出願は8月以降となっていたわけで,合格発表は約4割の大学が10月以前に発表していたことを踏まえると,しっかりと改善されてきたことがわかります(あまりに遅すぎても今度は「一般選抜の準備が間に合わない」などの苦情が出てきます)。
もう1つの学校推薦型選抜については以下の通りです↓
- 出願時期は11月以降とする(変化なし)
- 合格発表は12月以降とする
出願時期については変化ありませんでしたが,「推薦入試」と呼ばれていた時代には約4割の大学が11月以降に合格発表を行っていたので,そちらは改善されることになりました。
その他,入学前教育(大学側が早期に受かった受験生を対象に教育すること)については,「今以上に積極的かつ適切な指導をするように」と指示があり,調査書や提出書類の改善についても記載があります。
ここまでの内容について気になった方は,以下の文書に一度目を通すようにしてください↓
まとめ

以上,かつての推薦入試とAO入試が,それぞれ「学校推薦型選抜」と「総合型選抜」に名称が変わった経緯と変更点についてまとめてきました。
名称の変更にとどまらず,テストの内容自体も改善され,評価される能力や実施時期,さらには合格発表の日時も改善されたことがわかっていただけたかと思います。
令和5年度の調査結果を調べると,総合型選抜の利用者が国立5.9%・公立4.1%・私立17.3%,そして学校推薦型選抜の方が国立12.3%・公立26.0%・私立41.4%とますますその割合を増しているようです。
それだけに,そこで選抜されてきた受験生が真に各大学が希望する価値を備えた人材であるかどうかは,その後の生活をモニターすることで分析していかなければならないでしょう。
そしてそこで判明した結果を踏まえて,再度,選抜内容を見直しながら入試内容の質をさらに高めていくことが今後求められています。
一般選抜は一般選抜ならではの,そして学校推薦型選抜や総合型選抜においても独特な魅力を持った人材が判別されるように,各大学がより趣向を凝らした選抜制度を行っていく必要があるということです。
大学側が「高大接続」というより俯瞰的な目線で受験勉強を捉えては,今後の受験生が安心して普段の勉強に取り組めるように変わっていくことを期待しています。
受験生の側としてはこれまで通り,こうした選抜試験の利用についても検討してください。
単純に試験機会が増えるわけですから,大学合格を考えれば有利に働くはずです。
そして,より総合的な能力を発揮できるようかつ一般選抜の勉強とも並行できるよう,対策も時代に合わせたものを採用するようにしてください↓
最後までお読みいただきありがとうございました。