2022年11月にChatGPTが公開されてからというもの,生成AIについて議論されることが爆速的に増え,多くの関連サービスも登場してきました。
世界的にみると,上記サービスのユーザー数はわずか2ヶ月で1億人を突破したとのことで,これは主要なSNSが広まる速度よりもずっと早く,コロナワクチンの接種回数と同じスピードだったとのことです(参考:野村総合研究所の調査結果)。
公共事業ではない以上,営利目的で使われることは避けられませんが,社会に出ていない学生が教育の一環として使うことも大いに考えられます。
実際,保護者の許諾の有無は抜きにすると,中学生以上は生成AIの利用が可能ですし,まもなく小学生も使えるようになるでしょう。
GIGAスクール構想においてICT環境が整った昨今なだけに,学生のうちから情報活用能力を育成しておくことが重要であり,生成AIを使いこなすことはその良い練習になるはずです。
加えて,文部科学省は学校での活用方法に関するガイドラインを作成していますし,各学校も独自ルールを設けています。
当記事では,そんな「生成AIと小中高生がどのように付き合っていけば良いか」について,学術的に利用する際のメリットやデメリットを明らかにしながら考えてみることにしましょう!
生成AIと学校教育について
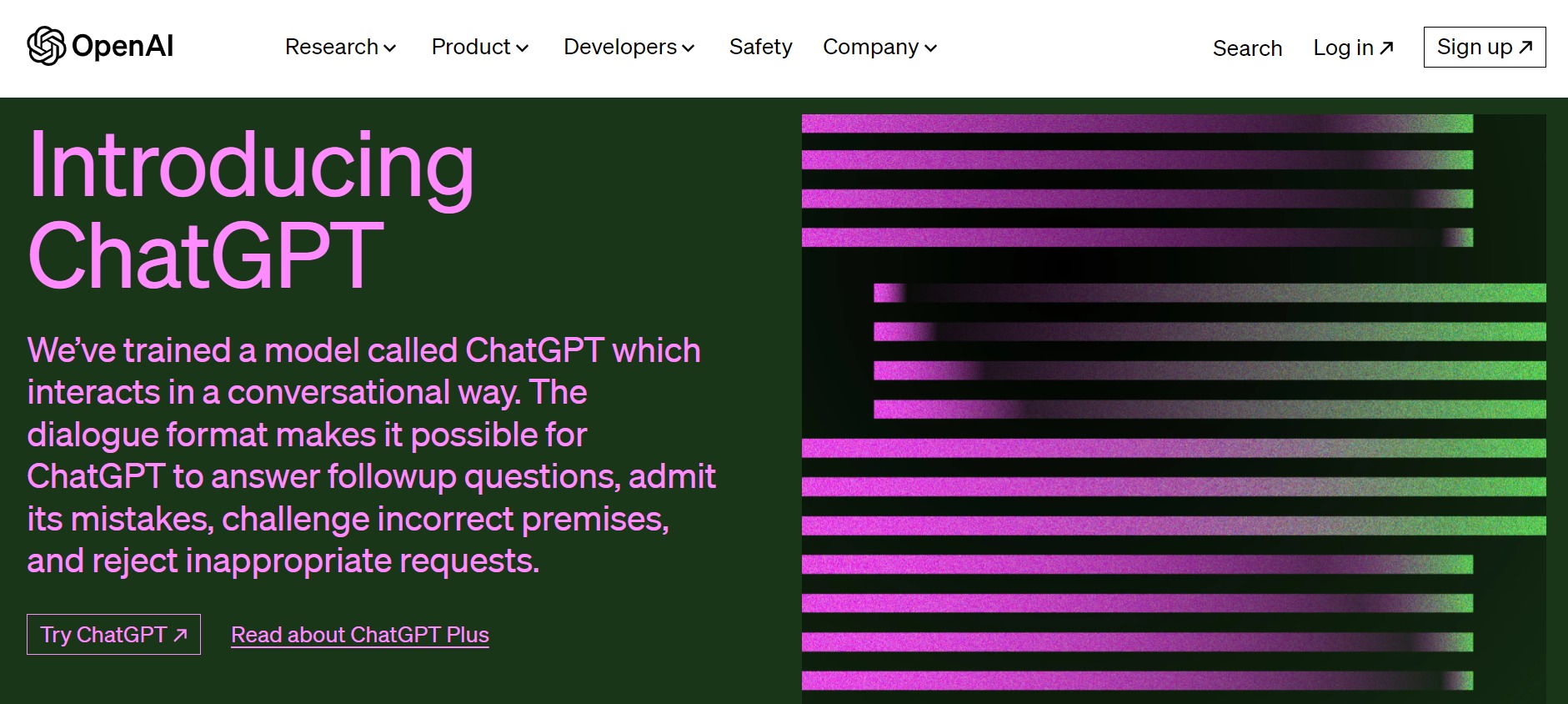
「生成AI=ChatGPT」などと誤解している人も見受けられますが,ChatGPTはあくまで生成AI関連のサービスの1つにすぎません。
名前にある通り,AIが生成したものであれば文章以外のものも対象となり,プログラミングのコード作りから,画像や動画に音楽の作成,さらにはそれらを高次元で組み合わせたようなプラットフォーム的なものまで含まれることになります。
そして,異なる強みを持った生成AIが存在し,Open AIの開発した「ChatGPT」は文章やプログラミングコード生成に強い印象です。
その他,文章生成ではGoogleの「Bard」やAnthropicの「Claude」が有名ですし,画像生成では「Midjourney」やStability AIが開発元の「Stable Diffusion」,そして基板生成ではマイクロソフトの「Azure OpenAI」やAWSの「Bedrock」などがあります。

参考までに,生成AIは英語で「Generative Artificial Intelligence(生成可能な人工知能)」と言うことや,ChatGPTのGPTが「Generative Pretrained Transformer(事前学習させられた生成のための変換器)」の略であることも覚えておくと良いでしょう。
どちらにも「生成」という意味のgenerativeが使われています。
さて,デメリットばかりがニュースで取りざたされていますが,生成AIに大きなメリットがあることは明らかです。
平たく言えば,人間社会の質を改善することに貢献するわけですが,例えば膨大な文章を作成しては違う言語に翻訳する手伝いをしてくれたり,何もないところから自分好みの画像を作成してくれたりと,様々な分野での生産性を向上させてくれます↓
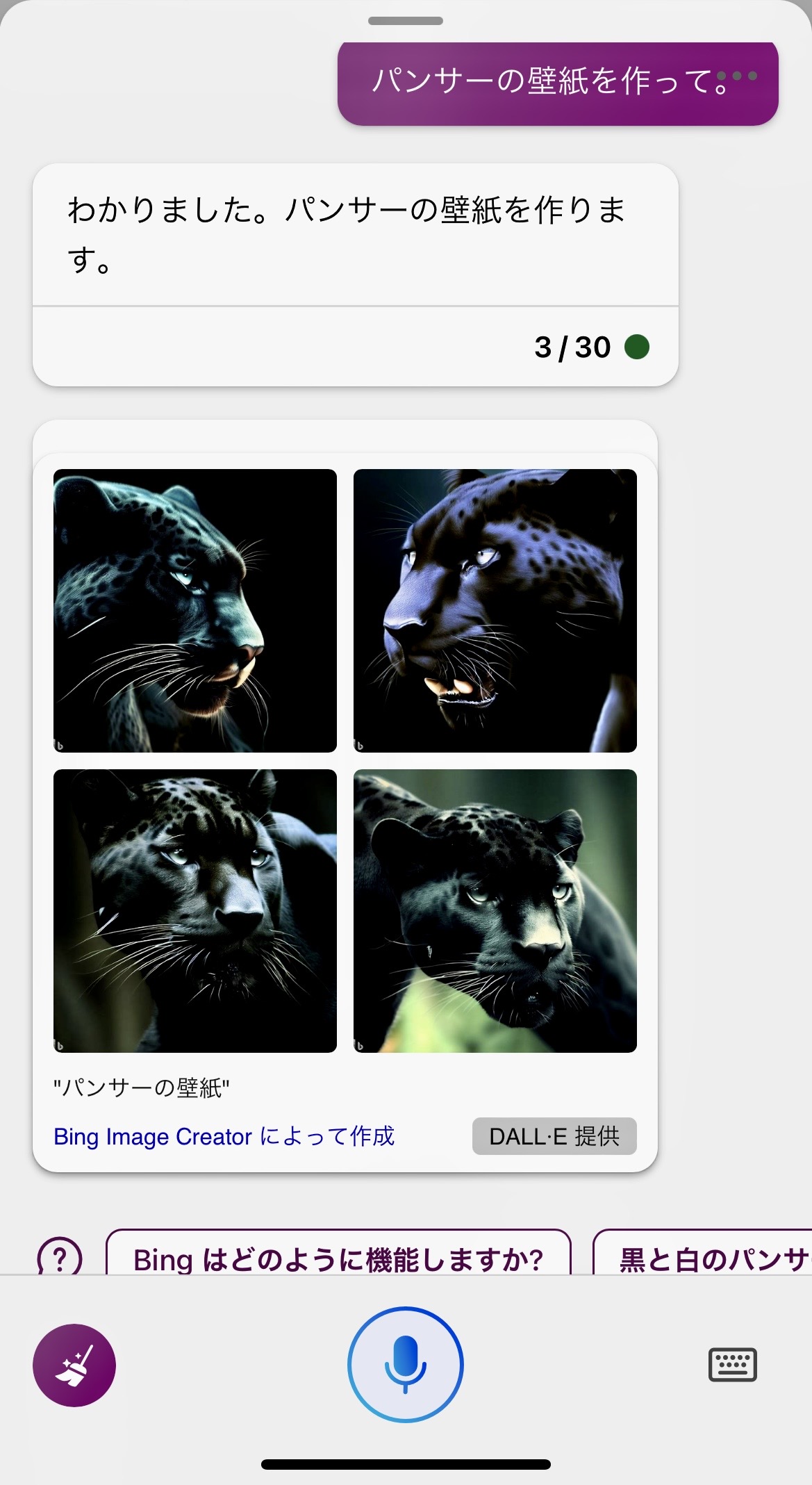
しかしその一方で,楽してお金を稼いだり,その場しのぎで使われたりなどと下品な使い方をされてしまうからこそ注意が必要となってくるわけです。
生成AI自身には罪はなく,あくまでその結果をどうこうする人間側の品格が問われることになります。
他人様のサービスに便乗した上,相手の権利を脅かすようなものであれば最悪ですが,アプリストアを覗いてみれば,公式アプリと名前の混同を目論んだものも見られ,生成AIに対する免疫ができていない人ほど簡単に標的にされてしまうでしょう。
個人情報を生成AIに読み込ませてしまう危険性については,企業や教育現場において声を大にして言われていることですが,これまでに情報モラルを学ぶ機会のなかった大人ほど,無防備になってしまっているように感じる次第です。
なお,最近の学習指導要領をみると,これからの時代は「ICTと上手に付き合っていく」ことが重要視されているため,生成AIについても,小中高生のうちから積極的に使って理解を深めていく方向で指導されることが想定されます。
他のICT機器と同様,「危険なので使わない(使わせない)」といった選択をしてしまうようでは情報活用能力は育ちません。
とはいえ,好き勝手に使ってしまうことも問題で,使用する前に一定量の知識を頭に入れておくことが重要です。
まずは次章で,小中高生の学校生活において,生成AIがもたらすメリットについてみていきましょう!
小中高生が生成AIを使う利点

先ほど紹介したBardをみると上のような文面が登場してくるあたり,ユーザーとして小学生も想定されている動かぬ証拠と言えるでしょう。
ユーザー側の工夫や使うアプリの種類によっては様々な使い方が考えられますが,ここでは文科省が公表する内容のみにとどめて紹介していきます。
生成AIの性質や限界を理解できる
1つ目のメリットですが,生成AIが持つ危険性などの必要知識を学んでから実際に使ってみることで,生成AIの性質や限界について身をもって理解することが可能です↓

生成AIとのチャットは,一見凄そうに見えるものの,よく読めば,無難な答えしか返ってこないことも少なくなく,期待が大きいユーザーほど残念な気持ちになってしまうかもしれません。
特に計算など,明らかに間違えている答えを平気で提示してきた際には,大した性能ではないと思ってしまうはずです↓


とはいえ,こうした経験はマイナスではなくむしろプラスであると思っています。
AIが完璧な答えばかりを返すようであれば人間の存在意義などなくなってしまうでしょうし,あまりに神格化されて「生成AIがこのように言っていたから」などと無批判で従うような人が出てきてしまっては色々と危険です。
犯罪行為を行ってもAIのせいにしてしまうでしょうし,AIの助言を妄信したあまりに大切なお金を失ってしまうことにも繋がるでしょう。
小中高生の段階から,AIが得意なところを理解して,人間がどの部分で能力を発揮できるのかを明確にしておくことで,今後の自分の身の振り方を考える際に役立つというのが1つ目のメリットです。
新しい視点が得られる
生成AIによる回答は確かに一般的で無難なものが多いですが,基にしている知識データが海外由来のものであれば,外国人の発想で知識構成がなされていることになります。
特に海外にしかないようなものについて調べる際など,現地に住んでいるからこそ言える意見が返答されてきた際は大変勉強になったと感じるはずです。
また,当たり前の内容であっても,ある程度の量を即座に提示してきてもらえることになるため,特に小中学生であれば新しい発想が得られることも多く,自分が馴染みのない話題になればなるほど,より多くの恩恵が受けられることになるでしょう。
例えば,以下は白いTシャツのメリットとデメリットについて尋ねてみたときのものです↓

箇条書きで簡潔にまとめてくれたり参考文献を提示してくれたりと,これらは見習うべき姿勢であると評価できます。
音声変換はまだ機械っぽいところが見受けられますが,文体の方はかなり自然です。
語学の助けとなる
生成AIは,英会話を学ぶ際の良い話相手になってくれます。
英語圏のサービスなので,典型的な質問に対しての答えは完璧です。
従来の方法で語学を行なおうと思うとアウトプットがしにくかったところですが,今や書いた英文を添削してくれるようなサービスも知られていて,英語ネイティブが周りに少ない島国日本においては大いに力を発揮してくれます。
実際,自分の読み上げた音声を自動で英語に変換して採点してくれるくらいは容易にできてしまうわけで,教室で1人1人が音読するのを聞く時間は節約でき,他人に笑われて嫌な思いをすることはありません。
特に後者は意外と深い傷になることが多いので,こっそり練習できることは多感な学生にとって吉報でしょう。
語学に限りませんが,学力レベルに差がある生徒相手に個別最適化学習することも生成AIの持つメリットです。
小中高生が生成AIを使う際のデメリット

基本的には危険性の方が重要ですし,そのつもりはなくても無意識に被害を受けていることもあるので,生成AIのデメリットについてはしっかり認識しておきましょう!
危険に巻き込まれやすくなる
生成AIを使うにあたっては年齢制限がありますが,中にはいい加減なアプリも少なくなく,対象年齢が4歳以上のアプリで「この内容でよく審査に通ったな」と感じるものもありました。
加えて,非常に見落とされがちなのは,一定レベル以上の知識が身に付いていることが使用の前提条件とされている点です。
これは暗黙の了解になっていることが多く,生成AIについての基礎知識がないと,自分の身に起こりうる危険について想定することは非常に難しくなります。
例えば,検索欄に入力した情報がサービスの提供元に把握されてしまう危険性があることを知っておかなければ,個人情報や機密情報を容易に入力してしまうかもしれません。
電子メールだとすぐに迷惑メールフォルダに放り込める内容であっても,生成AIに同じことを言われてしまうと無防備に入力してしまうこともあるでしょう。
そうした事態を避けるためにも,事前に情報モラルについて学んでおくことが重要です。
こういった知識の欠如は大人であってもたびたび問題となるくらいですから,情報活用能力が不十分な子どもはなおさら注意しておく必要があります。
もっとも,文科省は対策を講じられる学校をモデル校とし,生成AIに関する知見を蓄積しており,教育現場においては例えば中学の探求や高校の情報の授業で学ぶはずです。
そのままでは評価されない
学校ではレポートや作品という形で提出を求められる課題が出されますが,このとき,生成AIを利用したものは,自分の創造物として見なされないことが挙げられます。
というのも,学校の課題は,子どもの思考力や感性,創造性を測ることを目的としているからで,その作業をAIが請け負ったのであればそれはAIの業績と見なされ,その人自身の評価となりません。
今ではAIが生成したものであることを検出するためのソフト(例:生成AIチェッカー)も出てきていますし,似た内容のものを複数の生徒が提出すれば生成AIで作ったことを疑われるでしょう。
たとえ生成AIを何時間も使って良い内容のものを作り上げていたことが事実であっても,そのまま提出してしまってはその努力は報われません。
あくまで生成AIが提示してきた結果は参考にするだけにとどめ,コピーペーストはせずに,自分の意見を交えて作らなければならないということです。

ところで,今や音楽も生成AIだけで全て作れるようになりましたが,2024年のグラミー賞のルールにおいて,作曲・演奏部門に関しては「人間が作ったものが大部分でなければ選考対象外になる」との発表がありました。
資質・能力が低下する
次章で具体的に紹介しますが,数百文字の文章も生成AIを使えば1分も経たずに作成することができてしまいます。
これまでは提出期限が迫ってきたからこそ必死にやっていたところが,時間をかけずに楽してできるようになると,様々なしわ寄せがくることは避けられません。
例えば,生成AIを乱用することで以下のような資質・能力は育ちにくくなるとされています↓
- 批判的思考力
- 創造性
自分で文章を書くのであれば,自然と論理や構成について考えるでしょうし,自分なりの意見がそこかしこに散見されるわけですが,生成AIにまかせっきりになればその機会は減ってしまうわけです。
おまけに,時間をかけて大変な課題を達成したという喜びも実感できないわけですから,学習意欲も同時に失われてしまうことになるでしょう。
そうならないためにも,先述した通り,AIが収集し整理した結果を吟味しては修正するようにし,さらには思考を通して自分なりのアイディアを付け加える必要があるわけです。
もちろん,授業によっては生成AIの使用が制限されることもあるでしょうが,そうされなくても,こうしたことは基礎知識として学んでおきましょう。
読書感想文に学ぶ生成AIの使い方
ここでは太宰治の「走れメロス」を例に,生成AIで読書感想文を作るときの使い方についてみていきましょう!

生成AIを使うと,本文を1文字も読むことなく同作品の読書感想文を作ることが可能で,以下はChatGPTに200字で書くように指示したときの結果になりますが,それらしい内容になっていることがわかるでしょう↓

簡素化するために原稿用紙1枚分の量にしましたが,たとえ400字だったとしても,同等の文章を1分も経たずにやってのけてしまうわけですから驚きです。
日本語も大きな問題はなさそうに見えますが,実際にはいくつかの問題が生じています。
例えば,誰が質問しても同じ内容の感想文が作られることになっているかもしれませんし,その人が普段書いている文章とは明らかに異なる感じがするところは致命的です。
もしも上の文章を国語が苦手な生徒が書いてきたとあれば,急に文章レベルが上がったように感じるのは必然で,わかる人にはすぐわかるでしょう。
表面的なところでは,文章や内容が間違っている箇所も確認できますが,以下で,この読書感想文を上手く修正するための作業を行っていきたいと思います。
情報の選別を行う
これは情報活用能力に含まれるのでしょうが,生成AI(他人)が言ったことをただそのまま繰り返すだけでは活用したことになりません。
なぜかと言えば,書いた文章が自分のものになっていないからです。
当たり前のことですが,しっかりと本の内容を把握した上で自分が感じたことを正直に述べることが読書感想文の重要な点で,例えば,生成AIが1文目で言うように「感動的」だったのかどうかについては真っ先に考えなければいけません。
感動したとしても,その対象は絆や友情ではなく,メロスの強さや馬鹿正直さということもありえるわけで,その感想をもたらした原因について自分なりに分析していきます。
文章というのはその人の考え方を表す鏡のようなものですから,自分にしか書けない内容に変えていくことが重要だと覚えておきましょう。
そもそも,より無難で当たり障りのない表現を採用する生成AIだけに,尖った意見や否定的な意見,その人しか知り得ない具体例などは出てこないように調整されているため,今回の読書感想文に「ディオニスの発言に疑問を持った」などの文面は決して出てこないわけです。
生成AIを使ってアイディアを得ることは構いませんが,誰にも真似できないものを作り上げることを心がけてください。
間違いがないか確認する
同時に,文章の間違いについても確認していきますが,例えば上の3つ目の文章は日本語としておかしいところが多く含まれています。
この部分を読んだときに,すぐに「おかしいぞ」と思える能力は,日ごろの国語の授業などで鍛えられるものです。
私としては,文末が「ました」ばかりで終わっているところも気になりました。
なお,上の読書感想文では確認できませんでしたが,生成AIによる文章には嘘の情報が含まれることもあります。
特に,ネット上に情報が少ないマイナーな作品に関する文章で,人物や作品名のような固有名詞が使われている際は事実確認を行うようにしてください。
学べるところは学ぶ
しかし,生成AIによる読書感想文は一定のルールに基づいて書かれていることは明らかで,構成面では良い評価を得られそうです。
先の文章は過度な繰り返し表現はあるものの簡潔ですし,何より,結末部分が序文内容の表現を変えた繰り返しになっているところは見事だと思いました。
抽象的な内容から具体的な内容へと進んでいく流れも理にかなっています。
批判的に読んでいなければ,「これもありか」と判断してしまってもおかしくなく,少なくともAIが書いたかどうかをこの文章だけで判断するのは難しいでしょう。
上の文章は字数が300字弱と少ないこともあって,実際,ネット上で検索して出てくる判定機に分析させてみたところ,ほぼすべてが「人間が書いたものに近い」という結論でした↓

生成AIが作成した文章を一度読んで,再度何も見ないで書き直すだけでも,より判別は困難になると思います。
ゆえに,評価する側は,文面だけで評価することはせず,その人ならではのエピソードを含めさせたり,より長文をデジタルで提出させては公開されていない高品質なチェッカーにかけたりするなど,就職活動で行われているような工夫が必要になってくるでしょう。
場合によっては,面接代わりに受賞者インタビューのようなことをさせられることも考えられるはずです。
しかし,これは友人などに代筆してもらったときの問題と同じものですので,結局のところ「自分で考えて書く」という前提が守られているかが重要になってきます。
さいごに
以上,生成AIについてその基礎知識からメリットやデメリット,そして最後に使い方のヒントめいたものを書いてきましたが,当記事から何らかの学びがあれば幸いです。
生成AIに関しては,何の知識も持たない人が好き勝手使ったところで良い結果にはならないことについて述べました。
なるほど,受験においては辞書の持ち込みが可とされたり,大学でノートの持ち込みが許される講義もあったりしますが,それはあくまで,知識を使ってどのような論理を構成できるかという運用能力が問われているわけです。
生成AIの持つメリットとデメリットをまずは理解し,使用する際には明確な意図を持って自分らしさを含めるようにしましょう!
ところで,先ほど紹介した読書感想文についてですが,悪賢い子どもだと,生成AIの言葉だけを読んでも上手にまとめて提出してくるように思います。
その場合,道徳的な問題は生じるものの,ひとまずそのくらいの厄介者になれたのであれば,社会に出て活躍することもできるでしょうし,それはもはや生成AIに関する問題ではありません(道徳の授業を充実させるなどでなければ対処は無理でしょう)。
この他,有料版の生成AIを購読し,複数の生成AIを使いこなせる生徒が評価的に有利になることも十分考えられます。
とはいえ,これまでの時代においても大人が意見した読書感想文を本人が書き直して入賞することもあったわけで,相手がAIでなくても,周りの人に相談したり手伝ってもらったりして完成させたものを自分の作品として提出するようなことは当たり前のように行われてきたはずです。
もっと極端な例を挙げれば,熱心な親が優秀なトレーナーを付けた結果,自分の子どもが一流のスポーツ選手になった際,真に賞賛されるべきは一体誰になるのでしょうか。
このような理由からも,生成AIの使用自体は強い批判対象とはならないはずです。
ところで,先のメロスは嫌いなこととして「人を疑うこと」と「嘘をつくこと」の2つを挙げていました。
これらは,これからの時代にこそ大いに非難されるべき行為と呼べるかもしれません。
最後までお読みいただいた方,誠にありがとうございました。