令和時代になり,新学習指導要領や教育改革関連のニュースで世の中が騒がしくなってきても,小中高生は必要以上に焦る必要はありません。
というのも,学校側が詰め込み教育だろうとゆとり教育を施そうと,学ぶ側が取るべき勉強法はいつの時代であっても同じだからです。
それどころか,「学習形態がアクティブラーニングに変わろうと,もしくは問題解決能力を育む題材をどれだけ授業で取り上げようとも,生徒側の学習方法がこれまでと同じであれば,授業効果は全く変わらない」という意見が,30年ほど前からすでに提言されています。
今回は,25年前に発刊された「間違いだらけの学習論(西林勝彦)」という本の中から,2020年以降の教育改革において忘れてはいけないことがらについて,いくつか紹介することにしましょう。
「教科書は分厚い方が実は覚えやすい。」
「繰り返し学習すれば覚えられるというわけでもない。」
といった意見にハッとさせられた方は,是非原著の方を読んでみてください。
学ぶ量をあえて多くする

自分が学生だった時代を振り返ってみると,宿題の量やテスト範囲が少なければ少ないほど喜ぶのが当然だと思っていましたが,逆に少ないからこそ覚えにくく,応用がきかなくなってしまうことが多々あります。
例えば,こちらは先の本からの引用ですが,「班田収授の法・荘園の成立・三世一身の法・墾田永年私財法を歴史順に並べなさい」という問題を解いてみてください。
ただ名前と年号をセットで丸暗記するような勉強法を採用していた学生であれば,受験勉強が終わって歴史の勉強をしなくなった途端に忘れてできなくなってしまうことが知られています。
逆に,公地公民を「古代の土地制度の規制が徐々に緩くなって,しまいには崩壊して荘園制が成立した過程」と理解し,その中でこれらの出来事を捉える勉強法ができていた学習者であれば,簡単に,
- 班田収授の法
- 三世一身の法
- 墾田永年私財法
- 荘園の成立
と正しく並べ替えられることでしょう。
メモ
口分田を生前は授けるが,死後は国家が収めるのが「班田収授の法」。開墾した土地は三代にわたって保有を許可するようになったのが「三世一身の法」。そして開墾した田んぼを永久に私有地化できる「墾田永年私財法」を経て,貴族や寺社の私的な領有地の「荘園が成立」しました。
正解できた学生は,ただただこの4つを語呂合わせなどで丸暗記する学習法を採用したのではなく,それぞれの出来事の内容に加え,古代土地制度の衰退から荘園制の成り立ちという歴史の流れを学習しているわけで,これこそ,学習量が多い方が学びやすくなっている例だと言えるでしょう。
要点だけ書き並べた1枚のまとめ用紙(テスト前に作るようなまとめプリント)をひたすら覚えこむより,すごい分厚いけれどマンガ形式であったり,語り口調の予備校の授業の一場面を切り取ったような形式の書籍で背景まで学ぶ方が,わかりやすく記憶にも残りやすい場合があるのです。
もちろん,量が少ない方が覚えやすいこともあり,例えば2桁の数字を暗記するようなときは5個覚える方が20個覚えるより楽なのは明らかでしょう。
ですが,この例が先の口分田の話と違うところは,「覚えるべき事柄に意味があるものか,それとも無意味な情報の羅列なのか」ということです。
数字の2桁暗記は,それ自体に規則性もなく意味のないものですので,こういったものを覚える際の学習法は量を少なくする方がよいことになります。
ですが,実際学校で学ぶ知識のほとんどは意味があるものなので,勉強法を工夫することで忘れにくくなることも覚えておきたいですね。
解き直しでは工夫を加える
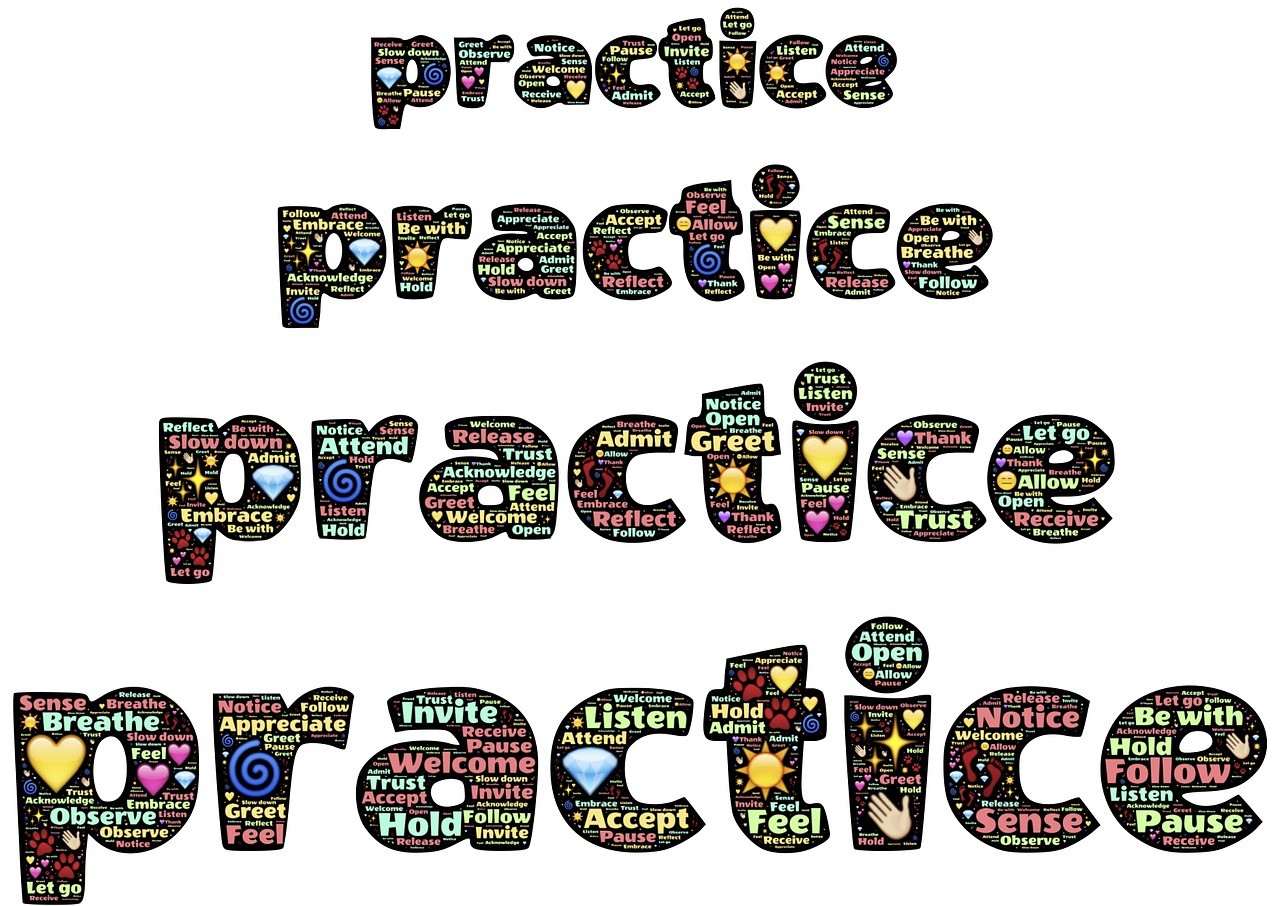
次に考えてみたいのは,同じ問題を数回解き直しする勉強法を採用するときの注意点についてですが,このときただの繰り返しにしないことが重要です。
頭をしっかり使って,学んだ事柄にさらに意味を加えることができて初めて解き直しが効果を発揮するようになります。
例えば1度目の学習で「女の人が氷を持っている」と理解したとしましょう。
それを2度目の復習で「熱を出してしまった子どもの母親が氷を持っている」と学び直すことができると,より「女性」と「氷」の結びつきが強くなるわけです。
下線部が繰り返しの際に学び直した事柄ですが,「女性と氷」に新しい情報(熱が出ている子ども)が加わっています。
逆に,何度繰り返しても頭を使わず,ただ「女性と氷」を丸暗記するような勉強法では覚えていられる期間も短く,復習の効果が薄くなってしまうのです。
というわけで,復習して理解を深めるという学習法を実践するときは,学習者がこれまでに気づけなかった知識を付け加えて理解できるよう,周りの大人が意図的に働きかけたり参照する教材の種類を変えるなどの工夫が大切になってきます。
なお,知識量が増えていくことについてですが,たくさん覚えたからといって新しい知識の吸収が邪魔されるようなことは滅多に起こりません。
むしろ現実は逆のことが多く,これは英単語などで顕著ですが,単語を覚えれば覚えるほど,上記で説明した「意味付けによる繋がり」のようなものが見えやすくなるため,詰め込める単語量がむしろ逆に増えていくことが起こり得るわけです。
この場合,「意味付け」の部分にあたるのは,接頭語や接尾語(unableやunfortunateから,unが付くと否定の意味になることを理解する)であったり,品詞の目印(lyが付くと副詞,-tionとなれば名詞だとわかる)といったものになります。
メモ
より正確に言えば,知識というのはその性質により,単なる知識(個別的知識)か応用のきく知識(法則的知識・接続用知識)かに分かれ,上の例の場合「単語自体」は前者を,「意味付けにあたる知識」は後者をそれぞれ指しています。
まとめ
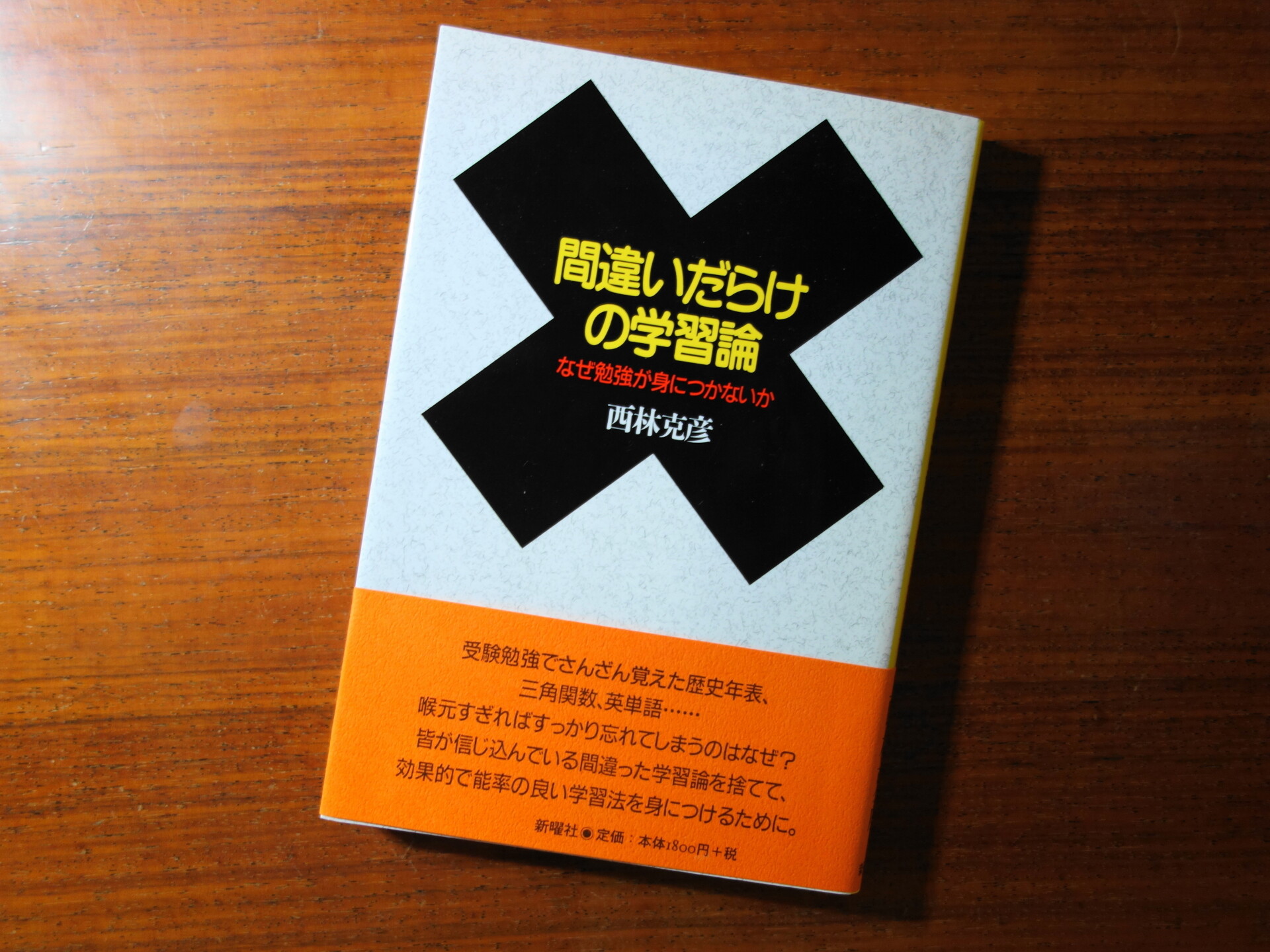
といったわけで,知識を学ぶときはなるべく意味付けして機械的な丸暗記にならないように工夫することが大切で,繰り返し解く際は,その問題で核となるような部分に気づくようでなければ,何度解き直しても真の意味ではできるようにはならないことがわかっていただけたのではないでしょうか。
そんな時に周りの大人ができることは,子どもに見えていない知識を気づかせるための手助けであったり,例えば学校のワークを復習する際であれば,子どもが思考停止した状態で解いていないかをしっかりと確認する必要があるということになります。
なお,こういったことは教育改革が叫ばれるたびにこれまでも言われ続けてきたことであり,令和時代を迎えてからも同じように言われ続けるでしょう。
それほどまでに,こういった勉強法は新しい教育の陰に埋もれがちなことなのです。
「2020年を迎えたからといって,別段新しい勉強法を採用する必要があるわけではありません。」と最初に述べたのはそういう理由があってのことでした。
逆に,これからの勉強法が今までと180度変わってしまうかのように教育改革を捉えてしまうと,これまでですら無視されがちであった効率的な学習法がますます見えにくくなってしまう恐れがあります。
学ぶ方法だけが変わり,学習者側の勉強法についての意識が変わらなければ,今回の結果もゆとり教育などと同じように「教育改革は悪だ。」という結論に終わってしまうかもしれませんね。
今後は「教科書を読んで知識を詰め込む勉強ではなく,体験型学習でもって楽しく学びましょう!」などと,一見もっともらしいことを教育の場で耳にする機会も増えることでしょう。
ですがそんなときこそ,「私たちはこれまでにかなりの回数,夜に浮かぶ月を見てきたにもかかわらず,『東の空から満月が出てくるのは,必ず夕方である』という命題が正しいか間違っているのかについて,100%自信をもって答えられる人は少ない」ということについて考えてほしいと思います。
上記問いの答えは「正しい」ですが,ここから学べることは,目に入っていても注意しなければ見えないことが多々あるということであり,これまで幾度となく体験しているはずのことであっても,自分には見えていなかったということに他なりません。
教育改革をしていなくても,数学の問題を解くこと自体が問題解決能力の育成に有効なアクティブラーニングだったと言えるはずですし,国語の読解問題を通して論理的な思考の習得だってこれまでの学習法で十分に可能だったわけです。
最後になりましたが,もう一つだけ。
学校の授業ではやることが多く,確保できる時間に限りがありますし,集団授業の形態というのはそもそも,成績が上位の人,つまりは要点だけ押さえた説明をしっかり理解できる生徒にだけ効果があるものですので,いったん落ちこぼれてしまった人を決して待っていてはくれません。
その結果,ちょっと勉強で遅れを取ってしまった子が,いざ一念発起して学校の授業をまじめに受けたとしても意味がさっぱりわからないことになり,「自分は頭が悪いんだ」とか「どうせ頑張っても無駄なんだ」と自尊心が傷つけられてしまう生徒が生まれてしまうことになります。
私も塾でそういった子にたくさん出くわしてきました。
しかしそういった子であっても,わからないところを(応用のきく知識を)適材適所で教えてあげれば,すぐにできるようになるという事実をどうか忘れないでください。
そういった働きかけについては,本来ならば,個別指導の塾で1対1でしっかりと教えてもらうのがよいのでしょうが,現代では「スタディサプリ」のようなオンライン教育サービスも出てきており,コスパが良いため教育格差の対抗策としても評判です。
実際,中学や高校において,授業と併用している学校も多いと聞きます。
動画を予習段階で観てから学校の授業を受けるだけでも,授業の理解度がだいぶ改善するので,苦手教科の克服にもおすすめです。
詳しくは以下のページにまとめているので,興味のある方はサービス内容を確認してみてください↓↓
参考
最後までお読みいただきありがとうございました!