2020年に小学校でプログラミング教育が必修化されましたが,使用される可能性のある教材については,文部科学省の運営するサイトにおいて,いくつかの有名ソフトウェアや基板,ロボットなどの教材がまとめられています。
授業が開始になる前の段階から,そういったものを使ってある程度知識を入れておけば,いざ直前になったときに焦らずに済むでしょう。
また,気に入った教材が出てくれば,例えばプログラミング教室に通わせてみようと思った際にも「○○(教材名)が習える教室を探そう」などと,有利に事を運べるはずです。
今回は,プログラミング教材を提供している各社公式サイトを訪問し,どういった教材がどのような意図で提供されているのか理解していきましょう!
小学校のプログラミング教育で使われる教材について

小学校のプログラミング教育について調べるには,「小学校を中心としたプログラミング教育ポータル」というサイトにアクセスするのが一番です。
ここでは実際に小学校で行われているプログラミング教育の事例であったり,使われている教材がまとめられていて,理解を深めることができます。
ただし,学習活動の分類の項目のような意図の部分を読み解くのは難解ですし,実際に自宅で真似しようにも,企業の協力なくしてできないものもありますので,家庭で読む分にはあくまで参考程度に考えておくのが良いでしょう↓
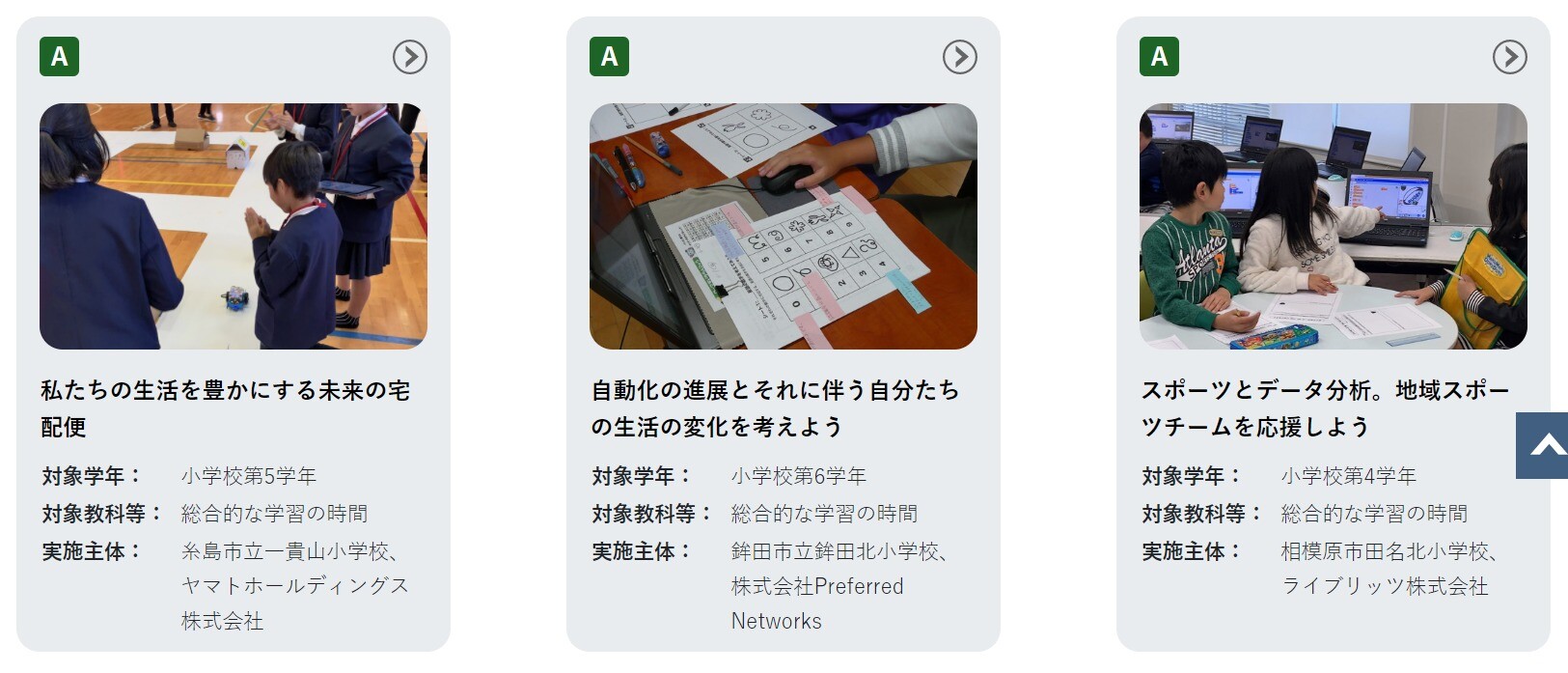
実際は,小学校の教員が参考にするような内容です。
なお,教材を検索すると,無料・有料に問わず,数多くの教材が表示されてきます↓

ここで,教材のタイプについても学ぶことができ,以下の7つのものに分けられています↓
テキスト言語,ビジュアル言語,タンジブル,アンプラグド,ロボット,ゲーム,その他
このうち,いまいちイメージがわかないけれども重要なのは「ビジュアル言語」で,これは図形や命令の書かれたアイコンやブロックなどを並び替えるなどしてプログラミングを行うものです。
小学校のプログラミング教育では,嫌いにさせないことが重要だと言いました↓
-

-
小学生のプログラミング教育!問題点や中高での学びも
2020年の4月から小学生のプログラミング教育が必修化されました。 もちろん小学1年生であってもその対象です。 とはいえ,「プログラミング」という難しそうな響きとは裏腹に高度な専門性は求められず,あくまで中学や高校の学び ...
続きを見る
なので,小難しいアルファベットを入力するテキスト言語より,圧倒的にビジュアル言語の方が好まれます。
とはいえ,複数のタイプに位置する教材もありますし,小学校の6年間を通してずっと同じ教材だけを使うこともないです。
それでは,以下でいくつか代表的なものを紹介していきましょう!
プログラミング用ソフトウェア
プログラミングの必修化で小学生が使うことになるソフトウェアは,直感的に操作しやすいビジュアル型のプログラミング言語がほとんどです。
新しい製品も年々登場してきてはいますが,これまでに使用されてきたソフトウェアの中で特に有名なのは,
- プログラミン
- Scratch(スクラッチ)
- Viscuit(ビスケット)
- プログル
- Hour of Code
の5つとなります。
ここでは,最初の3つを例に,どのようなことができるのか確認してみましょう!
プログラミン

- 名称:プログラミン
- 提供:文部科学省
こちらは「プログラミン」と呼ばれる動物を積み重ねて,イラストを動かしてアニメ―ションを作成できるソフトウェアになります。
各プログラミンは単純かつ明確な命令を持っているのですが,それらを組み合わせることで,色々な動きが楽しめるのがウリです。
工作用のデスクマット上に絵を配置し,その上にプログラミンを配置します。
下の画像では,犬の絵を選択したのち,6匹のプログラミンを試しに積んでみましたが,この後,再生ボタンを押すことで,プログラミングした通りに犬のイラストが動いて,仕上げに「わん」と鳴かせることができました↓

自分が作ったプログラムは保存できますし,気に入ったお手本があれば,そのプログラミング内容について詳しく確認することもできます↓

特に最初は,他人の作例から学ぶのが良い方法です。
「笑いの起こるプログラミングを何とかして作ろう!」と頑張ってくれれば最高で,遊び心に富む小学生向けに大変に使いやすいソフトウェアに仕上がっていると感じました。
追記:残念ながら,Adobe Flash Playerの提供とサポートが終了したことに伴い,2020年の年末をもってサービスを終了してしまいました。
Scratch

- 名称:Scratch
- 提供:MITメディアラボ
先に紹介したプログラミンは,実はこの「Scratch」を参考に設計しています。
プログラミンが入門用だとしたら,実施事例が多いScratchは,標準レベルのソフトウェアです。
新しいソフトウェアが続々と登場している昨今ですが,これと次に紹介するViscuitを中心に,多くの授業が今後も行われていくように私は感じています。
主に8歳から16歳向けで,世界規模でみると数百万人の人に使われており,作例の自由度も広いです↓

他人が作ったものを覗いてみると,実際に遊んだことがあるTVゲームに似た作品が数多く並んでいることに気が付くのですが,中身をみれば,かなり複雑なプログラミングによって動作していることがわかります↓
ゲームクリエイターやアニメーターになる人の初めの一歩は,こういうところから始まるのかもしれません。
なお,実際にScratchを使って,創造力を育んだり論理的思考を学んだりできる小学生向けの動画があるので,是非ご視聴ください(ちょっと勉強要素が強めですが)↓
Viscuit

- 名称:Viscuit
- 提供:合同会社デジタルポケット
Viscuitは文字を介さず,自分で描いた絵を動かすことのできるソフトウェアです。
パソコンやタブレットの他,スマホでも利用することができます。
早速,公式サイトに行ってみましょう。
「やってみる」という魚の絵をクリックし,次に「はらっぱ」を選択します。
さらには,好きな色の背景を押して,出てきた鉛筆のマークをクリックすれば準備は完了です。
この先の操作に関して,こちらも指導者向けの動画が利用できるので,以下で確認してください↓
魚が口を開閉しながら前に進むところまで覚えたら,かなり自由に遊ぶことができます。
プログラミング用基板

次章で紹介するロボットと比べると実に味気ないように思いますが,避けて通れないものが基板とでしょう。
教材としては,
- micro:bit(マイクロビット)
- Raspberry Pi(ラズベリー・パイ)
が有名です。
先に紹介した文科省のサイトでは「その他」に分類され,パソコンまたはモニタやキーボードと接続して起動し,パーツの一部として機能します。
パソコンを自作した方であれば馴染みがあるであろう基盤ですが,小学生にとってみれば,そうした仕組みすら新しく学ぶはずのものです。
以下はマイクロビットのものですが,パソコンの専用アプリで作ったプログラムを転送すると,音や文字などを表示してくれます↓
その他の機能としては,
- LEDで光らせる
- 光や温度センサー
- 動きセンサー
- 無線通信
などがあり,文字を映し出す単純なものにとどまらず,次章で紹介するロボットにも基盤は使われています。
ラズベリーパイのように,Scratchやマインクラフト(YouTubeのゲーム実況でも有名)と連動しているものもあるので,発展学習またはつなぎの教材として登場することが多いです。
プログラミング用ロボット

プログラミングがきっかけでロボット研究に目覚める生徒は数多くいることでしょう。
今だと自律型の自動車でしょうか,将来性のある魅力的な分野です。
代表的な教材としては,
- 教育版レゴ マインドストーム
- アーテックロボ
が有名で,基本的には,ブロック・センサー・モーターなどを組み合わせてはロボットを完成させ,専用のソフトウェアで起動します。
前章までに紹介した教材の集大成的なものなので,総合的に理解を深めることが可能です。
アイコンを並べるだけでもプログラミングができますが,レゴの場合,JavaやC言語による制御も可で,マインドストームにハマる小中学生はかなりいます↓
楽しいだけでなく,かなり本格的なプログラミングまで学べてしまうため,この先となると,いよいよプロ仕様のpythonに進むくらいでしょう。
なお,マインドストームはかなり昔からある有名どころなので,多くのロボット教室で学べるはずです。
小学校におけるプログラミング教育の実施例

ここでは,学術都市であるつくば市の小学校の例をみてみましょう!
2018年度に実施されたカリキュラムは「コアカリキュラム」と呼ばれ,基本の骨組みは上記画像にある計画に沿って行われました。
小学1~2年生では,ソフトウェアで紹介した文部科学省の「プログラミン」が採用されています。
懐かしの「スイミー」の1場面から,音読に合う背景をアニメーションにする国語の授業の一環として,早速1年生の段階からプログラミング教育が行われたわけです。
その後,小学3年生から5年生までは,より複雑な「Scratch」が採用され,理社のクイズ作成や図形を描く授業が行われました。
そして小学6年生になると,いよいよ「マイクロビット」の基盤を利用し,プログラミングで作動するセンサーづくりから外国語活動まで幅広く用いられることになります。
このように,児童の発達段階に合わせてプログラミングの学習計画が組まれることが普通なので,学年ごとに使う教材は変わっていきますが,あくまで何か別の教科の理解を深めるためにプログラミングが利用されていることに注意してください。
例えば,上の小5の社会の授業では,Scratchを扱う技術のみならず,食料品の産地についても理解しておかなければいけません。
また,各教材に慣れ親しむためにも,一度決めた教材は一定期間使うことになりますが,とはいえ段階的な積み重ねが必要になってきますので,もしも,操作や学習内容の面で一度遅れを取ってしまえば落ちこぼれてしまうでしょう。
加えて,特に子どもの目には魅力的なロボットのような教材は,学校だと予算や指導が難しい関係で,あまり使わせてもらえないことも覚えておきたいものです。
特に,人より理解に時間がかかるマイペースな子や発展的な学習を意欲的に学びたい小学生は,学校任せにせず,積極的に自宅学習を進めるようにしましょう。
まとめ

今回は,小学校のプログラミング必修化で使われる可能性の高いソフトウェアや基板,ロボットを中心に紹介してきましたが,その他にも小学生に人気のマインクラフトを教育向けに改良したものなども登場してきています。
今後ますます,小学生が使いやすいものが登場してくるかと思いますが,プログラミングを通して論理的な考え方を身に付けるためには,何よりも小学生自身が楽しんで学べることが大切です。
同じ教材を使っていても,教え方一つで授業の楽しさは全然変わってきてしまうこともあり,特にプログラミングの初印象が悪くならないように,評判の良いロボット教室・プログラミングスクールに通ってみることも,良い結果につながることが多いでしょう。
例えば,ScratchやLEGOのマインドストームについては通信講座でも学ぶことができます↓
今回はZ会プログラミング講座の教材を例に,LEGO Educationを使った学びについてまとめてみたいと思います。 その順序ですが,まずはどのような学びが可能になるのかから始めることにし,身に付く資質・能力や,上手に利 ... 続きを見る

![]()

Z会プログラミング講座の学び方!LEGOを自由自在に動かそう
私も学んでみましたが,こういったものを取っ掛かりにして,さらにスクールに足を運ぶという流れになるはずです。
さて,学校の実際の授業についてですが,教員側は基本的に,自分たちで何かを新しく作り出すよりも,うまくいっている授業例を真似して,少しだけ自分のクラスに合うように改良していくことが多いように思われます。
ゆえに,今回紹介したような,現時点の段階から頻繁に使われている教材を用いて学んでおくことが,プログラミング教育の予習段階としてはおすすめです。
特に,教員の研修用教材として,先に紹介したScratchとViscuitが代表例として取り上げられていることもあり,これら2つは授業のどこかで用いられる可能性が高いので,保護者の方でも興味がある方は,チェックしてみてください↓
参考
最後までお読みいただきありがとうございました。