Z会は自分が高校生だった時に大変お世話になりました。
Z会出版の参考書はもちろん,通信教育から東大進学教室まで多くのサービスを利用してきたように思います。
それから長い年月が流れ,今ではZ会の映像やAsteriaで利用できるようなオンライン教材が新たに加わるなどしていますが,基本的には当時と同じく奇をてらわず王道を行く教材を提供し続けてくれているようです。
そこで今回はそんな「Z会の通信・映像・教室のメリットやデメリット」についてまとめてみることにしました。
サービスごとに1つ1つみていくことにしましょう!
Z会の通信教育のメリットとデメリット
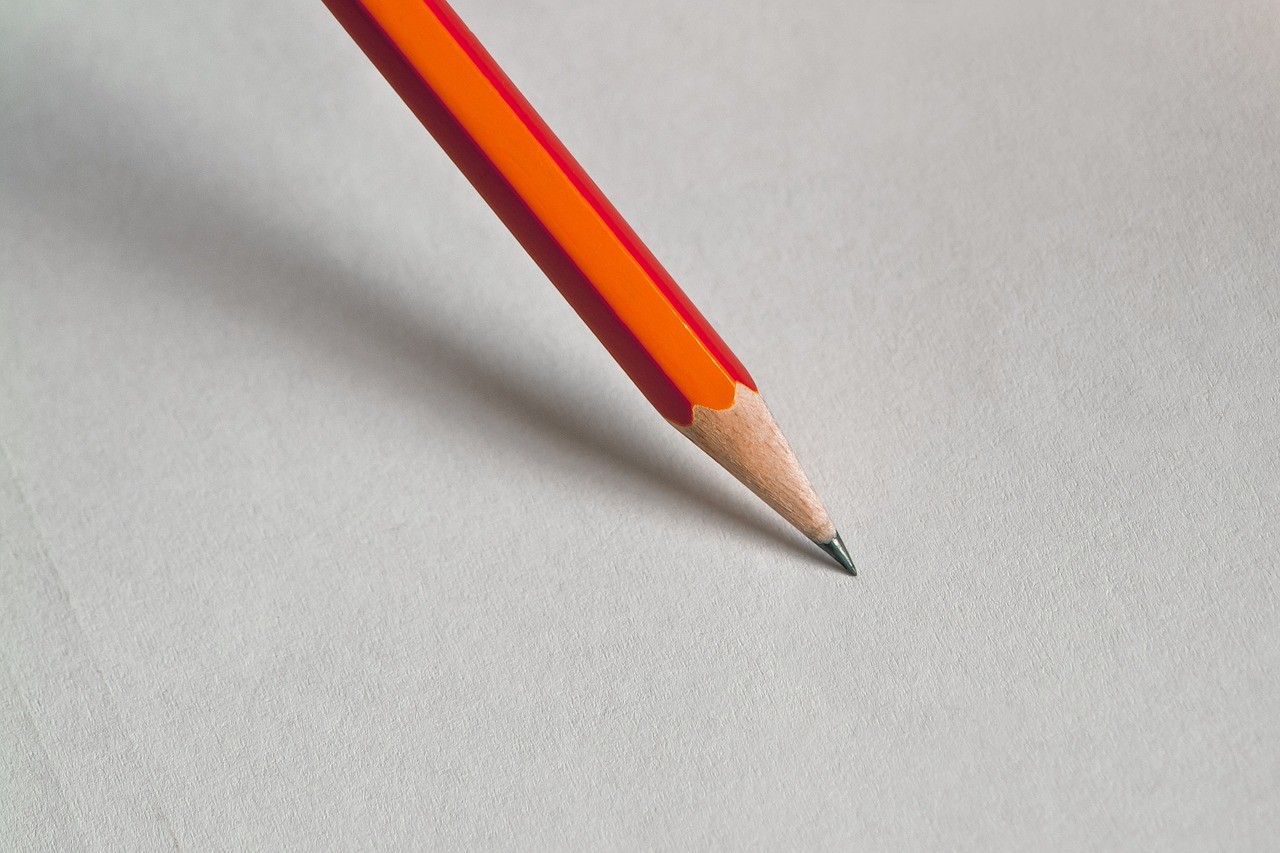
メリット
Z会の通信教育を利用するメリットですが,
- 取り組みやすさ
- 良質な教材
- 続けやすい料金
の3つが挙げられます。
本教育が始まったのは1961年のことなのですでに60年以上の歴史があることになりますが,その間で多くのノウハウが蓄積されたことでしょう。
まずは上に挙げた1つ目についてですが,取り組みやすさは良好です。
教材には目標時間が細かく設定されており,アプローチは明快かつ無駄な問題が見られません。
Z会の特徴として,年月が経過しても教材の内容が変わりにくいところが挙げられますが,同社が時代の変化に鈍感というわけではなく,最近だと公立の高校生がより効率的に勉強できるようにとレイアウトを大きく変えてきた大胆さが光ります↓
長年そうだった手書きにこだわるかと思いきや多くのコースがデジタル化(iPad化)され,これによりデータの管理がしやすくなり,答案の返却速度は上昇しました。
次に教材の質についてですが,これは「通信教育における生命線」になるでしょう。
先ほど教材内容があまり変化しないと述べましたが,これは別の見方をすれば,いつの時代にも通じる知識を伝えているとも考えられるわけです。
実際,私が現在の大学入試の問題を解く際,Z会で学んだ当時の知識に頼ることが多いわけですが,合格点を下回ることはありません。
塾講師としてより詳しく言わせてもらえば,多くの参考書で見かける問題だけで構成されていないところが大きな魅力です。
これはつまり,市販の参考書では学ぶことができない知識まで身に着けられるということで,もしその知識が入試で問われることになれば,他の受験生と確実に差をつけることができます。
実際,MARCH以上の大学入試においてそういった出題がいくつか確認できました。
私は当時,Z会の添削の仕事も並行して行っていたのですが,そこで当たり前のように指導に使っていた内容を自分の生徒に尋ねてみたところ,「初めて聞いたよ」という返答だったわけです。
私の学生時代にはどの参考書にも載っている当たり前の知識だったのですが,今ではそれを教えない高校も多いようで,時代の流れに驚かされたと同時にますますZ会が好きになりました。
また,以前の主力だった高校生向けのコース以外にも,新しい学習指導要領に沿った内容で幼児や小学生向けのコースも充実してきたわけです。
詳しくは以下で紹介しているキャンペーンページで確認していただきたいのですが,通信教育なだけに料金は比較的安めで,1科目なら年間数万円で利用できます↓
デメリット
そんなZ会の通信教育ですが,自分の学力よりわずかに上のレベル(大半の人は「標準」で十分です)を締め切り日だけ守って提出するだけで十分学力が高まるように設計されています。
しかしその反面,背伸びしてレベルの高いコースを受講してしまって消化不良を起こしてしまう会員がいるのも事実です。
目安として,添削課題で2割も正解できないようであれば,速やかにコース変更を検討してください。
また,添削問題を提出するだけで満足してしまい,復習に時間をかけないことも問題視されています。
学習者が幼児や小学生の場合は,保護者が横で一緒になって指導する必要も出てくるでしょう。
学習時間の目安としては1科目あたり週2時間前後となっています(一部プログラミングの講座などで,1ヶ月で2時間の学習が目安になっているものもあります)。
複数科目を受講する場合だとその時間が倍々になっていくわけですから,あれもこれもと欲張って取りすぎないことが大切です。
まずは自分が得意にしたい科目をきちんとやり通すところから始めてください。
得意科目を1つでも作ることができればそれが良いモチベーションとなり,他教科の成績も引きずられるように伸びてくるものです。
ちなみに,学校の定期テストが近かったり部活や行事だったりで,どうしても添削答案を締め切り日までに提出できないこともあるでしょう。
その場合,休みの日か長期休暇にまとめてやる羽目になりますが,これ以上Z会の通信教育を続けてはならないと判断できる基準があります。
それはずばり「夏休みにおける提出状況をみる」ことです。
これほどの長期休暇においても溜まった添削課題を提出することができないようであれば,この先ずっと出せないままでしょう。
夏休みに添削課題を出せなければ通信教育を用いた学習は向いていません。
このことをしっかりと胸に刻んでおきましょう。
Z会の通信教育のメリットとデメリットについてまとめると以下のようになります↓
- 質の高い添削サービスが受けられる
- 時代の要望に応じた学習カリキュラムを提供
- Z会の教材でしか得られない知識がある
- 難易度が高いのでコース選びを誤りやすい
- 答案を貯める生徒には向かない
Z会の映像のメリットとデメリット

メリット

それでは早速,映像授業のメリットについてみていきますが,こちらは「速習できる」点に尽きます。
これはどういうことかと言えば,学校で習ったり参考書を使って独学したりするよりも圧倒的に早く学べるという意味です。
学習範囲が膨大であっても,学校で週に数回しかない授業を待つことなしにどんどん学んでいけますし,Z会に在籍する実力ある講師たちが解説してくれるため,多くの場合,学校の先生よりもわかりやすく授業を受けることができます。
学習スタイルは人それぞれですが,私の塾の生徒をみる限り,「文章を読んで学ぶよりも人が語ってくれる方が学びやすい」と主張する生徒は多いです。
画面越しであっても集中力さえ維持できれば,通常の対人授業と何ら効果は変わりません。
試験本番までに時間があまり残っていないが逆転を狙う必要があったり,自分から率先して学ぶ必要性を感じたりした際にはZ会の映像をおすすめします。
料金については,高校生の場合,1年分の講座(150時間くらいの内容)が一括で20~30万円ほどです。
このとき支払いを「分割」にしてしまうと教材を一気に手に入れることができないことがあるため,1年分を一括で支払い,数ヶ月で全範囲を速習してしまうのが最も良い方法であるように感じています。
この他,長期休暇の数日間で集中的に学ぶ取り方もできますし,苦手科目があったりZ会の教室に通う前の基礎知識の整理だったりに受講してみるのもありでしょう。
デメリット
ところで,上で述べた学習形態で恩恵を受けられるのは自分でスケジュールを管理できる生徒のみです。
たとえ予定をあらかじめ決めて貰えたとしても,いずれは自分の生活リズムに合わせて独力でスケジュールを立てられるようになる必要があります。
このような時には,勉強の計画を管理してもらえる指導者が欲しいと思うはずです。
利用料金については個別指導の塾に通うよりかは安く済むためメリットの1つとして挙げましたが,Z会の映像では通塾したときと同様,1年間を通したカリキュラムが組まれることも多いため,途中で脱落してしまえば逆に高くついてしまう悲劇もないわけではありません。
その他,例えば病気で学校を休みがちな生徒や,能力はあるけれど勉強をこれまで全くしてこなかったような子が一念発起して学ぼうと思った場合に,最初こそ真新しさから食いついてみたものの,しばらくすると意欲が急激に低下してしまうこともあります。
映像授業の性質上,どうしても雑談が少なくなる傾向にあるため,勉強することを楽しいと思えない生徒には向きません。
「勉強の遅れを取り戻すぞ」といった強い意志を持っていたり,授業の進度が遅い学校に在籍している子が恒常的に不満を感じていたりする状況でなければ,モチベーションの維持がしにくいのがデメリットです。
これにもう1つ,Z会の映像を使って成績が上がらない例があるとすれば,学力が低い生徒が受け身の姿勢で学び続けてしまう場合でしょう。
当然ながら講師は動画内にいるため,やるべき課題をやっていなくても叱られることはないわけです。
どうしても怠けてしまいそうな子は,同じZ会の映像を教材として用いながらも予習内容の理解を第三者にチェックしてもらえる「ディアロ」などを検討してみるとよいかもしれません(後述)。
本章で述べたZ会の映像のメリット・デメリットをまとめると以下の通りです↓
- 短期間で素早く学ぶことができる
- 通塾するよりも安く済むことが多い
- 勉強のやる気の維持が難しい
- 受け身の生徒には向かない
Z会の教室のメリットとデメリット

メリット
最後はZ会の教室についてです。
先述の通り,こちらにも映像授業のコース(対人ではなく,通った校舎で映像授業を見るもの)がありますが,「24時間365日のフォロー」や「スマホ家庭教師」などの独自サービスがさらに付いてくる点で別物と言えます。
通塾して映像授業を受ける形態であっても,スタッフに質問ができたり自習室を利用できたりしますが,私のおすすめはやはり対人授業を受けることです。
そもそも料金が映像と対人の授業で同額なのでなんだか損した気持ちになるものですし,教室でライバルたちの存在や講師の視線を意識しながら授業を受けることには,デジタルから得難い魅力があります。
都内だと優秀な学校から通っている生徒も多く,ちょっとしたところで彼らの能力に驚かされることも少なくないでしょう。
授業の進度は学校よりも早く,それでいて扱う内容は深くなっているのが普通で,誰でも超難関大学や医学部に合格できるわけではありませんが,少なくとも高校1~2年生であれば,講師に言われたことをただこなしているだけでもトップクラスの学力に到達することが可能です。
たかが1週間に数時間のやり取りであっても,塾講師というのは生徒に大きな影響を与えることができる存在で,これは通塾することの明らかなメリットと言えるでしょう。
小中学生向けになりますが,Z会の教室の数も一昔前と比べるとずっと増えました↓
首都圏の教室例
お茶の水,葛西,渋谷,自由が丘,新宿,高田馬場,二子玉川,成城,池袋,荻窪,大泉学園,三鷹,立川,調布,府中,八王子,町田,横浜,日吉,大宮,川越,南浦和
教室によっては個別指導の形態が選べる場合もあります。
なお,このくらいの年頃の生徒だと,信頼できる先生に出会えたことをきっかけに物凄い勢いで勉強にのめりこむことも珍しくありません。
問題はそういった先生に出会えるかどうかなのですが,私のかつての師匠である鈴木正人先生や國分弘章先生や舘野直子先生がまだ現役で教えられているので大丈夫そうですね。
当時は横浜教室や恵比寿教室,そしてお茶の水教室の3ヶ所を行き来し,終電で帰ることも日常茶飯事な受験生でした。
デメリット
Z会の教室に通塾するデメリットとしては「時間に余裕がないといけない」ことと「お金がかかる」ことです。
Z会の教室には集団授業の他に個別指導のサービスもありますが,指導レベルや置かれる環境から考えて,集団授業を取ることを前提に話をしていきます。
こういった通塾スタイルにおいては,欠かさず通うことに加えて予復習をしっかり続けられることが絶対条件です。
無駄が生まれないようカリキュラムはきつめに組まれているので,一度休んでしまっただけでも抜けてしまう分野が出たり,置いていかれてしまう可能性が高まったりします。
予復習をせずに授業の時だけ頑張ったとしてもできるようにはなりません。
講師が厳しい先生だと授業中に発言するよう指名されたり,宿題をやったかどうかチェックされたりもするために問題ないのですが,優しい先生だとついサボってしまう生徒もいるので注意しましょう。
勉強ができるようになるコツについて言わせてもらうと,「一度習ったことを絶対に忘れないぞ!」という強い気持ちで授業に臨むことが大切です。
なお,料金は授業料以外に電車賃や参考書代がかかるので,1科目につき年間25~30万円くらいはかかると思っていてください。
他の大手予備校だと成績が良い生徒の授業料が半額や無料になることもあるでしょうが,Z会ではそのような不公平な話は聞きません。
人気講師の場合は常時満席になるため不可能ですが,気になる方は一度体験授業を受けてみてください。
最後に本章の要点をまとめましょう↓
- 塾において講師やライバルから学ぶことは多い
- 欠かさず通って予復習する必要がある
- 料金は他と比べれば高くなる
Z会と併用したいサービス

これまでみてきたように,Z会で学んだことを身に付ける努力さえ怠らなければ揺るぎない学力が身に付けられるわけですが,より日常的な問題,例えば,学校のテスト対策としてみた場合に個別対応しにくいといった弱点があります。
先述したように個別指導を利用できたりもしますが,毎回個別に質問をしたいわけではなく特定の時期に限って少し聞きたいことも多いので,年間を通して個別指導を受けるほどではなかったりするわけです。
また,Z会以外の参考書で独学していてわからない問題に出会ってしまったときはどう対処すれば良いでしょうか。
そういった場合に備えて,長期休暇のみ家庭教師を付けることや,最近では塾のフォローをするための塾すらあるので,いざという時のライフラインについても検討しておいてください。
なお,Z会の映像の章で触れた「ディアロ」ですが,こちらは映像で学んだ内容を講師にプレゼンテーションで説明し,理解度を第三者に確認してもらう対話式トレーニングが優れています。
こちらはZ会が栄光ゼミナールとタッグを組んで立ち上げた塾ですので,全くZ会と関係がないわけでもありません。
人の手が入る分,授業料はかかってしまいますが,映像授業のデメリットを少なくすることに成功しているのは明らかです↓
また,映像授業を月額2千円強で利用できる「スタディサプリ」はZ会の映像の対抗馬になり得る存在ですが,メインをZ会にした場合のフォローとして使ったりZ会で受講していない科目を受講したりすることもできます↓
自分の都合に合わせて複数のサービスを組み合わせたり,使いたい時にだけ使ったりする学習形態が主流になってきた昨今です。
従来の学び方にこだわらず,来たるべき時に備えて早い段階から色々と試してみては,自分なりの答えを出しておくことが大切だと思います。
まとめ

実際は学年の違いごとに利用法は多少変わるでしょうが,学年に関係なく言えることを中心に書いてきたつもりです。
今回紹介した3つのZ会のサービスのメリット・デメリットについては,以下のようにまとめることができます↓
Z会のサービスごとのメリット・デメリット
Z会の通信:取り組みやすく,教材はオリジナルで値段は安めだが,復習が甘くなったり教材が溜まったり,レベルが合わないことがあったりする。
Z会の映像:短時間で網羅的な学習が可能で逆転を狙う際に重宝するが,受け身の態度で動画に集中できないと効果は薄い。
Z会の教室:講師やライバルとの化学反応で爆発的な伸びに期待でき,勉強の楽しさに気づくこともあるが,講師との相性や料金面で問題が生じる可能性がある。
このうち自分に合うものを1つ選んで決めても構いませんが,「英語は教室に通うが,理社は通信教育で」などと使い分けることも可能です。
すぐ上の章で紹介した別会社のサービスも選択肢の1つとして検討してみてください。
なお,自分が考えるZ会という会社自体の弱みとして「説明がわかりづらく,宣伝が下手」というものがあります。
記事を書くにあたって公式サイトを確認してみても,良いサービスを提供しているにもかかわらず仕組みがよくわからないことも少なくありませんでした。
とはいえ,教育改革に対する動き出しは早かったですし最近は色々と大胆な試みをして露出も今日介しているようなので,頑張っている会社であることは事実です。
過去には新海誠監督の動画を作ったりしていますし,CMを目にすることもありますが,みなさんはご存じでしたでしょうか↓

受験を見据えたときに「学校の授業だけではダメだ」と思うことがあったとしたら,その直感は高確率で当たっています。
実際に塾で教えている身としては,学校側がもっと頑張って生徒を教育していただけると助かるのですが。
最近だと「成績が悪いのは学校ではなく塾のせいだ」と考える家庭も多いようですが,たかが週に数日塾に来て勉強したところで家で過ごす時間の方が圧倒的に長いわけですから,学力に大きく影響するのは家庭学習であることを強く認識しておいてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。