今回は,キットやツールを用いたZ会プログラミングシリーズの口コミと料金を中心にまとめてみたいと思います。
幼稚園の年長さんから始められる講座の他,ソニーのKOOVやRasberry Piといった有名どころを用いて小学生や中学生が学ぶ講座が存在し,通学する必要がない通信教育の形態で学べるところが大きな魅力ですが,3ヶ月~12ヶ月で完結するオリジナルのカリキュラムには,一体どのような特徴があるのでしょうか。
Z会プログラミングシリーズは全部で3つの講座に分けることができますが,それぞれの特徴やコース内容についても触れていくので,是非参考にしてください。
Z会プログラミングシリーズの特徴
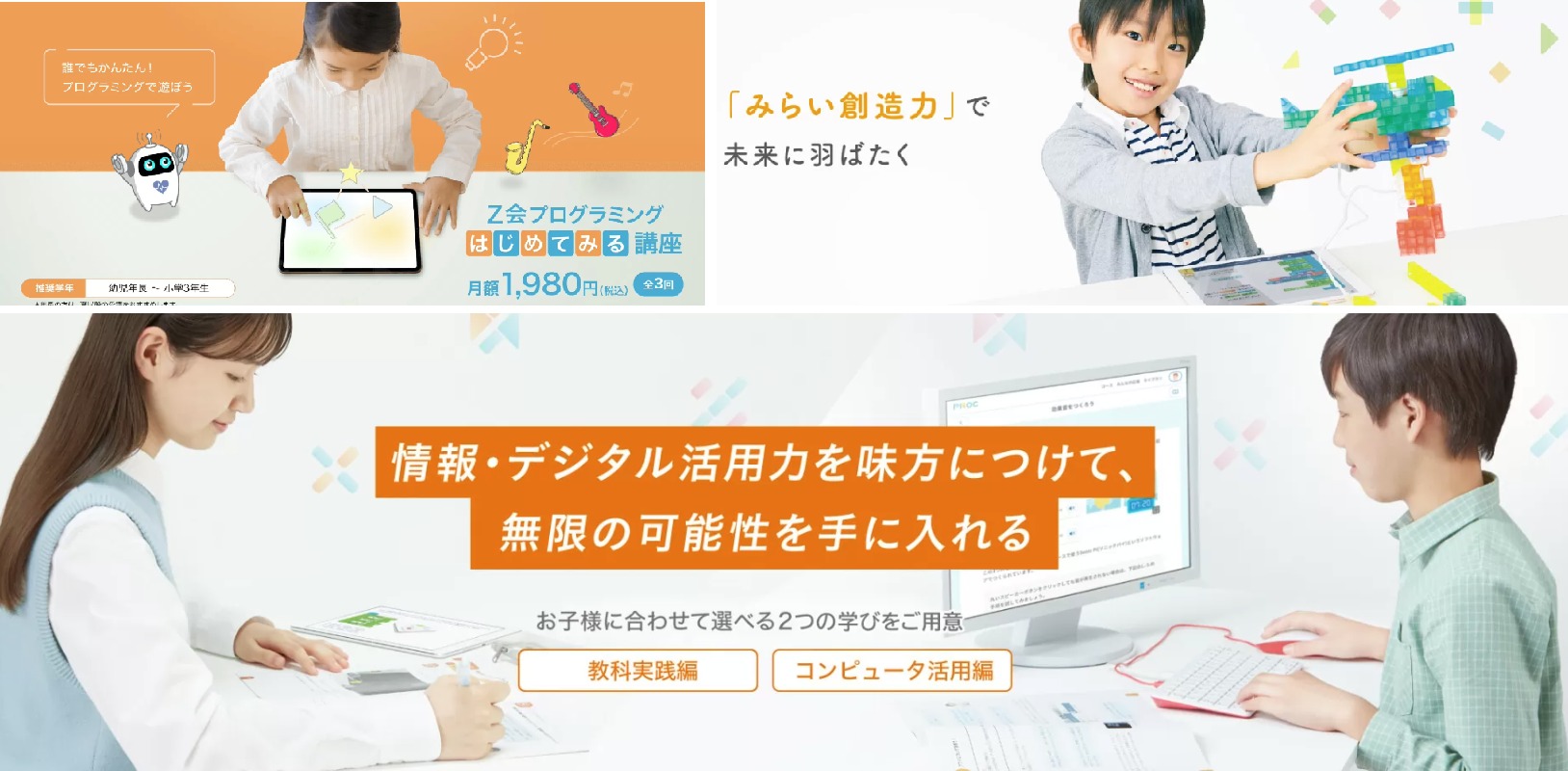
まずは,Z会プログラミングシリーズの特徴についてみていきましょう!
自宅で学べる
教育改革にいち早く乗り出したZ会が,小学生のプログラミング的思考(創造力・論理的思考力・問題解決能力)の育成にぴったりなサービスを始めたのは2019年のことです。
まだまだプログラミング教育に注目が集まっていない段階から,習い事で多忙な現代の小学生を対象としたサービスを開始したことは,今振り返ってみると,時代の流れを見据えた英断だったように思います。
とはいえ,Z会では古くから通信講座のノウハウを積み上げてきたわけですから,突然の思い付きから全く新しい事業を始めたわけではありません。
例えば,所要時間にして2時間で終了する月ごとの課題(withソニーのみらい講座のみ4時間)は,土日を上手に利用すれば毎週30分(または隔週で1時間)くらい取り組むことができればOKです。
これは,習い事で忙しい最近の学生事情を反映したもので,最長でも1年間で完結するカリキュラムなので長々と続ける必要もなく,「とりあえず,子どもにプログラミング教育を一通り学ばせることができた」と親が安心できるところも大きな魅力でしょう。
そもそも,本格的にプログラミングを学ぶとなれば,学校の授業では対応しきれません。
これはつまり,学校はあくまで興味を持つきっかけを提供する場にすぎないということで,次段階として,子どもがZ会のプログラミングシリーズを通して興味を深めるようであれば,本格的なプログラミング教室に通うも良いですし,使っていたソフトの参考書を買って読んでみるといった流れを踏むのがおすすめです。
Z会の講座を挟まずにいきなり教室に通わせても構いませんが,プログラミングの場合,キットを使った指導がどうしても中心となってしまうため,初期段階から高い費用を請求されてしまう傾向にあります。
大枚をはたいたのにもかかわらず長く続かなかったとあらば,残念な結果になってしまったと後悔してしまうかもしれません。
親だけならまだしも,子どもまでもが失敗体験を得てしまうようであれば問題です。
とはいえ,現代は色々な習い事に手を出すことができる点を逆手にとって,少し足を踏み入れた状態から進退を判断することができます。
この段階でつまずく子どもは少ないと思うので,教養の1つとしてとりあえず学ばせることができるというのがZ会のプログラミング講座の特徴です。
Sonyのキットを使える
Z会のプログラミングシリーズでは,ソニー・グローバルエデュケーション製の「KOOV」というキットを使うことができます↓

![]() こちらはプログラミング的思考の育成を目指すものですが,3年間かけて学べるカリキュラムは全コースで最長となっていて,扱うテーマも身近なものから始まり,抽象的,そして社会的なものへと年ごとに変わっていきます。
こちらはプログラミング的思考の育成を目指すものですが,3年間かけて学べるカリキュラムは全コースで最長となっていて,扱うテーマも身近なものから始まり,抽象的,そして社会的なものへと年ごとに変わっていきます。
最初のLEGOコースが登場してから約1年後に満を持して開講し,国産で固有ファンの多いSony製のキットがコースに加わったことを喜んだ方も多かったはずです(KOOV自体は数年前から販売されているものです)。
2023年4月11日をもってLEGOの講座は新規申し込みができなくなりましたし,同じZ会の「中学技術活用力講座の教科実践編」においてもVIRTUAL KOOV(プログラミングアプリ)の形で登場してくるので発展性もあります。
なお,キットは3年間同じものを使って学ぶので,1度購入してしまえばあとは受講料だけで済むのも良いところです。
Raspberry Pi 400を使える

小学校のプログラミング教育で使われる教材の記事にて,プログラミング用基板をいくつか紹介しましたが,そのうちの1つがこのラズベリーパイでした。
低予算で導入できて持ち運びも用意とくれば,自宅学習にピッタリです。
見た目は完全にキーボードにしか見えませんが,一式購入すると,電源ケーブルとHDMIケーブルにマウスなどが付属してくるので,それをテレビやモニターと接続してみると,ラズベリーパイオリジナルのデスクトップ画面が起動します。
とりあえず,パソコン本体とキーボードが合体したものだと考えてみるとよいかもしれません。
Z会では中学技術活用力講座のコンピュータ活用編で使うことになりますが,受講者は通常で買うよりも安く手に入れることができるのが特徴です↓
Z会プログラミングシリーズのコース紹介
それではZ会プログラミングシリーズのコースについて,より詳しく説明を加えていきましょう!
全部で以下の3コースがあり,年長から中3生までが対象です↓
- みらいwithソニー・グローバルエデュケーション
- はじめてみる講座
- 中学技術活用力講座(教科実践編・コンピュータ活用編)
みらいwithソニー・グローバルエデュケーション
Z会プログラミング講座みらいでは,テキストとなる「みらいワーク」とロボットの「KOOV」の2つを併用しながら問題解決能力を身に付けます。

テキストはスモールステップ式に段階を踏んで学べるZ会オリジナルの教材のため,小学生が十分に自学自習できる内容ですが,保護者ガイドも付いていて,学習の狙いや子どもにアドバイスするときの方法について知ることが可能です。
KOOVのロボットやアプリのイメージについて理解を深めるためには,以下の動画を観てください↓
この他,本コースにおいては,プログラミングの実力が付いたことを診断するテストが全2回実施されるので,客観的な評価が受けられるところも魅力でしょう。
はじめてみる講座

はじめてみる講座は3ヶ月で完結するのが特徴で,プログラミング未経験の年長さんから小学3年生が対象です。
Sctachの機能を使いながら理解していくスタイルは,2つ前の講座と同じですが,より基礎的な内容を学ぶことができます。
全3回のカリキュラムは,やるべき課題が明確です↓
はじめてみる講座のカリキュラム
1回目:ゲーム作りを通して,キャラクターの動かし方を始めとする基本を学ぶ
2回目:入力した内容によって音色が変わる楽器を作り,記録や再生について学ぶ
3回目:PCやタブレットのカメラ機能やマウス操作を通して,センサーについて学ぶ
教材については,子どもが独学できるよう,動画を見ては実際に動かして試行錯誤できるようになってており,毎月4枚のカードが届くので,スモールステップ方式で1つずつ課題をこなしていくことになります。
第1回目と2回目の教材として使うことになるScratchですが,プログラミング教材として最もポピュラーなものの1つです。
子どものやる気を高める仕組みもあるので,気楽に始めたい方にはもってこいの講座でしょう。
中学技術活用力講座 教科実践編

2025年1月の共通テストから「情報」という教科が加わります。
その時に備えるべく,2022年度から,Z会プログラミング中学技術活用力講座が新しく登場しました。
教科実践編は中学で身に付けることが望まれる情報活用能力を扱った講座ですが,小学校高学年~中学3年生までを対象に,カリキュラムが3ヶ月(全3回)で終了できるところが嬉しいです。
比較的短時間で,技術家庭の評定が上がることが期待できます。
将来重要になるにもかかわらず,現状,スポットライトが当たっていない科目なだけに,しっかり対策しておくと後々大きな差となって現れてくるでしょう。
内容としては,Z会オリジナルのテキストと,VIRTUAL KOOVというアプリでの学習となります↓

先程,KOOVのロボットについては動画で紹介しましたが,こちらは「バーチャル」の名前を冠するように,3D空間でのプログラミングが可能です。
Z会の公式サイトにある動画を観れば,中学の物理で学ぶ摩擦や重力の概念を再現できていることがわかるでしょう。
ゲーム的な感覚で課題を解決しては,創造力ややり抜く力を身につけられます。
ロボットのKOOVを使って学んでいる方にはお馴染みのアプリですが,小学校で扱うであろうScratchと同じビジュアル型のプログラミングになるので,導入は極めてスムーズです。
中学技術活用力講座 コンピュータ活用編

同じく中学技術活用力講座になりますが,こちらはコンピュータ活用編となり,12ヶ月のカリキュラムを伴った実践的な講座となります。
キットとして先述した「Raspberry Pi 400」というキーボード型のコンピュータを用いるため,ソフトウェアの活用能力も身に付けられるのが特徴です。
その際に用いることになるアプリはPROCなので,Sonic Pi・GIMP・Impress・Scratch・Python・HTML・CSS・JavaScript・Calc・Mathematicaのようなソフトウェアを実践することができます。
音や動画の他,プログラミング,ウェブ関連,データ分析など,幅広い内容です。
この他,テキストや総仕上げテストもあり,最終的には中学の技術の内容に限らず,高校の情報Iの基礎レベルまで到達することができます。
Z会プログラミングシリーズの料金

ここでは,Z会プログラミングシリーズの料金についてまとめましょう!
キットが必要なコースだと,通信教育にしてはちょっと高くついてしまいますが,その分,組み立てて遊ぶならではの楽しさが得られることは言うまでもありません。
また,基本的な使い方さえ学んでおけば,Z会の課題がないときであっても自由に遊べてしまう点も大きなメリットです。
受講料は毎月払いができますが,一括で申し込む方が安く済む講座もあります。
みらいwithソニー・グローバルエデュケーション
KOOVのコースは1年目とそれ以降で料金が異なります↓
- 1年目:53856円(月払いは5280円)
- 2年目:67320円(月払いは6600円)
- 3年目:67320円(月払いは6600円)
キット代は初年度のみかかり,通常5万円以上するKOOVアドバンスキットが24970円で購入可能です(ただし2年目の継続受講が前提で,キャンペーン時にはより安く購入可能です)。
初年度の料金を合計すると78826円となります。
何にせよ,一度どちらの資料も取り寄せてみて,ゆっくり判断してみてください。
はじめてみる講座
はじめてみる講座は,タブレットかパソコンが自宅にあることが前提で,Z会を介在することでiPadを安く購入することもできますが,もちろん自宅にあるものを使って始めることができます。
月額で1980円ですが,3ヶ月まとめて最初に5940円払ってしまうことも可能です。
本講座に限りませんが,Z会のプログラミングシリーズはどのタイミングでも開始できるので,小学校入学前のタイミングや長期休暇などを利用して,本格的な授業に備えましょう。
中学技術活用力講座
教科実践編は月額4840円ですが,3ヶ月一括で払うと12342円となり,月額払いよりは少し安くなります。
こちらはキットを別に必要としません。
タブレットかパソコンがあれば,いつからでも学び始められます。
一方のコンピュータ活用編ですが,12ヶ月の講座で一括払いで56100円の受講料がかかる他,必須キットの代金が17600円です。
これらを合わせると73700円となりますが,1ヶ月で考えれば6000円強と,学べる内容からすれば決して高くはありません↓
Z会プログラミングシリーズの口コミ

最後に,Z会プログラミングシリーズを受講した方の口コミについてみていきましょう。
東京都 小1
他のブロック教材と違ってKOOVを与えたときの子どもの反応が良かったです。ロボットの設計図をiPadで回転させながら確認することをよくしていましたが,それによって子どもの空間把握能力が育ちました。
この時期の子どもの学びにおいては楽しく学べることが重要です。また,iPadを使いこなして空間能力を鍛えておくと,算数や数学の図形の問題を解くときにも大変役立ちます。
京都府 小2
教室も検討しましたが,送迎は負担になるので躊躇しました。Z会のプログラミング講座ならば自宅でできるので,節約できた時間で家族が一緒になって学ぶようにしています。
幼稚園児から小学校低学年あたりまでは親子が一緒になって学ぶことが重要と聞きました。
親が普通に行っている学び方(思考体系)も,子どもの目からすればすごい技術に映るはずです。親が今何を考えているのかを1つ1つ声に出しながらただ普通に学ぶだけで,子どもにとっては大きな学びになるのだと思います。
愛知県 小3
親としては,「おぉー!」という声が隣から聞こえてくるたび,きっと新しい発見や驚きがあったのだなぁと嬉しい気持ちでいっぱいです。たとえ思った通りに動かせなくても,失敗から学ぶことが多いのがプログラミングの魅力。1年後にはさまざまな思考力が身についていることを期待します。
大人になると感動の気持ちも薄れてきてしまうものですが,子どもたちには驚きや楽しいといった気持ちを大切にしてほしいものです。
遊びと勉強が別物だと切り離されて考えられる時代ではありません。
新潟県 小3
出来上がった作品を家族に見せるのが楽しみな子どもは,講座の課題を終えた後も試行錯誤して学びを深めていることがあります。本人はプログラミングが遊び(楽しいこと)と同義のように感じているようで,そんな様子を見て親は安心しているの一言です。
Z会のプログラミングシリーズでは,課題に取り組んだ様子を全国にいる会員と共有できる機能があります。以前のLEGO講座があったときの例にはなりますが,以下のような感じになるのだと理解してください↓
まとめ

以上,Z会プログラミングシリーズに含まれる講座ごとの特徴や教材内容,さらには料金や口コミについてまとめてきました。
やや高価になってしまいがちですが,キットを使って学べる講座は特に魅力的であり,小学生の指導要領にあるプログラミング的思考が短期間で完成できてしまうカリキュラムですから,どんな教育をわが子にさせればよいかに悩む親にとっては,大変わかりやすいものだと言えるでしょう。
加えて,Z会は通信講座であるという性質上,キット込みでも月額6000円程度で利用できてしまうところは,どこぞの教室に通学した場合と比べれば,ずっと安く済むものです。
また,説明書を読み解いて創造力を働かせては新しいものを作り出すという行為には,他人に頼らず独力でやらないといけない要素も含まれています。
その際,身に降りかかってくる困難は自分自身で乗り越えるしかなく,それは通信講座であろうと通塾しようと変わりありません。
以下の記事で述べたような資質・能力が,本講座を通して身に付くことは十分に予想できるでしょう↓
なお,特設ページから資料請求することで,各講座のより詳しい内容を知ることはもちろん,小冊子(STEAM教育プログラミング教育など)がもらえることもあります。
申し込みの前に,以下の記事のチェックをお忘れなく↓
最後までお読みいただき,ありがとうございました。