毎年,文部科学省のHPで最新の「学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」を確認することができます。
そして,教育現場におけるICT(情報通信技術:Information and Communication Technology)環境の改善は,最近の教育改革における主要テーマの1つとなっていて,21世紀型の新しい学習スタイルの確立に直接影響を及ぼすものです。
今回はそんなICT環境の現状について,
- 学校内のICT環境の整備状況
- 教員のICT活用指導力
を中心にみていくこととし,今の学校でどのような教育が行われているかについての理解を深めていきたいと思います。
とはいえ,まずはICTを用いた学びについてまとめておくことにしましょう!
ICTを用いた学びについて

ICTは学校において「一斉学習・個別学習・協働学習」といった3つの学びに活用できるとされています。
ゆえに,ICT環境が整えば,これらすべてを行いやすくなるわけですが,それぞれの学習形態はどういった特徴を持っているのでしょう。
一斉学習
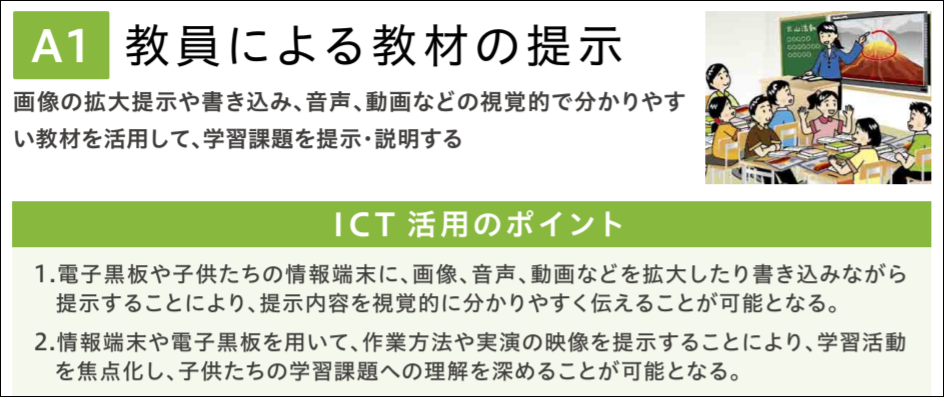
これまでに学校で行われていた集団授業と同じ印象を持つ方が多いと思いますが,ICT環境の整った中での一斉学習では,実際に教師が実演する様子を,電子黒板や子どもの持つ情報端末に映したり,カメラで動きを連写したものを使って説明したりすることも可能です。
私が子どもの頃はスライドで示すか,ビデオを流すなどしていたところですが,令和時代においては,より鮮明かつ素早く行うことができるようになりました。
最近は電子黒板機能付きプロジェクタも登場してきています。
面白いところでは,体育の授業で水泳やバスケットボールなどを行う際,自分の身体の動きを動画で確認し,画面共有されたお手本と見比べて課題を考えだしたり,物を放り投げた後の動きをスロー再生できたりするところでしょう。
こうした授業形態は何も生徒だけのメリットに限らず,教師側からしても,生徒全員の動作を確認できますし(授業中に全員の動作を確認する余裕がないため),「圧倒的なデータ量を基に質の高い情報が得られる」という点でもICTの強みが生かされることになります。
最近では,SPLYZA Motionのようなアプリを用いて探求学習を行う小学校も存在しているほどです↓
こうしたデータをロイロノートなどを使って仲間と共有して意見を出し合えば,それは高度な一斉学習をしていることになります。
以前,とあるTV番組で,前方に進む車から後方にボールを投げたとき,球速と車の速度が同じだと空中にボールが止まったように見える実験していたのですが,こうした面白い実験をICTを駆使して子どもたちに提供できれば,彼らも俄然,積極的に参加してくれるでしょう。
もっとも,これまで白黒でしか示せなかったものをカラーで提示できたり,大きく拡大して示したり,音声や動画を提示できたりするだけでも教育的には有効なのですが,表示までのスピード感や解像度といった情報量が多ければ多いほど良いのは言うまでもありません。
個別学習
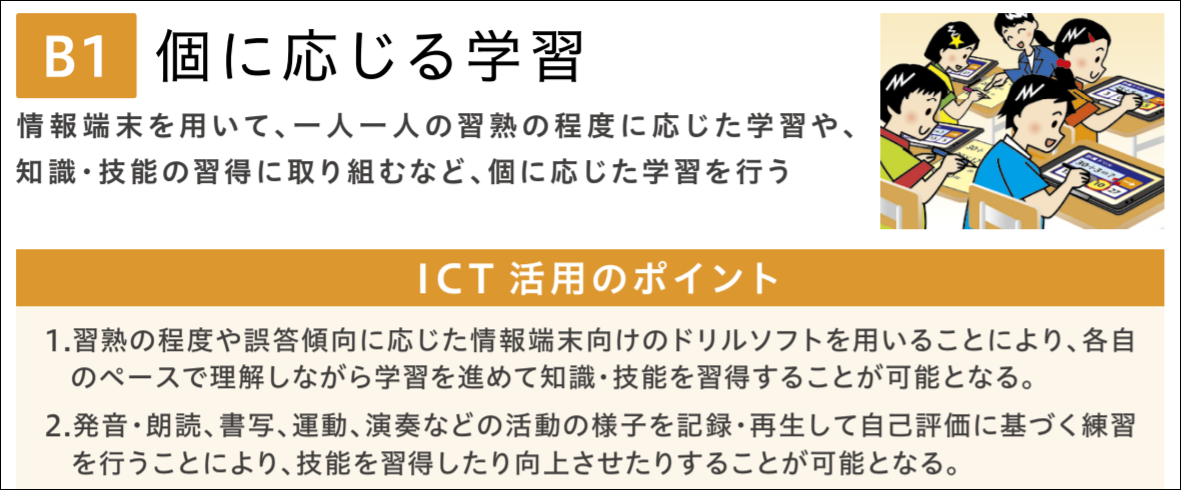
ICTは個別学習において特に有効です。
1人1人の習熟度や誤答の傾向といったデータを蓄積し,搭載したAIまたは教員がそれを上手に分析することで,各自に応じた課題を提示しやすくなりますし,学習ペースは本人に合わせたものにすることができます。
これは,いわゆる「個別最適化学習」と呼ばれるものですが,そのときに使うAIドリルが最近は一般家庭にも提供してもらえる時代になりました。
当然,教員側からしても,ドリル型の教科学習用コンテンツは重宝していて,進度が速い生徒は発展学習ができますし,遅れを取り戻すことも容易です。
昔は一部の塾や学校のみがその権利を買っていて,資金力の差が教育格差を引き起こすことにも繋がっていたわけですが,今や安価に利用できるものも増え,上手く活用できているかはともかく,可能性を秘めた教材は見渡せば潤沢にあります。
この他,PCを用いて発音を録音するか,書いたものを入力して残すことで,あとから教員が個別に生徒を評価することが容易になるため,集めたデータを有効活用することも可能になるわけです。
なお,このアプローチは,英語の資格試験においてスピーキングやライティングを採点する際にも用いられており,デジタルデバイスの扱いに慣れておくことがCBTの得点力の上昇にも繋がります。
これは,PISAやTIMSSのような国際的な学力調査において,日本人の弱点と考えられたこともあるため,その対策も兼ねられる一石二鳥なアプローチになるでしょう。
英語繋がりだと,オンライン英会話を始めとする新しい学習スタイル(遠隔教育など)が,学校現場においても積極的に取り入れられていくことが今後予想されますが,最近はネイティブ講師を画面の向こうに置き,英検の面接対策を行う学校がニュースで取り上げられていました。
協働学習

私と同年代であれば,インターネットを使った調べものやプレゼンテーションの練習は,大学に入ってから初めて行ったという方も多いでしょう。
が,これからの時代は高大接続ということで,より早期のタイミングから行われることになりました。
グループに分かれて役割を分担し,情報端末を用いて同時並行で編集していくような,いわゆる「シェアワーキング」も協働学習に含まれます。
最近では,ドラマで流れるような曲を作る際にもこのような形式が取られていることを耳にしました。
担当する音楽チームのメンバーが別の国に滞在していることも珍しくなく,働く場所や時間を選ばないことは,新しい働き方のスタンダードになりつつあります。
ところで,グループで協働作業することで,1人では得られないアイディアが浮かぶことも,多くの方が経験してきたことでしょう。
これまでに書いた記事の中では,アクティブラーニング(主体的・対話的で深い学び)や生成AIを使った学びにおいても同様の効果について述べています。
学校におけるICT環境の現状

ここからはいよいよ学校におけるICT環境の整備状況を詳しくみていくことにしますが,評価基準としては,コンピュータや電子黒板,無線LANといった電子機器の整備率に注目します。
加えて,クラウドと接続するための高速大容量の通信ネットワークの実現や個人アカウントの割り当ても同じくらい重要です。
コンピュータ整備率
前章で挙げたようなICT学習を行うためには,学習デバイスとしてのコンピュータが必要になります。

ここでいうコンピュータとは,専用教室にあるデスクトップ型のものに限らず,ノート型やタブレット型のものも含み,低スペックなものでも授業に使う分にはそうそう困らないため,家庭用のものほど高価にはなりませんが,生徒全員分となればさすがに高額になってしまうわけです。
なお,理想を言えばキーボード操作にも慣れておきたいところです(社会人は文書作成を求められますし,CBTや大学の課題もキーボードで入力します)し,家に持ち帰って使えることもあってChromebookが人気のように感じます。
ノートブックなので持ち運びができますし,Apple IDは個人情報の管理が難しいという観点から敬遠されがちです。
それでは,現在の公立では,生徒1人当たりにどのくらいの台数のコンピュータが用意できているのでしょう。
令和2年のデータでは「1台のコンピュータを約5人で使う」でしたが,令和5年には「1台のコンピュータを0.9人で使う(1人1台端末)」が実現できました↓

実際,上の数字は学年がごちゃ混ぜになっている数字なのですが,小中高のすべてにおいて1人1台端末は実現できています。
もちろん,端末が揃ってもソフトや教員の指導力が揃わなければ宝の持ち腐れとなってしまいますし,維持や更新に備える必要もあるわけで,まだまだ油断はできません。
とはいえ,次章で述べているように,教員のICT指導力も上がってきています。
各生徒が独自アカウントを持っていなければ,データを収集しても意味を成しませんし,現在は次の段階の課題を解決している状態となります。
長期休暇の際に許可がいる学校や,フィルタリングや使用時間に制限を設けるかどうかといった議論はまだまだ始まったばかりです。
とはいえ,デジタル教材の導入(そして次に紹介する大型提示装置の導入)で,より良い授業が行えるようになった教員は多く,生徒も授業が楽しく,わかりやすく,そしてマイペースかつ友達と協働してできるようになったと聞きます。
大型提示装置と無線LANの整備率

電子黒板は,教員が教材を生徒に提示するために使われ,普通の黒板と異なり,写真を拡大して見せたり,音声や動画も再生できたりするのが強みでしょう。
つい最近も,iPadを購入した人のレビューの中に,実際の授業に(電子黒板などの投影用などで)使う予定がある教員を見つけましたが,カラフルで刺激的な画像は,子どもの興味や関心を高めるのに役立ちます。
文科省は平成30年までは電子黒板の整備率を調査していましたが,それ以降,プロジェクタやデジタルテレビも含めた「大型提示装置」の整備率を調査するようになりました。
そのため,データはこれまでのものと繋いで評価することはできないということで波線が入っていますが,以下のデータだと9割弱に整備されたということで,これは3年前の1.5倍近くです↓

1人1台のコンピュータ環境と大型提示装置はセットみたいなところがありますので,こちらもいずれは100%に近づくでしょう。
なお,普通教室における無線LANの整備率は教室はもちろん校内でも100%近くになっていて,さらに,そのスピードにも気を配っているようです(100Mbps以上でネットに接続できる学校が99.6%)。
以上のことから,学校におけるICT環境については問題ないと考えて構いません。
その他で気にすることとしては,学校からクラウドに接続するときの環境でしょうか。
ネットワーク整備の課題としては予算の確保が難しいところが指摘されていて,回線容量が増えるにつれて料金の負担が高くなるものです。
その他,カラープリンタやデジタル教科書の配備も考慮すべき項目で,引き続き見守っていきましょう。
ICT環境における教員の質

最後に,教員のICT指導能力についてみていきたいと思います。
教える側が「コンピュータが苦手」などと冗談でも言えなさそうな時代が到来したかと思いきや,実際はICT支援員が配備され,技術的な質問に答えることはもちろん,教員の研修も行ってくれており,「教師が生徒と一緒にICTに慣れていく」方針で授業は進んでいるようです。
もっとも,教員の習熟度が高まるに越したことはなく,文部科学省の本調査においては,教員のICT活用の指導力を,
- 教材研究・指導の準備や評価・校務にICTを活用する能力
- 授業にICTを活用して指導する能力
- 児童生徒のICT活用を指導する能力
- 情報活用能力を指導する能力
の4つの点を中心に調べています。
Aは,教育効果を高めるための計画ができるか,ネットやCD-ROMでの情報収集に加え,プレゼン能力やデジタル独自の評価ができるかが問われるものです。
ネットや校内ネットワークを活用し,必要な情報の交換や共有化を図る能力もこちらに含められています。
学校に通わせる親の側からすれば,どのような様子で自分の子どもが学校生活を送っているのかが気になりますし,教員間での情報共有も欠かせません(引継ぎやベテランからの技術伝達に用いることも可能です)。
Bでは,資料を効果的に提示でき,生徒の興味・モチベーション・理解を助ける工夫ができるかを自己評価します。
CとDについては後で考えることにして,まずは結果を見てみましょう↓

上記は令和5年3月の結果ですが,令和2年のときと結果を比べてみると,Aは86.7%→88.5%,Bは69.8%→78.1%,Cは71.3%→79.6%,Dは81.8%→86.9%とすべて増加しています。
Dは昨今ニュースで騒がれていることもあり,相変わらず徹底されているようです。
色々な権利(肖像権や著作権など)や常識に加え,犯罪に巻き込まれない立ち振る舞いや個人情報とセキュリティーについても深く学ばなければいけませんが,最近はそういったものの目をかいくぐるような事案が次から次へと出てきています。
悪いことをしている側(大体は大人)を教育すべきなのは当然で,子どもに罪はないのですが,自己防衛は必要です。
なお,Cの調査質問としては,以下のようなものがありました↓

この質問は教員を対象に行われたものですが,逆に生徒側の目線になってみれば,
- コンピュータの基本操作を覚える
- ネット上の情報を取捨選択できる(ネットリテラシー)
- ワードやエクセル,パワーポイントを上手く使える
- 意見交換や話し合いにコンピュータやソフトウェアを活用できる
といった能力が,今後の時代において求められることがわかります。
前章と本章の内容に関しては,GIGAスクール構想の記事も参考にしてください。
まとめ

以上,教育現場におけるICT環境の現状と今後の課題を中心にまとめてきました。
2020年度はコロナの時代となり,ICTの整備が急速に必要となりましたが,その結果,2022年度には大きな改善が見られました。
最近のデータをみてもすでに1人1台端末や無線LANの整備は理想に近いものが実現され,もちろん大型提示装置は100%を目指したいところですが,現在は次の段階に目を向ける状況となっています。
つまり,ICT環境が実現されたことを前提に,どの有償コンテンツを採用すべきかや,デジタル端末の保管をどうするかといった問題は存在し,指導教員用の端末が1人1台でなかったり,ICT支援員の助けを必要と感じる教員もまだまだ多いようです(支援員の配備は4校に1人が目標です)。
生徒は,学校の授業時間よりも自宅で過ごす時間の方が長いわけですから,多忙な日常の合間を縫っては,自らICTを上手に扱えるように学んでいかなければなりません。
スマホゲームやSNSなどの悪い面ばかりが強調され,ICTの効果を信じられない人もいまだ見受けられる時代ですが,ICTで育った子どもたちが納得のいく結果を出すことで,周りの目は変わってくるでしょう。
最近は将棋の藤井聡太さんの活躍で,AIを用いて将棋を学ぶ価値が見直されたように思います。
意外なところにもICTの大きな可能性は眠っているため,最近のデジタル化政策にいまいち賛成できない方も,禁止事項を増やして遠ざけるのではなく,上手な使い方を身に付けさせるようにしましょう。
教員任せではなく,保護者も生徒本人に協力していくことが大切です。
なお,今回紹介した調査結果は過去のものも含めて文科省のHPから確認できます。
最後までお読みいただき,ありがとうございました。