前回の社会の勉強法とノート術に引き続き,今回は「理科の成績UPのための攻略法」について考えてみましょう!
「攻略法」などと書くと何やら難しそうに思えるかもしれませんが,実のところ20年前と今とで理科の指導内容には大きな変化はなく,塾でのノウハウはすでに確立しています。
なので,ここにまとめている勉強法とノートの取り方にだけ注意してもらえれば,すぐに点数が取れるはずです(英語と数学の方がずっと大変です)。
具体的な手順についてこれからまとめていきますが,是非とも気楽に読んでいただいて,何か1つでも役に立ちそうなヒントを得て帰っていただけたらと思います。
なお,大学入試の理科については,本記事に記載した内容の他,計画の立て方に対する知識も学ぶようにしてください(最近出た本の中ではプランブロック式戦略的学習計画法という参考書がおすすめです)。
理科を学ぶにあたって
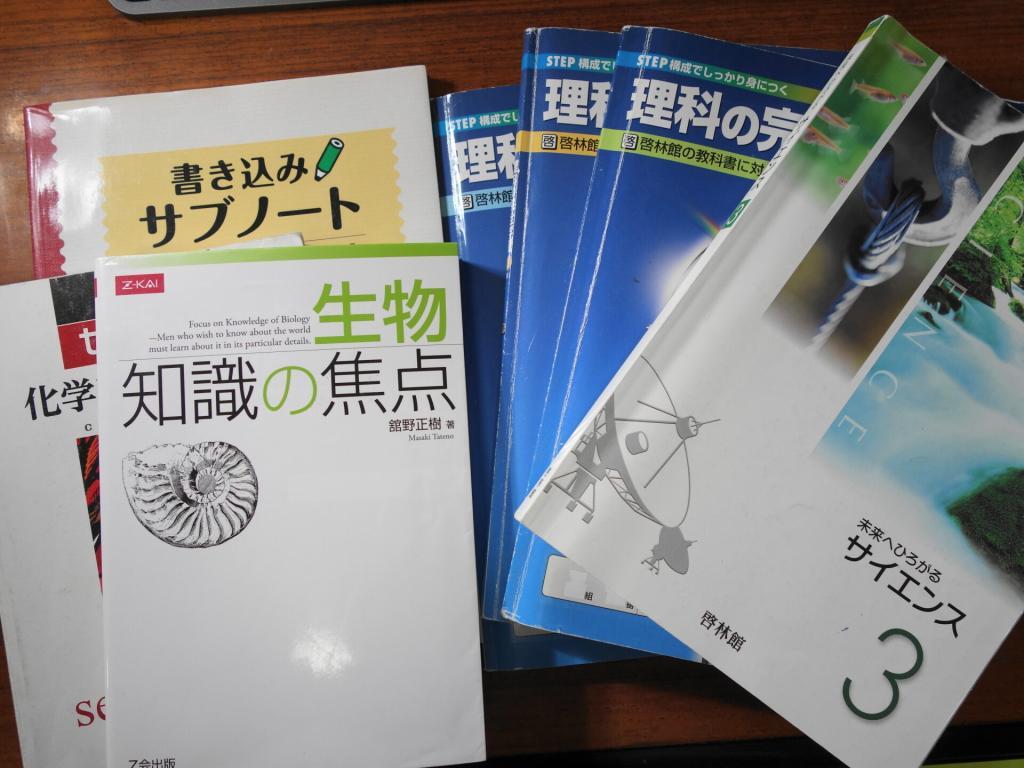
文系科目の方が得意だったり,理科に苦手意識があったりする生徒は特に誤解しがちなのですが,例えば中学校で学ぶ理科は最も簡単な教科の1つと言っても過言ではありません。
その最大の理由は「積み重ねがいらないから」であり,知識が全くない状態から始めて,次のテストでいきなり高得点を取ることも十分に起こり得ます。
高校に入ると物理や化学を中心に数学的な要素が登場し始める関係でやや難度は高まりますが,それでも他教科より取り組みやすいことは確かです。
いずれにせよ,勉強が苦手な生徒,つまりこれまでの勉強人生において顕著に良い点数が取れた経験が少ない生徒ほど,理科を逆転のきっかけにしてほしいと思っています。
とはいえ,勉強のやり方に関して注意すべきポイントはいくつか存在する他,学習効果を高めるためのノート術もいくつか知られているので,ただ闇雲に努力することだけは避けたいものです。
勉強が苦手な子が本当に頑張ったとき,非情にもその努力に見合うだけの結果が出なければ,もう2度と頑張ろうとは思わないのが人間というものでしょう。
逆に,上手くいった場合には,その成功体験が理科に限らず,多くの教科を頑張るモチベーションに代わり,中学校や高校の学生生活に良い影響を与えることになります。
1つの成功が自分の将来を決定づけることになるかもしれません。
主要3教科である英国数と比べると,どうしても配点面などで重要視されない理科ではありますが,だからといって決して軽視することなく,やると決めたら大きな覚悟を持って全力で取り組むようにしてください。

それでは次章で,理科の勉強法をみていきましょう!
理科の勉強法

勉強ができないと思っている生徒ほど,理科をとにかく頑張って自信を付けるようにしてください。
繰り返しますが,理科は英語や数学といった主要科目と異なり,勉強の積み重ねがそこまで必要ではありません。
それゆえ,これまでの勉強の遅れを取り戻すために大きく前に戻って学習ような複雑な学び方については考えず,今学んでいる範囲に対して,シンプルで王道を行く勉強法を採用することが最適解となります。
具体的な手順としては「理解する→問題を解く→復習する」という流れに気を付けて頑張るようにしましょう!
学習内容を理解する
模試でも学校の定期テスト対策でも,試験範囲が判明したら,まずは教科書を読んで内容を理解するようにしてください。
理科には表や図が多く登場してくるものですが,このとき,いきなり学校のノートを見返したり,箇条書きになったワークのまとめを読んだりするようでは失敗します。
社会の勉強法のところでも語ったように,テストは文章の形で出題されるため,ある程度の長さがある文を読んで勉強することが何よりも重要です。
とはいえ,勉強全般に苦手意識があったり未習範囲の内容を初めてやったりする場合において,教科書が難しいと感じるときもあるでしょう。
そんなときは,教科書の内容をサポートする目的で書かれた参考書を買ってくるか,動画による講義形式のオンライン教育サービスを前に挟むようにしてください。
意外かもしれませんが,参考書は分厚くなればなるほどわかりやすく感じるものなのでページ数があるものを選ぶのがおすすめで,活字に慣れていない生徒は動画形式で学べるスタディサプリのようなサービスが役立つように思います↓
これらは本来,学校の授業が担当すべき領域ではありますが,様々な理由で授業を受けられなかった生徒がいることは把握済みです。
真面目に授業を受けていても,時間が経ちすぎていて何を学んだか覚えていない人も少なくないでしょうし,理解した内容であっても,違った先生が説明することで何か別の発見があるかもしれません。
なお,高校の理科ともなると科目間の性質の差がやや顕著になることもあって,勉強法を多少変える必要性が生じてきます。
暗記物の生物であれば社会のときとほぼ同様の勉強法が採用できるものの,物理のような数学的なものや化学の理論部分を学ぶ際は,数学の勉強ノートの書き方の記事内容が参考になるかと思います。
とはいえ,理科に限っては数学知識の積み重ねは不要です。
その回ごとに新しい気持ちで学習できることがほとんどなので,安心して頑張ってください。
制限時間付きで問題を解く
教科書を読んだら次にノートを読んで,「はい,勉強終わり!」としてしまっていませんか。
中学生で特に多いのは,ノートを読んで,書き込まれたワークを眺めたら終わりにしてしまうことで,それは誤った勉強法になります。
頭では理解している内容であっても,問題をいざ自分1人の力で解こうと思ったら案外できないものなのです。
わかった内容をできる状態に変えることで,初めてテストで良い点数が取れるようになります。
加えて,テストでは時間制限があることも忘れてはいけません。
問題を解くときは素早く答えを出すことを意識しましょう。
1回目に問題を解く際には何分かかったかを書いておくと最高です。
2回目に解くときはその時間の半分を目標に解いてみてください。
時間をかけたらできる問題も,制限時間内に解けなければ解けていないのと同じなのです。
なお,記事の冒頭で「理科は簡単だ」などと言い切ってしまいましたが,1回目に問題集をやってみるとほぼ解けないことと思います。
ここで「どうせ自分なんて」などとふてくされることなく,問題集の答えをすぐに見てはそれを暗記してしまう勉強法を採用してください。
私が塾で教えるときによく行っていることですが,問題を解くのに大きな抵抗がある生徒相手に指導する際,解答をいきなり読ませることから始めています。
勉強ができるできないにかかわらず,中高生の暗記力には凄まじいものがありますし,実は理科のテストでは問題集と似た問題しか出ないので,若さを生かして問題と解き方のパターンをすべて暗記させてしまえば高得点が取れるのです。
もちろん,最近の傾向としては文脈を理解しないと解けない問題も出てきますが,ひとまず丸暗記してから理論部分を補うことも十分に考えられます。
入試まで時間がない人は,問題を解いては暗記する方法で学んでみてください。
何度も復習する
どんなにできない生徒であっても,問題集をテスト前に5回解き直してうまくいかなかった例はありません。
他教科との兼ね合いもあるので,塾では最低3回解き直すように指導していますが,「頑張って逆転してやる」という強い気持ちがあれば5回をお勧めします。
ところで,最初に使う際に以下のように書き込みをしてしまえば,ワークや問題集を1度しかやることができません↓

答えをただ眺めているだけではできるようにならないのは先述した通りですが,中には丸付けをしない生徒もいますし,答えの漢字を間違って書き写しているようなケースもあります。
最終的には書き込んで学校の先生に提出する必要があるにしても,初回にコピーを取っておくか,そのときまでに何回かノートにやっておくことを忘れないようにしましょう。
なお,「自分の学校では難しい問題が出題されるから高得点が取れません」と言う方は,その問題のレベルに合った問題集を買ってきてください。
これまで理科の勉強をさぼっていたというのであればワークと教科書をやるだけでも大きな進歩と言えますが,これまでワークと教科書をやったのにもかかわらずうまくいかなかったのであれば,解いてきた問題のレベルが試験のレベルに見合ったものではなかったのではと推測できます。
復習のタイミングですが,解いた翌日であれば記憶がまだ新しく正解できてしまうと思うので,間隔を1週間や1ヶ月後などと広めにとることがポイントです。
詳しいやり方については,令和時代におすすめしたい勉強法とノート術も参考にしてください。
問題を何度も復習することにより,教科書のどの部分がどういった形で質問されるのかがわかってきます。
極めつけは,問題を解いてから教科書を読むことで,最初に読んだときよりもさらに内容がよくわかることも少なくありません。
時間がある方は,仕上げにまとめノートを作ってしまうのも有効です。
これは模試や入試のときに大活躍します。
次章では,そうしたノートの作り方について解説していきましょう!
理科のノート術
あまりみなさんが通っている学校の先生の悪口を言いたくないのですが,塾に通っている生徒で,不当な理科の成績評価をされてしまっている子は結構います。
特にノートやワーク提出が義務付けられた中学生の場合,筆跡の良し悪しだけで理不尽に内申点が下げられてしまっていることすらあるわけですが,今さら習字教室に通えとでも言うのでしょうか。
ここでは,そういった憂き目に遭わないための防衛策を2つ紹介します。
もちろん,これらのノート術は学校に提出するしないに関わらず,純粋に理解の助けとなるものです。
色ペンで書き込みをする
良いノートを作るためにも,後からわかったことをどんどん書き込むようにしてください。
学校でノートを取る際には余白を多く取るようにし,教師のセリフも沢山書き残しておきましょう。
こうすることの意図についてですが,その日の授業の様子を思い出すきっかけになるだけでなく,教師側からすると,自分のセリフをわざわざ書き残してくれた生徒をぞんざいに扱うわけにはいかなくなるからです。
さらに,前章で述べた復習段階において,ノートに書かれたキーワードをつなぐようなセリフを書き込んでいきます。
こうすることで,文章として読めるノートに変えていくわけですね。
パッと開いたときに,勉強を頑張っている感がにじみ出てくるノートを作りましょう。
具体的にどうやるかですが,まずは板書した内容に,色ペンを使って書き込みを加えるところから始めます。
例えば,このようなノートがあったとしましょう↓

何の変哲もない理科のノートですが,ここに以下のルールで書き込みを加えていきたいと思います↓
- 青で補足的な説明を自分の言葉で加える
- 緑で疑問に思ったことや問いかけを書く
色に関しては特に決まりはなく,授業中に使っていない赤以外の色を選んでみました。
その結果,このようなノートができあがります↓

これだけでも,ノートを見た時の印象がだいぶ変わったのではないでしょうか。
板書以外の内容をわざわざ目立つように色付きで書き込んでいるところに意味があり,それによって,授業に対する積極性の部分での評価が高くなります。
「明らかにこれまでとはやる気が違うぞ!」というアピールを,下品でも構わないのでどんどん行っていきましょう!
ちなみに,書くことがないという人は生成AIに尋ねてみてください。
炭酸同化については以下のような答えが返ってきました↓

区切りを入れる
そもそも,ノートなんてものは自分だけがその内容をわかれば良いわけで,部屋のレイアウトにも似た要素があります。
他人からは汚く見える部屋であったとしても,当の本人はどこに何が置いてあるか把握している部屋であって使い勝手が良いという事実は,誰もが理解しているでしょう。
ですが,字が汚いノートは残念ながら教員から総じて低い評価を受けてしまうことが多く,その際,見た目の印象の悪さが影響していることは明らかです。
授業中に字をきれいに書くようにすると時間がかかってしまい,先生の話が聞けません。
先生のセリフを書き残そうとすればなおさらです。
そこで,文字自体ではなくノートをきれいに見せる技をお教えしましょう!
簡単に実践できるノート術としては「区切りを入れる」ことがおすすめです。
以下の写真は,先ほど書き込みをしたノートの一部を,ただ蛍光マーカーで囲ってみただけですが,見栄え的にはどうでしょうか↓

だいぶ見やすくなったように思います。
囲むだけの作業であれば短時間で済むので,まずは大きな図表を囲むところから,是非実践してみてください。
図表を加える
最後にダメ押しで,図や表を貼り付けていきましょう!
資料集でも教科書でも,ネットで調べた内容でも構いません。
わかりやすいまとめページが見つかったら,それをコピーしてください↓

今や家でも簡単にカラーコピーができてしまう時代になりました。
拡大や縮小も自由にできますし,ICTが活況の時代において頻繁に利用すべき技術の1つです。
それをノートに切って貼っていきますが,後になってどのページだったのかわからなくならぬよう,引用先の情報も書いておきましょう。
こういったまとめの作業は,授業がある程度進んだ時にまとめて行うでも構いません。
最後に,忘れてはならない注意事項として,ノートを作ることよりも問題を解くことに時間を使うようにしてください。
ノート作りにハマってしまうと,それだけで大層勉強した気持ちになってしまいますが,それだけでは点数に結びつきません。

まとめ

以上,理科の成績アップにつながる勉強法とノート術について,簡単に実践できるものをいくつか紹介してみました。
今回の記事の要点を書き出してみると,
- 教科書の理解から始める
- 制限時間付きで問題を解く
- ワークには書き込まない
- 復習は3回以上行う
- ノートは復習時に書き込みを加える
- 区切りを加えて見映えにこだわる
- コピーを貼ってまとめる
となります。
もちろん上で示したのはあくまで一例にすぎませんので,当記事をきっかけに自分なりの工夫を加えてみてください。
理科で実際に良い点が取れると自信がついて,他の科目でも良い点を取りたくなるもので,そういった欲が出てきた生徒は,概して受験で成功するものです。
たかが理科,たかがノートですが,それは自分の人生すら大きく左右しかねないことをゆめゆめ忘れないでください。
最後までお読みいただきありがとうございました。