当記事は2021年(令和3年)度に開始となった「大学入学共通テストの解き方」についてまとめたものです。
難易度や問題形式が大きく変わることも稀でなく,あくまで過去のデータをもとに語ることしかできませんが,それでも解き方について学ぶ前と後とではテストの印象がだいぶ変わってくるように思います。
なお,共通テストに臨む者の心構えとしては普段から自分の実力を高めておくことが肝心で,その力が正しく発揮されるために解き方を学ぶということを忘れないでいてください。
共通テストの過去問は試験直後であれば各新聞社のHPなどで入手でき,しばらくすると大学入試センターの方にも掲載されます↓
はじめに
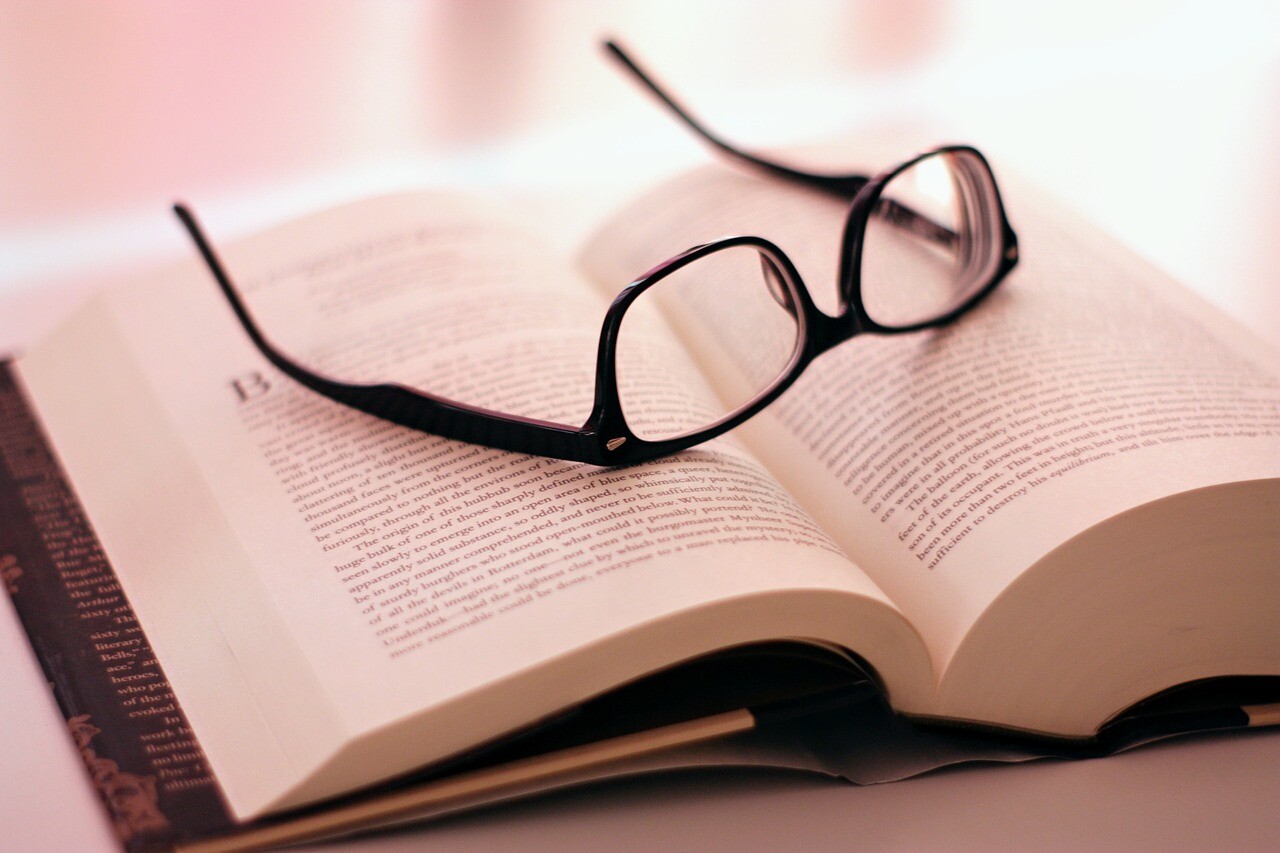
共通テストの解き方を学ぶにあたって,最初に知っておきたいことがいくつかあります。
まず1つ目は自分の実力の限界です。
これについて知りたければ,時間を測らずに問題を解いてみてください。
とはいえ,現状利用できる過去問の数に限りがあるため,通常通り時間を測ってやってみた後にすぐ採点をせず,残った問題を解き直したり再度見直したりする時間を設けるようにするのがおすすめです。
変更した答えについては,青いペンで書くなどして区別しておきます。
ここで初めて丸付けをしますが,時間無制限で解いたときの点数(青ペンの答えを含めたもの)が自分の実力の限界であり,制限時間を課したときの結果(鉛筆で書いたもの)をこれにできるだけ近づけるために解き方を学ぶというのが基本方針です。
そのためもしMAXとなった点数が自分の望むものでなければまったく別の勉強,つまりは知識の拡充であったり思考力を養成したりなど,実力を底上げするための勉強が必要だという結論になり,これは解き方を学ぶ段階にはまだ至っていないことをも意味します。
基本的に共通テストの問題は実力通りの結果が出るように作られているので,どうあがいても6割しか取れない受験生が8割を取る解き方を知りたいと願っても,そんな都合が良い方法があるはずもないのです。
2番目に知っておきたいこととして,他人にとってのベストな方法が必ずしも自分に合うとは限らないということがあります。

ゆえに,自分に役立ちそうな解き方を試しては,うまくいったものやできそうなもののみを採用していく姿勢でいるのが一番でしょう。
とはいえ,本番が近づくにつれて実力が高まっていくのが自然ですので,それに併せて解き方もより高度なものに変化させていく必要があることも忘れないでいてください。
今の段階では真似できないけれど,未来の自分なら実践可能な解き方も存在するわけです。
次章からはいよいよ教科ごとの解き方をみていきますが,共通テストの基本情報やプレテストについて確認したいような方は以下の記事をお読みください↓
英語の解き方
共通テストの英語はリーディングとリスニングがどちらも100点満点で,1日目の15時10分~16時30分に前者が,そして17時10分~18時10分に後者が行われます。
平均点の推移は以下の通りです↓
2021~2023年
リーディング:58.80→61.80→53.81点
リスニング:56.16→59.45→62.35点

リーディング

文法やアクセントなどを問う問題は一切なく,第1問から第6問までのすべてが文章題です。
私は初めて見たタイプの問題に関しては質問の先読みなどをせず,最初から最後まで普通に読んでから問題を解くことをルール化していますが,正答率を落としてでも先に進まないと時間がギリギリになってしまうこともよく理解しています。
時間切れになってしまっても85%くらいは取れますが,全部の問題に目を通した方が高得点であることの方が多いです。
とはいえ,ここは各自のポリシーに従っていきましょう(判断はすべて自分の手に委ねられています)。
まったく内容がちんぷんかんぷんのままではさすがに読み直さないと得点にならないでしょうが,見直したい気持ちは極力抑えるようにし,立ち止まって時間を浪費してしまうことだけは避けてください。
それくらい読む分量が多いわけで,答えに迷った時はとりあえずどこかにマークしておくとともに,シートの問題番号にチェックを入れておき,最後までやってから戻ってくることをおすすめします(そのような時間がない場合もあります)。
第1問のAはメッセージのやり取りや表の読み取り問題で,試験の雰囲気に慣れられるようにと難しさは控えめです。
技的には質問を先読みし,対応する場所を探す方が早く終わるでしょう。
Bはウェブサイトに書いてある内容を理解するもので,丁寧に1つ1つ検証していくよりも,パッと眺めて「これっぽいな」と判断したものの詳細(数字など)を確認してみるのが早いです。
とはいえ,一体どんな内容のことが書かれているのかといった大まかな内容把握は真っ先にしておくべきだと思います。
第2問は表や記事(広告含む)にコメントの読み取りが主ですが,こちらも全体把握をざっとしてから質問を読む方法が有効です。
よく見ると,内容が言い換えられたものが正解になっていることもあるため,確認作業なしにこれと簡単に決められる選択肢ではないことに注意してください(少なくとも2択で迷うはずです)。
第3問は旅行や学校生活に関連する口コミや記事,ブログなどの内容を理解する能力が問われます。
AとBの問題に分かれている問題では「こんなに読んだのにこれしか解く問題がないのか」と憤ることもあるでしょうが,むしろ問題にできそうな情報がそれくらいしかないのです。
計算が必要な問題や出来事を起きた順に並び替える問題があり,特に後者は,英文を読みながら一緒に解いていくようにしないと時間がかかってしまうので注意してください。
さて,第4問からは気持ちを切り替えなければなりません。
というのも,ここからはずっと長文が続くからです。
さらにここまでの問題と異なり,より内容を深く理解していく必要があります。
さもなければ,推理を必要とするタイプの問題は解けないでしょう。
私は先に文章を読んでから考えることにしています。
ただし,文章だけでは意味がよくわからなくても,後に載っている図表を見れば「なんだ,こういうことだったのか」とすんなりわかることもあるので,語注ではないですが,先にどんな図表があるのか目を通しておくのが良いでしょう。
第5問は何らかの記事と発表用の準備(スライドやメモ)がセットになった問題です。
基本的に問われる内容はこれまでと同じで,内容理解や要約の他,出来事の順番を整理する出題でしたが,major figure(主役)とminor figure(下っ端)のような見慣れない単語の意味を推測するような問題も見受けられました(2021年)。
第6問はAとBの2つに分かれ,より専門性の高い記事や教科書を読み,内容を要約したり理解度が問われたりする問題です。
解き方としては,最初に文章をざっと読み,質問に答える際に詳細を後から検証する形を推奨しますが,文章が長くて探す場所を見失ってしまえば時間のロスに繋がってしまうこともあり,読みながらどんな内容が書いてあったかを段落の横に適宜書き出しておくことをおすすめします。
基本的には時間をかければ解ける問題ばかりなので,第6問に取りかかる地点でどれだけ時間が残っているのかが正答率に影響することを忘れてはいけません。
過去問の結果を分析する際には「読解力が不足していたのか,それとも単に時間が足りなかったのか」に注意してください。
実際,第6問が苦手だという生徒の話をよく聞いてみると,第5問までに時間を使い過ぎてしまっていることが原因になっていることも少なくありませんでした。
なお,見慣れない単語(専門用語や造語)についてはちゃんと言い換えられています。
大問ごとの配点や解答時間の目安は以下の通りです↓
リーディングの得点と時間の目安
第1問:10/10点,9分
第2問:18/20点,13分
第3問:12/15点,13分
第4問:14/16点,13分
第5問:12/15点,13分
第6問:24/24点,19分
時間は1分程度前後して構いませんが,第4~第6問では各問題内にミスはあっても1問までに留め,全問正解の大問もいくつか見られる状態に近づけてください。
上のように解くことで,80分で90点が取れることになります。
ところで,全ての選択肢を検証し終えても判断に迷う問題は確かに存在し,それにいくら時間をかけても間違えてしまう可能性が高いです(例えば2021年の8番)。
ならば,先述の通り,後回しにしてしまった方がよっぽど賢明であるように思われます。
一般的には,並び替えの問題(何問かセットになっていて,全問正解して初めて得点になる問題)や推測問題(国語が得意でないとたとえ和訳を読んでも正解できない問題)は人によっては捨て問にしてしまう選択もありでしょう(それでも8割は取れます)。
読まされる文章は事前知識がないものがほとんどでしょうが,なかなか為になる英文が多いように思うので,楽しみながら読めるのが理想です(これは一般選抜試験でも同じです)。
他に気づいたこととして,センター試験の名残のような問題があった他,新しい資質・能力を問う問題,realiseのようなイギリス英語も見られました。
リスニング

共通テストの英語では,リーディングと同じ配点に格上げされた「リスニング」の重要度が特に増しています。
リスニングは文法知識や速読力も測れてしまう特徴を持ち,例えば聞き取りづらい音は自分の文法知識を総動員して推測しますし,聞こえた順に頭から理解していく(できれば日本語にせず,状況を頭に浮かべる)ことは速読する時と同じです。
ゆえに,リーディングができる人は正しい英語の音さえ聴き分けられれば問題なく解けることになるため,過度に心配する必要はありません。
加えて,リスニングはリーディングよりも短期間で完成できる点が魅力でもあります。
とはいえ,付け焼刃的な対策ではできるようにならないため,毎日数分でもリスニングを行う習慣は早期の段階から身に付けておくべきでしょう。
通学時間であったり,寝る前の5分だったりは単語とリスニング勉強にあてるようにしてください。
リスニングテストは一方的に音声が流れて終了となるので,制限時間を気にする必要はありません。
とはいえ,試験中にどのような行動を取るかで多少得点が変わってきます。
経験的に一番多い失敗は,間違いが連鎖してしまうことでしょう。
過去問を解いていて連続で間違えてしまった箇所があれば,それはよく聞き取れなかった問題の影響を後の問題にまで引きずってしまったことが原因である場合がほとんどです。
音声がいったん流れ切ってしまえば,それ以上その問題に時間をかけたところで正解率がアップすることはありえません。
その場合は適当にマークして,次の問題に集中しましょう。
基本的にはプレテストのときと同様,後ろの問題になるほどどんどん難しくなっていくパターンです。
読まれる回数には違いがあり,第1問と第2問では2回ずつ読まれるので多少余裕があります。
とはいえ,あまりに余裕ぶっていると1度目にまったく聴き取れずに焦ってしまいますし,心の準備をするという意味でも,あらかじめ質問に軽く目を通しておきどのような話題がポイントになるかくらいは予想しながら待ち構えておきたいところです。
第1問のAは1人の話者がしゃべり,その内容を最もよく描写した選択肢を選ぶものですが,1問くらいはやや戸惑う問題が入っているかもしれません(2021年や2022年の問3など)。
実際,簡単な問題と難しい問題を両方含めることで初めて成績に差が付くわけですから,自分だけは全問正解できるなどと決しておごらず,できる問題を確実に得点していく姿勢でいることが大切です(勘でも25%の確率で正解できるわけですし,1つでも選択肢が排除できれば可能性は33%に上昇します)。
Bは内容的に正しいイラストを選ぶ問題ですが,英語の音が消失する感覚に慣れていればof herselfなども正確に聴き取れるでしょう。
イラスト間の違い部分に注目し,どの箇所が話題の中心になるのかを推測できると正解率が高くなります。
第2問もイラスト問題ですが,今度は複数話者の対話を聞き,話している物や場所について答えるものです。
dirtyとsunnyの単語から軍手と帽子を予測する(2021年)などの新形式らしい出題も見られました。
ここまでは2回読まれることもあって,そこまで慌てることにはならないでしょう。
しかし,第3問からはレベルが一段階上がります。
1回しか音声が流れない上,会話の量も多くなるからです。
第4問以降の問題では先読みの時間が別に取られますが,そうでない第3問で先読みが不要かといえばそのようなこともなく,かなり時間が足りないように感じています。
質問文と状況設定くらいは先に見ておかないと正直きついです。
似た音の混同(backとbag)を狙ったものも過去にありました(2021年)。
さらに悪いことに,正解の根拠が対話文の最後まで出て来ない問題もあるのですが,答えが決まり次第すぐに次の問題の先読みを行うようにしてください。
参考までに,音声が流れ終わってから10秒すると次の問題が読まれます。
第4問以降はメモを取る頻度が増えるかもしれませんが,最後に書いた内容が覆る可能性があることと,書くのに集中して聞き逃さないことに注意しましょう。
確かに図表から答えを判断できるので,以降の第5・第6問と比べてそこまで大変には感じませんが,全部正解して初めて得点になる問題もあるため油断大敵です。
第5問は講義内容をノートに取る形式になりますが,言い換え表現なども多いため,あくまで内容重視で聴くようにしてください。
選択肢は二項対立であったり,ポイントとなる単語さえ聴き取れていれば混乱するようなものではないですが,追加で音声が流れることもあってゆっくりはしていられません。
最後の第6問はAとBの2つからなり,前者はまだしも後者では国籍別の訛りと4人の話者に混乱させられるはずです。
これまでは女性と男性さえ区別できれば良かったところを,ここだけ同性内での区別もしなければならなくなります。
目標得点ですが,90点を取るには2回読まれる問題とグラフや表のある第4問をほぼノーミスで突破し,残りの問題において2~3問のミスが許される程度です↓
リスニングの得点の目安
第1問:25/25点
第2問:16/16点
第3問:12/18点
第4問:12/12点
第5問:15/15点
第6問:10/14点
実際はうっかりミスをしてしまうこともあるでしょう。
なので,より現実的な数字として「8割目標」で指導するようにしています。
その場合,上の状態からさらに2問どこかで間違えられることになりますが,1問あたりの配点が3~4点に相当するので,どれを間違えてもなかなかにダメージが大きいです。
途中まで順調に来ている人であっても,第5・第6問が本番だと思っていてください。
ところで,個人的にリスニング力がこのレベルに到達するのは歓迎していて,これほどに難しい問題を解かなければならないとなれば,さすがに多くの生徒たちはリスニング対策せざるを得ないでしょう。
共通テストが登場するまでは,リスニング力が高くても入試で有利に働くことはそこまでありませんでした。
できる人は満点ですし,できない人も7割くらいは取れましたから。
ですが本テストを見るに,リスニング対策をしないで挑めば5割ですら危うくなるはずです。
そうなれば,リーディングで9割取ったところで総合点は7割に激減してしまいます。
使える英語力を目指して頑張りましょう!
数学の解き方
数学IAの解答時間は70分と多めであるのに対し,数学IIBは60分です。
どちらも配点は100点満点で,記述式の問題は今のところ確認できません。
平均点の推移は以下の通りで,赤で示した令和4年度は難化しました↓
2021~2023年
IA:57.68→37.96→55.65点
IIB:59.93→43.06→61.48点
IA

第1・第2問は必答で,第3~第5問(場合の数と確率,整数の性質,図形の性質)から2つを選んで解答します。
第1問〔1〕は2次方程式や等式の問題。
素早く計算を行うことになりますが,空欄の形をできるだけヒントにして解いていきましょう。
計算は暗算を基本としますが,途中式を空欄の近くに書いておけばいざというときの見直しに使うことができます。
途中式を書くならきちんと書くし,暗算でやるならその分早く解くといった具合に,どっちつかずな状態は避けてください。
〔2〕は〔1〕とは別の分野からの出題になりますが,頻出の三角関数の問題であれば有名な公式群を手早く使って解いていきます。
正弦定理に余弦定理,はたまたsin,cos,tanの基本公式はすぐ頭に浮かぶ状態にしていないと間に合いません。
2021年度のものは三平方の定理の証明でよく見る形でしたが,この証明は東大入試でも出たことがある有名なものです。
もちろんそれを知らなくても,指示通りに式を立てていくと気づくと思います。
図を正確に書くことも大切ですね。
見た目からすぐに答えが埋まる問題もあり,例えば2021年度の(4)は他の問題が一切解けていなくても正解できました。
たまには簡単な問題もあるわけです。

第2問は見たことのない切り口で始まる問題が多く,まるでPISA型問題を解いているような感じを受けるかもしれません。
とはいえ,2021年の時のように「ストライドが0.05大きくなるとピッチが0.1小さくなる」といった文章以外に,わざわざ「一次関数で表せる」などとヒントが書いてあることも多いです。
その他,形式に慣れておくことが必要で,あまり問題を解いていないとカッコに「−(マイナス)」や「a(アルファベット)」を入れたり,2.00のような数字を「カ=2,キ=0,ク=0」とバラバラに答えたりする問題に混乱させられてしまうかもしれません。
第2問には,現実世界のデータ(例えば総務省HP)を出典とする問題も見受けられ,初年度から2024年に至るまで,箱ひげ図やヒストグラムに散布図などの統計に関する問題が必ず出題されてきています。
大体こういうものは,計算が入ってくると多くの時間を必要としますが,共通テスト程度ではグラフを分析するだけで解くことができるはずです。
ページ数はセンター試験の3倍くらいの分量となり,確かに見た目には多く感じられますが,実際にかかる時間はさほど変わりません。
統計を苦手とする受験生は想像以上に多く,毎年「必ず出る」と口を酸っぱくして言い続けているにもかかわらず解けないまま本番に挑む生徒が一定数存在します。
ここだけ平均点が毎年低めに出てくるのは上のような事情があるからでしょう。
第3問の確率の問題で考察問題が再び登場した際に,もしも解答群が与えられていれば,すべてのパターンについて調べずとも解けることは覚えておきましょう。
第4問は整数論的な問題で,不定方程式が多かったですが2024年はn進法でした。
第5問は,方べきの定理やチェバ・メネラウスなど,古典的な方法を使って解くことになります。
総じてこれまでのセンター試験と同じ公式を使って解くことができますが,時間が伸びた分,気が付きにくさがアップしていたり,考察問題がやや増えていたりで,つまづく箇所が増えている印象です。
焦らずに解ける問題をすべて解いてとりあえず7割程度を確保してから,残った時間で飛ばした問題のいくつを正解できるかの勝負になるところは従来の攻略法と同じになります。
目標点と解答時間の目安は以下の通りです↓
数学IAの得点と時間の目安
第1問:24/30点,20分
第2問:30/30点,20分
第3問:20/20点,15分
第4問:20/20点,15分
第5問:20/20点,15分
くどいようですが,数学では問題のヒントに気が付くことができなければ得点にならず,時間内に解ききれない問題が出てしまうものです。
ゆえに,解くべき大問の中で2ヶ所くらいは,それこそ一気に6点くらいマイナスになってしまうこともあるでしょう。
その箇所が1つで済めば90点台,2~3つあっても80点台となるだけです。
数学ができる人も「今回は運が悪かっただけだ」と思うようにして,自信までは失わないようにしましょう。
IIB

苦手な分野が多いという理由で,IAよりIIBの方が得点できない生徒も多いです。
昔はあり得ませんでしたが,ここ最近はIIBの平均点の方が高くなる傾向にあります。
第1問と第2問が必答で,第3~第5問(確率分布と統計的な推測,数列,ベクトル)のうち2つを選択しますが,ほとんどの方は第4問と第5問を解くことになるはずです。
第1問は今のところ三角関数の出題が顕著ですが,合成公式や加法定理の丁寧な誘導がありました。
どんな解き方をするかについても,「相加相乗平均の関係から」などの指示が見られ,ページ数が多い割にスムーズに事が運んでいきます。
とはいえ,指数・対数関数や恒等式の考え方が全く問われない年度もないため,幅広い知識を持っておかなければなりません。
第2問は関数(1~3次)の問題です。
文章を読んで登場人物が何をしているかを理解する問題も見られるものの,空欄から逆算することで,そこまで頭を使わずに解けてしまうこともあります。
適当に数字を当てはめて考えられる柔軟さは,共通テストにおいても有用です。
後半では接線の方程式や積分を使った面積計算が出てきます。
第3問は確率分布と統計的な推測の問題ですが,ベクトルが未習などの特殊な理由がない限り選択することはないでしょう。
ここでは省略します。
第4問は数列です。
等差数列と等比数列が混ざった漸化式が出てきましたが,誘導が丁寧なので,スモールステップで1つずつ答えていくと自然に終わります。
同じことを最初は具体的な形か簡単な形でやり,後半でより広い形で扱うパターンになっていくのでしょうか。
2023年の問題は預金の金利を計算するもので,実生活に数学の知識が役立つことがわかる良問でした。
第5問はベクトルの問題です。
最初は平面が中心で図形の性質と関連させた出題が中心ですが,後半となると立体の座標が出てくるか,より深い考察問題が出題されます。
内積や大きさの問題も見られるので,すぐに計算できるように練習しておきましょう。
目標点と解く時間の目安ですが,
IIBの得点と時間の目安
第1問:27/30点,17分
第2問:30/30点,13分
第4問:17/20点,13分
第5問:18/20点,17分
制限時間の関係で時間内に解き終わらない問題があることとうっかりミスがあることを考慮して満点狙いはやめましょう。
また,すべての問題が同じだけ難しいことはありえないので,上の目安時間にはあまりこだわらず,大問1つに計15分程度をかけることは基本に,簡単なものはできるだけ早く終え,計算が大変で取っつきづらい問題やいまいち考え方がわからなかったものを残り時間で解くようにしてください。
国語の解き方
国語は200点満点ですが,大学入試センターは平均点を100点満点に変換して掲載していることに注意してください。
また,過去問は著作権の問題で省略が目立つため,正確に時間を測って本番を再現とはいきません。
ここ最近の平均点の推移は以下の通りです↓
2021~2023年度
国語:117.50→110.26→105.74点

国語は生徒がノートに要約をまとめたものの他,自分で調べた内容や新聞の批評を引用するなど,共通テストらしい内容が大問ごとに見受けられます。
とはいえ,文章を解くにあたってこれまでと何か解き方を変える必要があるかと言えばそのようなことはなく,従来通りの勉強法と戦略でもって十分に対応可能です。
構成も,おなじみの「評論文,小説,古文,漢文」の4部構成となります。
それでは第1問からみていきましょう。
評論文は論理の構成がどのようになっているのかに注意したいので,指示語を明らかにしたり,文章の流れに影響する論理展開を示す語句に注目したり,時間の流れに注意したりします。
漢字は全問正解したいところですが,文字だけをみて判断すると失敗するので,簡単そうに感じても他の書き方が考えられないかを自問してください。
例えば「ミンゾク的な」と書いてあっても複数の候補が考えられるわけです。
同じ漢字の使い方を選ぶものも同様で,すべてに目を通すようにしてください。
文章自体については,指示語として「これ,その」,逆接として「だが,しかし,ところが,にもかかわらず」という単語が,時代を表すものとして「中世,近世,近代,今」といった単語がずっと出てきています。
全体を見通してからでないと解けない問題は極めて少ないので,傍線部が出てきたらその段落を読み終えたタイミングで解くようにして構いません。
なお,あまりに評論文が苦手であれば,意味段落ごとに見出しを付ける問題は読みながらリアルタイムで解いていくべきでしょう。
新傾向の問題として,さながらグループワークをしていて同じ班で話し合っているかのような問題もあります。
これらは結局のところ論理で解くことができますが,普段のクラス内での話し合いにおいても相手の主張は何なのか考え,説得力を伴う発表力を磨いておきたいところです。
第2問は小説ですので,人物の心情を中心に理解していきます。
評論文よりは読みやすいと感じても,選択肢が意外と難しいので正答率までが高くなるわけではありません。
例えば2021年度の問3などは,多くの人が2択までは絞れたように思います。
しかし,どちらもいまいち言い回しに気になるところがあり,最後の最後で間違えてしまった方も少なくないでしょう。
ですが,誤った選択肢というのは,一見内容に合っていることが書かれているものの,重点が置かれている位置がずれているものです。
「書いてある・書いてない」という議論から一歩進み,触れられてはいるけれども重点がずれてやしないかにも注目してみてください。
最後の問題では新傾向の問題が多く見られます。
例えば,批評家の意見の理解を問う問題だったり(2021年),生徒と生徒が話し合っているような出題があったりもしました(2024年)。
同じ文章でも注目する場所によって受ける印象が異なるところは,今後の社会に出る上でぜひとも押さえておきたいポイントです(多種多様な意見があって社会は成り立っているわけです)。

第3問は古文ですが,文法と単語の知識量が勝敗を決めるという構図はこれまでと変わりません。
古文では主語が省略されやすいので,誰が話しているかに注目しましょう。
登場人物が多いときには決まって関係図が用意されているものです(複雑な道具が図解されていることもあります)。
単語帳を1冊やり終えていればほとんどの単語の意味は問題なくわかるはずで,2021年度を例にすると「めやすし,まなぶ,里,消息,ゆゆしき,おろか,いみじく」は受験生ならばすべて知っておかなければなりません。
自らが「みづから」と平仮名になっていたあたり,難易度がより簡単になるように調整されていたように感じましたが,難しい問題では漢字で書かれているはずです(「おのづから」とも読めるので)。
また,和歌についてもそこまで大きな意味を持たされてはいませんでしたが,間接的であるにせよ必ず問われることになるので,鑑賞できる程度にまでは訓練しておきましょう。
第4問は漢文ですが,こちらは教訓めいたものが1つあって,それを中心に文章が作られています。
基本,最後の問題が教訓を問うもの(鑑賞)になっていますので,ここを間違えないことが最大のポイントです。
逆にここさえ押さえてしまえば,後はそこに合うように内容を逆算して考えていくような解き方もできます。
2021年の問6の内容が問3や問5の出来に大きく関係していることは明白です。
目安時間と得点目標ですが,全80分で200点満点を次のように配分してください↓
国語の得点と時間の目安
第1問:44/50点,25分
第2問:44/50点,25分
第3問:50/50点,15分
第4問:50/50点,15分
実際問題,現代文が20分ちょっとで終わったり,古典が10分以内で終わったりすることもあるでしょう。
なので,問題全体を見通すまでは最大に時間をかけても上記時間までとし,最後に余った時間で残りの問題を解くか,2択で悩んでいた問題を見直すようにしましょう。
なお,古典は現代文より満点が狙いやすいように思いますが,1問ミスまでは許容です。
ゆえに,9割を目標に設定してはどこか1つの大問で完答,残り3つは1問ミスまでOKと考えておきましょう。
理社の解き方
理社はラインナップが多岐にわたりますが,1科目60分の100点満点となります。
共通テストになったことで初見の問題が増え,読む量も多くなっている中で感じるのは「読む力」の重要さです。
理社を解く以前に,資料を正しく読むことができなければ,いわゆる「読めばできる(簡単とされる)」問題も正解できないでしょう。
なお,根源的に暗記科目である日本史や世界史であっても,出来事をつなぐための背景知識の方を理解する方がむしろ重要となってきており,教科書を読むこと,ひいては歴史マンガを使った勉強法はますますその重要性を増しています。
共テの理社に挑む前に,まずは以下の記事で述べた内容が身についているか確認するようにしてください↓
なお,ここでは理社を代表して「化学」と「日本史B」の解き方を紹介しますが,その他の例えば「生物」や「世界史B」も同じ考え方で攻略することが可能です。
化学

化学は大問の数が5つあり,それぞれが20点満点と計算しやすいが,問題数は年によって変わる印象です。
とはいえ,どこか特定の分野しか学ばずにテスト本番に挑むことは基本ない(もし挑んだとして受験で有利になる点数は取れない)ため,以下のように捉えておくのが現状良いように思われます↓
- 第1問=理論化学①
- 第2問=理論化学②
- 第3問=無機化学
- 第4問=有機化学
- 第5問=特に定めず
なお,同じ理論化学でも①と②で出題の内容は重なりませんし,第5問はユニークな出題です。
計算問題は大問1つにつき0~2題含まれ,割り切りやすい数値が選ばれがちではあるものの,その他の問題と比べると時間はどうしてもかかってしまいます。
加えて,問題の難易度も高めです。
共通テストだけあって,身の回りにあるものを化学的な切り口でみていく問題が見られ,どのような形で化学の勉強が実際の役に立つのかがわかるようになるのが特徴と言えるでしょう。
2024年の例では医薬品(第4問)やドーピング検査(第5問)の話が登場してきました。
計算は工夫して時間を節約するか,どうしても解けないものは捨て問とし,無駄に時間を費やすことの無いようにするのが解き方のコツです。
数学のときのように,特に他の問題と内容的に繋がっていたりはしないので,連続して間違えることにはなりません。
8割得点するための目安は以下のようになります↓
化学の得点と時間の目安
第1問:16/20点,12分
第2問:16/20点,12分
第3問:16/20点,12分
第4問:16/20点,12分
第5問:16/20点,12分
それぞれの大問で難易度に違いはないので,どれも1問ミスに留めるようにすれば自ずと8割が達成可能です。
とはいえ,気になったものを後で見直せるほどの時間は余らないため,ギリギリの戦いになることを覚悟しておきましょう。
ちなみに,上で言った1問ミスには「時間がかかりそうな計算問題を1問捨てる」ことも含まれていると考えてください。
日本史B

大問の数は全部で6つあり,第1問は特に時代を限定しませんが,第2~第6問はそれぞれ決まった時代からの出題です↓
- 第1問=特に定めず
- 第2問=原始&古代
- 第3問=中世
- 第4問=近世
- 第5問=近代
- 第6問=近現代
ということでどこかの時代に限定して学ばないようにするとともに,上で示したような硬い内容の資料を正しく理解することが重要です。
実際の設問においては
「資料から読み取れる内容は何か」
「資料から読み取れる内容としてこれは正しいか否か」
が問われることになるため,中には何の知識がなくてもただ資料を正確に読むだけで解けてしまう問題すらあります。
これを予備校の分析速報などでは「簡単(易問)」などと判定するわけですが,国語ができない読む力の低い生徒にとっては難問です。
例えば上に示した資料を基に,以下の内容の正誤が自信をもって判断できるでしょうか↓
- 岩城国は既存の一か国を分割して作られた
もちろん,確実な知識を多く持っておくことも重要で,出来事が3つ並べて書いてあってそれらを正しい順番に並び替える際には年号の知識が問われます(もちろん,時代背景の知識だけで解くこともできます)し,説明や作品名を聞いて事件名や人物名を答えるためには必須です。
なお,日本史Bは本来時間を十分に余らせて終えられる科目で,それは読む量が増えた共通テストにおいても変わっていません。
全部の文章を読んだとしても時間以内に解き終わります。
なお,正解すべき目標点に関しては第1問が低くなる傾向にあるのは正しくても,その他は問題自体の難易度によって変わるために安定はしません。
なので,以下のような書き方になってしまうはずです↓
日本史Bの得点と時間の目安
第1問:9/18点以上,10分
第2問:12/16点以上,10分
第3問:12/16点以上,10分
第4問:12/16点以上,10分
第5問:9/12点以上,10分
第6問:18/22点以上,10分
すべて最低点を取ってしまうと72点なので,実際は全て満点の大問があったり,配点が3点の問題のみを間違えるなどで+8点を確保して8割を達成してください。
なお,中学歴史に毛が生えたレベルの知識で解くと5割が目安です。
なので,5割に届かないレベルの方は中学の歴史からやり直しましょう。
終わりに

初めての共通テストを受けるにあたって,
「試験方式が変わって混乱する!」
などと不安がっていた生徒もいましたが,私は
「対策しないで臨める分,受験生のそのままの実力が反映されやすい最も良いテストになるんだよ。」
と正すようにしていました。
次回以降もどこかの問題形式が大きく変化すると思いますが,遭遇した際にはそれをチャンスだと捉え,気を引き締めて臨むようにしてください。
テスト本番ではとにかく全力を尽くすことだけを心がけるべきで,これまでと同じ問題が出てホッとするようでは緊張感が足りていません。
油断して間違えてしまうことも大いに考えられますし,簡単な問題ではみんなが正解できてしまうために平均点は上がってしまうものです(実際,平均点が高めだった初年度は強気の出願が目立ちました)。
試験中は必死に解くようにし(ただし必死と焦るは別です),最後の問題を時間内にちょうどやり終えたときに「何とか終えられて良かった」などとホッとするくらいがちょうど良いでしょう。
とはいえこの場合においても,自信がなかった途中の問題にはチェックが入っているでしょうから,すぐ戻って見直すことになるわけで,休息は基本的に訪れません。
これから共通テストが行われる回数が増えていくにつれ,予備校で多くの対策をした人ほど点数が取れるようになっていきます。
初回のテストですらプレテストをもとに対策していた受験生も多かったわけですが,教育にお金をかけられた生徒ほど貴重な情報が得られるチャンスが高くなるということは,環境に恵まれていない受験生にとっては大変辛いものです。
例えば,2021年度の英語でfact(実際に起きた事実)とopinion(個人の意見)が問われましたが,翌年の講習で早速,選択肢のどこに注目しどのようなダミーが用意されるのかを事細かく教えることになったわけです。
リスニング対策においても,どの問題を先読みすればよいかだったり,1回読みと2回読みの問題でどのように聞き方を変えればよいかだったりを,より細かく指導するようになりました。
大学入試と言うのは小手先のテクニックで点数が取れてしまうことも多いので,本来の学問とかけ離れてしまっている部分ではありますが,そういった勉強も是非行うようにしてください。
特に普段真面目に勉強している人ほど,そのような「ラクな思い」を経験すべきです。
実際,2021年と2022年で,ほとんど解き方や出題範囲に違いは見られませんでした。
もちろん難易度は受験する年ごとに変わるものですが,自分だけが難しい問題を解いているわけではないことは,いかなるときであっても忘れないようにしてください。
みんなができなければ,低い得点であっても偏差値自体は変わりません(令和3年度は理社の一部で得点調整が行われました)。
テクニックで差をつけられないよう,季節が秋以降になったらオンラインでも構わないので対策講座を受講しておきましょう↓
当記事を読まれたみなさまが,共通テストで弾みをつけて,2月以降の本番に臨めることを祈っております。
ありがとうございました。