スタディサプリで小学校の算数について学んだ場合,一体どの程度まで学力が上昇するのでしょうか。
低学年向けのものもありますが,今回注目するのは「小4~小6算数」です。
当記事ではこれらの概要について説明するところから始め,小学校の授業から中学受験にまで使えるかどうかについても検証してみたいと思います。
スタディサプリの小4~小6算数とは

スタディサプリの小学算数講座ですが,小学4年生から6年生までの高学年を対象としたものと,3年生以下の低学年用のものとで内容が異なることに注意してください。
後者については別に記事にしてありますが,小4までの復習用に使うこともできます↓
近年,小4に満たない段階から塾に通う子どもが増えているとの話も聞きますが,私自身が教えている都内の個別指導塾においてはそのようなケースは稀です。
個人的には「たとえ中学受験させる場合であっても,本格的な対策は小学4年生になってからで十分間に合う」と考えており,それは令和時代においても変わりません。
とはいえ,勉強する必要がないとまでは言っていません。
そろばん教室に通わせたり図鑑や学習マンガを買い与えたり,それこそスタディサプリの低学年講座で学んでおくのも良いでしょう。
特に重要なこととしては,読書習慣を身に付け,算数の文章題の内容を正確に理解できるだけの読解力を身に付けておくことだと思っています↓
-
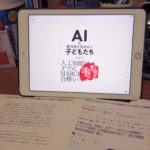
-
頭が良い中高生は「読む力」が高い件について
最近はコンビニやスーパーも無人化に近づきつつあり,ロボットが人間に代わって多くの仕事を請け負う時代の到来をより一層意識するようになりました。 そのような社会において必要とされる人間であるためには,ロボットが苦手とするコミ ...
続きを見る
話を戻しますが,小学校高学年になった生徒がスタディサプリで算数の勉強を始めようと考えた場合,講座の難易度を「入門編・基礎・応用」の3つから選択することが可能です。
これらの具体的な講義数は,
小4~小6算数の講義数
小4:入門編36講義,基礎30講義,応用15講義
小5:入門編37講義,基礎32講義,応用30講義
小6:入門編31講義,基礎32講義,応用30講義
の全273講義となっています。
講義では毎回動画を視聴することになるのですが,内容が難しくなるにつれて講義時間は長くなる傾向にあるものの60分に達することはなく,学校の授業と同じくらいです。
ただしそれに復習や板書の時間も加わるので,1講義こなすのに1時間から2時間くらいかかると見積もっておきましょう。
つまり,1学年分の全レベルの講義を視聴したいと考えれば全部で200時間程度を見込んでおく必要があるわけで,1年かけて取り組むには十分な量が用意されていると言えます。

ちなみにそれぞれのレベルの難易度は,
- 入門編=学校の授業を1から理解する
- 基礎=教科書レベルから思考力を要する応用まで
- 応用=中学入試の小問レベル
であり,講座内容に重複する部分はほとんど見られず,下に位置する講座ほど難しくなっていることは明らかでしょう。
算数が苦手な子であれば入門編から始めればよいですし,学校のテストで満点を狙うのであれば基礎を,そして中学受験を視野に入れる方は応用で学んでおくことをお勧めします。
ところで,これらの講座を担当する講師はまったく別の3人となっており,飽きや相性といった問題が発生しにくくなっているところも特筆すべきでしょう。
スタサプの講師陣については以下の記事をお読みください↓
内容については文字による説明だけだとわかりにくいと思いますので,次章以降で詳しくみていくことにします。
入門編の講義内容について

まず,算数の根幹部分を教える「入門編」から見ていきますが,担当講師は加古希支男先生です。
上の記事で述べたように,彼は経済学部を卒業して一般企業に勤務した後,教育免許を通信教育で取得し30歳で小学校の先生になるという異色の経歴を持っています。
2013年からは東京学芸大附属小金井小学校の教諭をしており,関わった研究が第61回読売教育賞最優秀賞(算数・数学教育部門)を取ったり,授業方法に関する先進的な書籍を複数出版するほどの実力者です。
見た目からも名前からも堅そうな印象を受けますが,真面目な教え方が特徴的で,先生自身,算数が大好きである様子が動画からひしひしと伝わってきます。
本講座の内容ですが,例えば小学6年生のものだと以下について学べるものであり,学習指導要領が改訂された2020年に内容がアップデートされました↓
小6算数入門編の学習内容
対称な図形,円の面積,文字と式,分数のかけ算とわり算,角柱と円柱の体積,比と比の値,拡大図と縮図,速さ,比例と反比例,並べ方と組み合わせ方,資料の調べ方,量の単位
ちなみに,上の赤字部分は高校生になってからも使う重要な項目であり,理解が不十分なまま受験生となった生徒が大変に辛い大学入試を強いられているのをみると,小学生のうちから完璧に理解しておくことが極めて重要であると思わずにはいられません。
また,「文字と式」であったり「並べ方と組み合わせ方」のように,中学に入ってまもなく役立つ項目も見受けられるので,「中学校に入ってからも困らない学力を」と考えている保護者の方にもすたでぅサプリの入門編の受講を勧めたいと思います。

基礎と入門編のどちらから学ばせるべきか悩むような場合は,入門編のテキストにある確認テストをまずは解かせてみてください↓

逆に言えば,基礎や応用レベルに進む前に,上のような問題が完璧に解けなければなりません。
小4~小6算数のテキストはPDFで自由にダウンロードできますし,PCの大画面で確認することもできます↓

テキスト自体には小学生が学習しやすいように余白が多めに取られている上,ヒントの図表やコメントも加えられていて,まさに小学校の教科書らしい構成です↓

加古先生の学校での授業経験が,スタディサプリの教え方にも生かされているように感じます。
基礎の講義内容について
続いて「基礎」と呼ばれる講座についてみていきましょう!

こちらは尾崎正彦先生が担当します。
彼は新潟大学の教育学部を卒業し,浜浦小学校の教諭を経験されただけでなく,新算数教育研究会の奨励賞や文部科学大臣賞,全国算数授業研究会全国理事や新潟市教育委員会認定のマイスター教師になるなど,多くの業績や活動歴がある方です。
時代の要請に沿った思考力の育成を目指す授業は,国公立の中学を受験する際にも役立つでしょう。
授業は細部までよく考えられた丁寧な作りとなっていますが,線対称の講義で回文(「若山やはるか光るは山や川」のように,逆に読んでも同じになる文)の説明から入ったときには大変驚かされました。

講義内容は入門編とほぼ同じ順序で進んでいくものの,より深くまで掘り下げた内容であることは明らかです。
特徴的なのはテキストの構成であり,板書や授業内のポイントを書き込む形のテキストになっているため,入門編以上に余白部分が目立ちます↓

教育業界において,プリントを用意して授業する先生というのはひと際教育熱心で,それだけ良い授業をすることはもはや定説化しており,小学生にどのように授業をすればよいのかよく研究されていることがこのテキストを見た瞬間に伝わってきました。
講義動画を一時停止して,書き込んだり考えたりする時間がその都度取られるところにも,授業の進行が綿密に計算されていることがわかります。
なお,各学年の最後の講座はまとめとなっており,幅広いジャンルから出題されるところが特徴です↓

面積の問題を説明するのに「ピザの例」を持ち出すのは,実は2020年の教育改革のモデル授業を受けた際にもよく目にしました。
学習指導要領が新しくなっても,緒方先生であれば時代に沿った内容でもって授業してくれる安心感があります。
なお,この基礎講座のみ「小学生向け問題集」というコンテンツが利用でき,全範囲のチェックをより短時間で行うことができます。
こちらについては解説や動画などが存在しないため,子どもが間違えてしまった際は親が教える必要がありますが,簡単に子どもの実力が把握できるので是非使ってみてください↓

小学生向け問題集に関しては,以下で使い方についてまとめています↓
応用の講義内容について
最後に説明するのは「応用」の講義ですが,こちらは完全に中学受験用です。

かなりがっつりと勉強することになるので,勉強習慣が身についていない子には不向きですが,真面目に取り組める子であれば大きく学力がアップすることと思います。
担当するのは繁田和貴先生で,小学生時代はサピックスの模試で3年連続全国1位となり,その後は開成から東大に進学するなど,学力で彼の右に出るものはいません。
現在は個別指導塾TESTEA(テスティー)の塾長をしており,15年間で3000人の指導経験があることからも中学受験のスペシャリストだと言えるでしょう。
中学受験の経験がある方だと講義のタイトルを見ればすぐにわかるかと思いますが,小6講座は受験頻出の項目ばかりです↓
小6算数応用の学習内容
相似,面積比,流水算,出会い算,通過算,時計算,速さ,水量,数の問題,N進法,平面や立体図形,旅人算,食塩水など
小学4年生の講座こそ講義数は全部で15しかありませんが,小5,小6ともに30講義が用意されており,彼の授業を安価で受けられてしまう機会はスタディサプリなしには実現できなかったでしょう。
ちなみに繁田先生の教える塾では90分授業を1回受けるだけでも9000円前後します↓
入会金(22000円)や運営費(19800円)を計算に含めずとも,例えば月に4回授業があれば36000円ほどです。
授業形態が違うためコスパ的な比較はできませんが,これだけでスタディサプリの年間利用料金よりも高くなってしまうわけですから,導入段階としてスタディサプリという選択肢は十分に考えられるのではないでしょうか。
なお,スタディサプリにおける彼の講義スピードは相当に速く,まさに中学受験の予備校的な授業が展開されますし,テキストの問題の質もそれにふさわしい内容となっています。
TESTEAに通う前の予習段階に見てみるのも良いですね。
講座説明には「中学入試の基本的な小問(大問の1や2)を主に扱う」とありますが,これらの講義を通して培った技術はそれ以外の問題(大問の3以降)を解く際にも使うことになりますので,本番で役立つ場面は決して少なくありません。
各講義で解くことになる問題量も10問近くに及ぶことがほとんどで,頻出問題を完璧にできるようになることを目指しましょう。
受験経験がある方であれば必ず一度は解いたことがある問題です↓

繰り返しになりますが,中学受験をする予定のある方は,これらの講義内容をマスターした後で第1志望校の過去問であったり,演習量を補うための参考書だったりを別にやる必要があることは忘れないでください。
別の見方をすれば,中学受験特有のテクニックばかりが身に付くとも言えるので,学校の授業が理解できる程度で良ければ「基礎」までやれば十分でしょう(続けて中学内容の予習をするのが良いように思います)。
まとめ

以上,スタディサプリの小学講座から算数について紹介してきましたがいかがだったでしょうか。
レベルが細かく3つに分かれていることもあり,幅広い目的に応じて使える講座が揃っていることがわかっていただけたのではないかと思います。
最後に1つ気になる点を述べれば,スタディサプリのコンセプトである「効率重視の学習」が前面に表れすぎてしまっているところでしょうか。
講義内容からは無駄な部分が極力省かれているのは聞こえは良いですが,逆に小学生が好きな雑談などはあまり見られない傾向にあります。
例えば「速さ」の講義では,「きょり=速さ×時間」といった説明が出てきますが,私の塾だと教師が大げさなリアクションと共に「木の下のハゲじじい!」とか「キティーちゃんは痔!」などと声を張り上げて笑いを取るようなところが,スタディサプリでは確認できません。
流行りのアニメやマンガの話題も権利の面で出せるはずもなく,この状態で小学生に授業をするのは私だと難しいと感じます。
丸暗記を極力減らし,「どうしてそうなるのか」を論理的に説明することで忘れにくくさせるという工夫は講座の随所に確認できますが,楽しい学習ができたと感じるかどうかは人を選ぶ可能性があるということです。
ゆえに,これからスタディサプリの導入を考えていらっしゃる方は,子どもが飽きずに続けられそうかどうかを念頭に置いて,必要に応じて声掛けをしたり褒めたりする要素を加えていきましょう!
スタディサプリには「サプモン」というお楽しみコンテンツは存在するものの,どこぞの通信教育のように添削課題やプレゼントがあるわけではありません↓
-

-
サプモンの遊び方!ガチャを回してバトルをしよう
スタディサプリでは「サプモン」というゲームで遊ぶことができます。 ただし,そのためには普段から勉強してコインを稼いでおく必要があるため,まったく勉強と無関係なものではないですし,サプモンの存在がスタサプを頑張るためのモチ ...
続きを見る
そういった意味でも親の干渉は必要で,面倒であってもその日の授業が終わった後にどれだけできるようになったのか確認問題などを解いてもらい,ちゃんと説明までできた際には大いに褒めてやるようにしてください。
週末にまとめて親がチェックするでも構いませんが,何らかの確認作業を行うだけで子どものやる気は大きく変わってくるものです。
結果として,算数を題材とした多くの知的活動(数字を使ったミステリー小説やパズル遊びなど)を楽しめるようになってくればその子の未来は明るいでしょう。
まずは無料体験から始めてみてください↓
なお,小学講座をお得に利用できるキャンペーンの最新情報については以下でまとめています↓
-

-
【2024年7月】スタディサプリのキャンペーンコードまとめ
当記事では「スタディサプリのキャンペーンコード」に関する最新情報を記載しています。 ところで,一口に「スタディサプリ」といっても様々なコースやプランが存在し,コーチに見てもらえる「個別指導塾オンラインプラン」や「合格特訓 ...
続きを見る
最後までお読みいただきありがとうございました。