今回の記事では,高校受験をする予定がある中学生がどのように3年間かけて勉強していけばよいかについて,特に「参考書や問題集の使い方」を中心に解説してみたいと思います。
オンライン環境が整備され,新しい教育改革が進行中の昨今においては,家庭学習の重要性がますます増してきているわけですが,部活や習い事で忙しい中学生ですから,その現状を踏まえた上で早期のうちから効率良く学習を進めていきたいものです。
その時,学校の教科書やワークだけを使って勉強していくのはおすすめできません。
というのも,学校の教科書は授業が前提になっていて独習するには向かず,難易度的にも高校入試に対応できるレベルではないからです。
そのため,参考書や問題集を積極的に使っていきますが,中1のときから適切に用いることができれば学校の成績は常時トップクラスを維持できるでしょう。
以下では,おすすめ教材として具体的な書籍名も挙げていますが,各社から似たような本はたくさん出ています。
学校や塾の先生から何かを勧められることもあると思いますし,紹介している本が手に入らなかったり気に入らなかったりすることもあるでしょう。
そのような場合,似た目的で書かれた書籍であれば十分に代用することが可能ですので,目的にだけ注意して適宜購入していただけたらと思います。

高校受験英語のおすすめ参考書と問題集
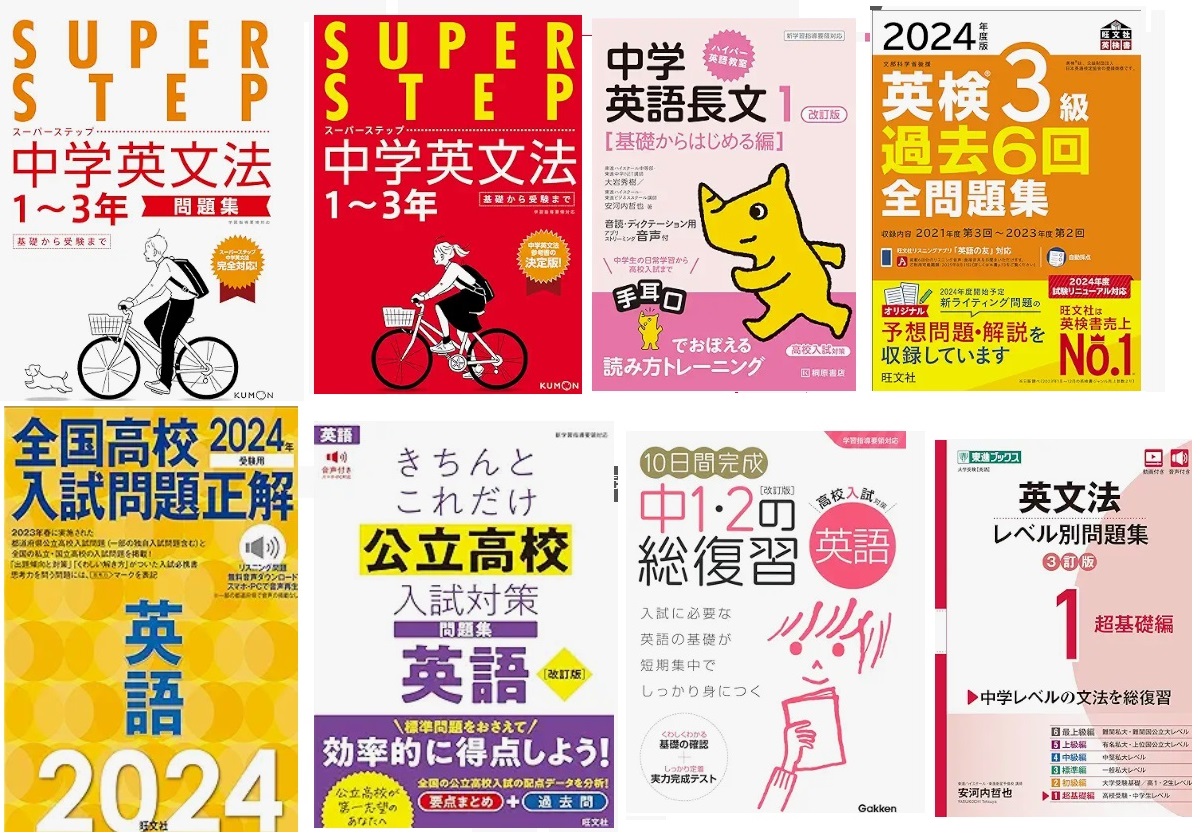
まずは最重要科目と言っても過言ではない英語からみていきましょう!
中学1年生向け
中学1年生が用意すべき参考書と問題集は以下の3種類です↓
- 文法の参考書と問題集
- 基礎的な読解用の問題集
- 英検4~5級の問題集
日常的にはAを用いて勉強しましょう。
おすすめの教材としては「新中学問題集(新中問)」が1番やりやすいように感じています↓
とはいえ,この問題集は個人用には販売されていないので,塾に頼んで手に入れてもらうくらいしか購入ルートがないのが難点です(私立だとこれが学校の教材に指定されているところもあるのですが)。
難易度は標準編で構わないので,その分,早いペースで進めることを優先しましょう。
なお,塾に来ている難関私立校に通う生徒の場合で言うと,夏休みの間だけで中学1年生の全文法範囲を終えることもあります。
Aに該当する市販参考書の中では,くもん出版の「スーパーステップ中学英文法1~3年」が優れているように思うので,参考書と問題集の2冊をセットで買ってください。
もちろん,中1範囲のみで結構です。
続いて上のBですが,これは夏休みや冬休みのような長期休暇を利用して一気にやってしまいます(普段は文法学習中心のため)。
例えば「ハイパー英語教室中学英語長文1」が考えられるでしょう。
最後にCですが,こちらは旺文社の「過去6回全問題集」などを使い,音声までしっかり聴くことでリスニング能力を鍛えるようにしてください。
その際はディクテーションまで行うようにし,できれば発音の方法も学んでおくようにします↓
腕試しとして,中1の2学期には英検5級に挑戦してみてください。
中学1年生の英語学習で大切なことをまとめると,文法をしっかり学習して基礎力を養い,読解へと発展させていくこととなります。
文法用語がわからないと参考書に書かれている解説が理解できないので,Aを使う際は「形容詞」や「副詞」といった用語に気を配ることが重要です。
単語のスペリングを苦手とする生徒は多いです(これはどんなに優秀な生徒であってもです)ので,何回も書く以外に,家では発音も取り入れて覚えるようにしてください。
スピーキングテストは今後多くの高校入試でも採用されてもおかしくないですし,ちょっと気が早いかもしれませんが,共通テストに向けた有効な取り組みにもなるはずです↓
中学2年生向け
中学2年生になっても中1のときとやることはほとんど変わりません。
ただし,ある程度文法知識が増えてきた頃になるので,以下のDで挙げたような総復習ができる問題集を最後に1冊仕上げましょう↓
- 文法の参考書と問題集
- 基礎的な読解問題集か長文問題集
- 英検3~4級の問題集
- 中学1~2年の文法まとめの問題集
中2の文法で難しいとされるのは「不定詞」と「動名詞」の分野です。
これらを学校の授業を受ける前に予習しておくと先生の話が理解しやすくなりますし,学校の授業が良い復習になります。
中1に引き続きAでは「新中問」またはくもんの「スーパーステップ」を,Bには「ハイパー英語教室中学英語長文2」を,そしてCには旺文社の「英検問題集」などを使うようにしてください。
最後のDに関しては学研プラスや文栄堂などから「中1・2の総復習」といったそのまんまなタイトルの参考書が出ていますので,書店で見て取り組みやすそうなものを選びましょう。
1周であれば7~10日で終わると思いますが,3周くらいはしてほしい他,取り組む時期はある程度学習が終わりに差し掛かった冬休みまたは春休みにやるのがおすすめです。
Bも中3になる前の春休みに集中的に行いましょう(中3への橋渡し的な使い方です)。
学校があるときは部活で忙しく,勉強時間が満足に確保できていない方は,長期休暇の過ごし方が特に重要となってきます。
中学3年生向け
中3生ともなれば,いよいよ高校受験の年です。
部活も引退前で忙しくなりますが,勉強の方も継続していきましょう!
おすすめは以下の通りです↓
- 文法の参考書と問題集
- 長文の読解問題集
- 中学3年間の文法まとめ問題集
- 志望校の過去問
1学期は文法に専念します。
中3の文法は中2のときよりもまた一段難しくなるので頑張りましょう。
このとき並行して,学校の教科書に出てきた単語を全部覚えてください。
巻末にある索引を見て意味を言っていくのもいいですし,覚えるべき単語は教科書の枠外にもピックアップされてきているはずです。
まとめ方は単語カードを使うでもスイッチノートにするでも構いません↓
6月には英検がありますが,そこで3級(できれば準2級)に受かれば,学力的には順調に育ってきていると判断できます。

中学最後の夏休みは長文を精読して過ごすようにします。
「精読」というのは「時間を気にせず,ひたすらわかるまで考えながら,丁寧に1文1文読むこと」です。
この際,構造分析のトレーニングをすることになりますが,塾では東進の「レベル別問題集レベル1」を使っています。
他にくもんの「スーパーステップ中学英語リーディング」も,ノートに訳を書くようにしながら読み進めていけばかなりの力が付くはずです。
2学期が始まったら志望校の過去問を2年分やり(残りはやらず,直前用に取っておく),出題傾向を掴みましょう。
その後はひたすら実践的な演習を行うのみですが,Amazonの検索欄で「高校入試 英語」などと入力して表示されてくるものが,この時期に使うべき参考書に該当します。
「きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集」から「入試問題正解」までより取り見取りです。
2学期から直前期にかけては精読をしている余裕はありません。
本番と同条件で,問題を時間内に解き終わることに重点を置きましょう。
薄めの長文問題集であれば,難易度を変えて最低でも2冊は終わらせるようにしてください。
もちろん直前期は過去問練習に全力です。
以上が,中学での3年間における英語の勉強法でした。
大学入試ではさらに顕著になりますが,英語が得意でないとスタート地点にさえ立てない学校が増えてきています。
高校入試に限らず今後の人生に関わる1大イベントとして,英語の習得を本気になって目指しましょう。
高校受験数学のおすすめ参考書と問題集

お次は高校受験数学ですが,英語と同様,習得するのに時間がかかるため,得点源にするには適切な参考書と問題集が必要となります。
中学1年生向け
- 問題集
数学においては,教科書内容を理解した後,とにかく演習量を増やすことが大切です。
ちなみに,中学校から文字を扱う式が登場するわけですが,ここを理解不十分のまま先に進んでしまうようでは,以降数学の勉強についていけなくなる可能性があります。
文字を使った足し算・引き算といった四則演算から,代入や移項といった計算方法にも慣れるようにしてください。
小学校で扱った分数なども,とにかく早く正確に計算できるようにしておくことが,今後の点数に良い影響を与えます。
演習量を増やすために,英語のときにも紹介した「新中学問題集」を第一に勧めますが,市販品としては「チャート式中学数学」や「ハイクラステスト数学」が良いです。
参考書とセットで買うなら中高一貫校の生徒が普段使う「体系数学」を勧めます。
とはいえ,上で挙げたものはもれなく難しいため,数学が苦手な方は学研プラスの「中1数学をひとつひとつわかりやすく」などから始めましょう。
中学2年生向け
- 問題集
中学2年生の数学でつまづきやすいところは,2学期に登場する1次関数です。
こちらも,ちゃんと理解できるかできないかで数学が得意になるか苦手になるかが決まってしまうので,気合を入れて乗り切りましょう!
なお,図形では入試に頻出の証明問題が登場してきます。
こちらは解き方をノートにしっかりと書いて,練習を積むようにしてください。
ただ眺めて読むだけではいけません。
参考書は中1のときに紹介したものの中2版を用いますが,物足りない中学生は「最高水準問題集特進」や月刊誌である「高校への数学」をやれば完璧でしょう。
中学3年生向け
- 問題集
- 分野別強化演習
- 過去問
中学3年生の学習カリキュラムですが,夏までに志望校の問題を1回解いておくことが重要です(直近3年分の過去問は直前期のために取っておきます)。
数学では,受ける学校によって出題範囲が大体決まるので,過去に出題された問題を参考に得意分野を作るようにしましょう。
そのためには,夏休みを用いて得意分野を厳選し,目をつけた単元の演習に時間を割くようにします。
上のAでは,これまでに使ってきた問題集をやり直すのも良い方法です。
Bに該当するものとしては,旺文社の「全国高校入試問題正解 分野別過去問」があります。
夏休みが終わったら考え方を一転させ,今度は苦手分野をなくすことに専念してください。
得点を周りと競う受験においては,この考え方が極めて重要です。
このとき,解説を読んでもわからない問題については無視して構いません。
とはいえ,その分野における教科書の章末レベルの問題は何が何でもできるようになっておきましょう。
直前期には取っておいたCの過去問3年分を使って演習してください。
高校受験国語のおすすめ参考書と問題集

中学1年生向け
- 語彙用問題集
小学校までの国語に自信がない場合は語彙力を増やしましょう。
Amazonで「小学校 語彙」と検索すれば問題集がいくつか出てくるはずです。
それ以外は学校の勉強をしていれば基本大丈夫ですが,何かしたいという生徒には受験研究社の「中学10分間復習ドリル(読解や漢字・語句)」をやらせることがありますし,国語が苦手な子にはくもんの「中学基礎がため100%シリーズ」を勧めることもあります。
中学2年生向け
- 読解問題集
中学2年生になったら,秋ぐらいまでに読解の基本的な問題集を2冊は仕上げておきたいところです。
塾では,解説がしっかりしている「出口式中学国語 新レベル別問題集(0~1)」を勧めています。
出口氏の書かれる問題集は解説がとにかく充実しているので,そこで学んだ解き方の手順を別の問題に生かしていくよう心がけましょう。
中学3年生向け
読解の正しい解き方を習得し,その後問題演習へと進むというのが中学3年生の国語の学習手順です。
- 読解の基礎問題集
- 古文と漢文の参考書
- 過去問
Aですが,中2のときに出口氏の問題集を使った生徒は,そのまま「中学国語新レベル別問題集(2~3)」に進んでください。
Bにおいては,長期休みを利用して,受験研究社の「中学トレーニングノート(古文・漢文)」か旺文社の「とってもすっきり古文漢文」をそれぞれ使ってみるのがおすすめです。
なお,難関校を受験するような生徒には「出口式現代文 新レベル別問題集0」をやらせることもありますが,独学する難易度が極めて高いので自分の実力とよく相談してください。
秋以降はCを使って問題演習を行いましょう。
一般的に,国語は同じ問題を何度もやり直すことはせず,毎日違う問題を解くことで学力が伸びていきます(ただし,漢字や文法は繰り返しが必要です)。
高校受験理科・社会のおすすめ参考書と問題集

中学の理科・社会は英国数に比べると重要度が落ちますが,積み重ねがそこまで必要にならない教科なだけに,やる気を出せばすぐにできるようになります。
勉強法は,教科書を読んでは問題集で理解を深めることの繰り返しです。
どちらも暗記科目なため,中学3年時には中1・中2でやった内容を再度学び直すことになります。
一度完璧に理解した内容であれば,仮に忘れてしまっても思い出すまでの時間が短く済むため,中1のうちからしっかりと勉強しておくと後になって楽ができるとここで述べておくことにしましょう。
まとめノートを作っておいたり,学校のノートやテスト問題を取っておいたりすることが後々役立ってきます。
中学1年生向け
- 問題集
- 参考書
Aとしては「ニューコース」が有名ですが,教科書に沿った内容を扱った定期テスト用の問題集であればなんでも構いません。
なお「さらにレベルの高い勉強をしたい,詳しく知りたい!」という生徒には旺文社の「中学総合的研究」を勧めています。
こちらはBに当たる参考書になりますが,かなり詳しいところまで書いてあるので,好奇心旺盛な生徒には非常にためになると評判です。
学校で配られる資料集(イラストや写真中心の参考書)も重宝します。
中学2年生向け
- 問題集
- 参考書
中学2年生になって1つやってみてほしいのは,歴史と地理におけるまとめノート作りです。
テスト勉強のときに作成した「まとめノート」は,中3になって必ず役に立ちます。
また,中2の理科の電流のところでつまづく生徒が多いので,予習を中心に復習までしっかりやっておきましょう。
勉強法やノート術は以下に詳しくまとめているので参考にしてください↓
2年生の冬休み以降に時間があれば,中学1~2年生のときに学んだ内容を総復習します。
そのときに使う問題集や参考書はこれまでにやったもので大丈夫です。
中学3年生向け
- 問題集
- 参考書
- 入試演習
主要科目(英語や数学)と異なり,理社は学年が変わってもやることに大差ありません。
難易度は変わらず,基本的には範囲がただ広がっていくだけです。
中3理科においては運動と天体が要注意の単元となります。
夏休みには,中2の電流の範囲も含めてよく復習しておきましょう!
高校入試における理社の問題は,主要科目と比べると難解なものはなく,苦手分野をなくしてさえおけば特に問題は生じません。
出題範囲はどの学校においても共通ですし,ほとんどの生徒が高得点を取るので差がつかないわけです。
逆に言えば,定期テストで点が取れない子は毎回非常に苦しむことになるため,理解不十分なまま入試に挑んでしまうと周りに差を付けられてしまいます。
なので,油断せずに復習を小まめにしましょう。
とはいえ,「ニューコース」さえしっかりやっておけば,定期テストで8割を切ることはほとんどありませんし,中1や中2での復習回数がこの辺りになって物を言い始めます。
まとめ

ここまで,高校入試に役立つと思われるおすすめ参考書や問題集を科目別かつ学年別に紹介し,その使い方についても説明してきましたがいかがだったでしょうか。
積み重ねが必要な英語と数学は特に注力して取り組むようにして,長期休暇の際には普段できない特別な演習や総復習をするのがポイントです。
1つ言い忘れていましたが,過去問を使う際は時間を測って丸付けや間違いの分析までしっかり行いましょう。
なお,今の時代はオンライン教育も簡単に利用することができるため,参考書代わりとして用いることで独学するよりもハイペースで学習することができます。
やる気のある中学生は先取りをして周りと差をつけるために,遅れをとってしまっている生徒であれば逆転を可能にするために,是非使ってみてください。
以下はスタディサプリになりますが,該当する学年の講座を動画で視聴し,演習量の不足を市販の問題集で補うといった使い方が非常に有効です↓

![]() 最後に内申点について少し述べておきますと,中学3年生になってから気にすればよいと思う方もいるでしょうが,中学2年生のときに内申が2や3だった生徒が,中3になって突然5を取るようなことはまずありません。
最後に内申点について少し述べておきますと,中学3年生になってから気にすればよいと思う方もいるでしょうが,中学2年生のときに内申が2や3だった生徒が,中3になって突然5を取るようなことはまずありません。
ゆえに,成績は中1のときから気にしておくようにし,どのような勉強が自分に合っているのかを早く見定めておくことが重要です。
時間に余裕があるうちに,色々な勉強法を試しておきましょう!
今回の記事内容がみなさんの高校受験の役に立つことを祈っています。
最後までお読みいただきありがとうございました。