今回はスタディサプリの中学講座にある「定期テスト対策講座」の使い方についてまとめてみることにしました。
定期テストの成績は内申点に直結してきますし,本人のモチベーションに繋がる大事な要素です。
成績が良いとクラスメイトたちから一目置かれますし,自然と勉強ができる仲間が集まってきては教えあったりできるようになるなど,良い環境づくりにも繋がります。
普段の授業は頑張って聞いていてもテストのための勉強をしなければ得点に結びつかないこともしばしばあるので,スタディサプリにおいても通常講義との違いをしっかり理解し,上手に使い分けていきましょう!
スタディサプリの定期テスト対策講座の特徴

スタディサプリの中学講座には,普段の授業の予復習に使える「通年講座」の他に「定期テスト対策講座」と呼ばれるものがあります。
このうち,日々の学習の主軸としてお世話になるのは前者で間違いないのですが,学校の定期テストが近くなると試験範囲を一気に復習する必要が出てくるわけで,そのとき通年講座を悠長に見直している余裕はないでしょう。
一般的に定期テスト対策は2~3週間前(直前期)から始めるのが普通だとされていて,それでクラス1位も十分に狙えます。
ただしそれは,すでに理解を終えた範囲を復習すれば良いだけの状態になっているからこそなせる技であり,直前期に入る前からちゃんと勉強していることが前提となっていることにはくれぐれも注意してください。
直前期までサボっていて,テストが近くなったからと2~3週間前から頑張ったところで間に合わないのです。
しかも今や普段の学習態度まで評価基準に含められることが多く,配られたプリントや書いたノートが直前期の効率的な勉強を可能にします。
さて,スタディサプリの定期テスト講座においてもこの直前期を意識したカリキュラムが組まれていて,始めるべき時期や教材の構成も通年講座とは異なったものになっているのが特徴です。
スタディサプリの場合,開始時期は定期テストの3週間前が推奨されており(ただし1週間前から使うこともできます),以下の2つが利用可能です↓
- 徹底暗記マスター
- 厳選予想問題
これらの詳しい使い方については次章以降で解説しますが,簡単に述べると前者は「英単語や理社の重要語句を覚えられるもの」で,後者は「本番と同一形式での演習ができるもの」となります。
通年講座と同じ問題が出てくることも当然あるのですが,構成自体は通年講座とは明らかに異なり,別の角度からより理解を深めることができるわけです。
対応範囲はより限られますが,スタディサプリでは実技教科(音楽・美術・保健体育・技術家庭)の対策すらできてしまいます。
ただし,教科書内容に沿う必要があるため,特定の教科書に対応した講座以外(例えば国語の共通版など)では定期テスト対策講座が利用できないことと,用語暗記が不要な科目(数学や国語など)には徹底暗記マスターが存在しないことにご注意ください。
さらに言えば,学校のワークやノートの復習もこれらとは別に行わなければならず,例えば期末テストで学校の校歌を分析しろと言われた際,スタディサプリの知識だけでは当然ながら歯が立ちません。
中3生ともなれば,学校で習っていない初見問題(高校入試を出どころとするような難しめの問題)を目にする機会も増えるでしょう。
試験範囲も「これまでに習った全範囲」とか平気で言われるわけです。
本人の目標点や本番までの残り時間によってはどこかで妥協する必要も出てくるでしょうが,基本的には上のような対策も手を抜かずに行わなければなりません。

なので,特に英数で高い点数を取る必要がある方は,普段からスタディサプリにある様々な講座(英検対策講座や高校受験対策講座)を視聴して,根本的な学力を高めておくようにしてください↓
少なくとも私のような大人があなた方の中学の定期テストを受けたところで9割の得点率を下回ることはないわけですから。
スタディサプリの定期テスト対策講座の使い方
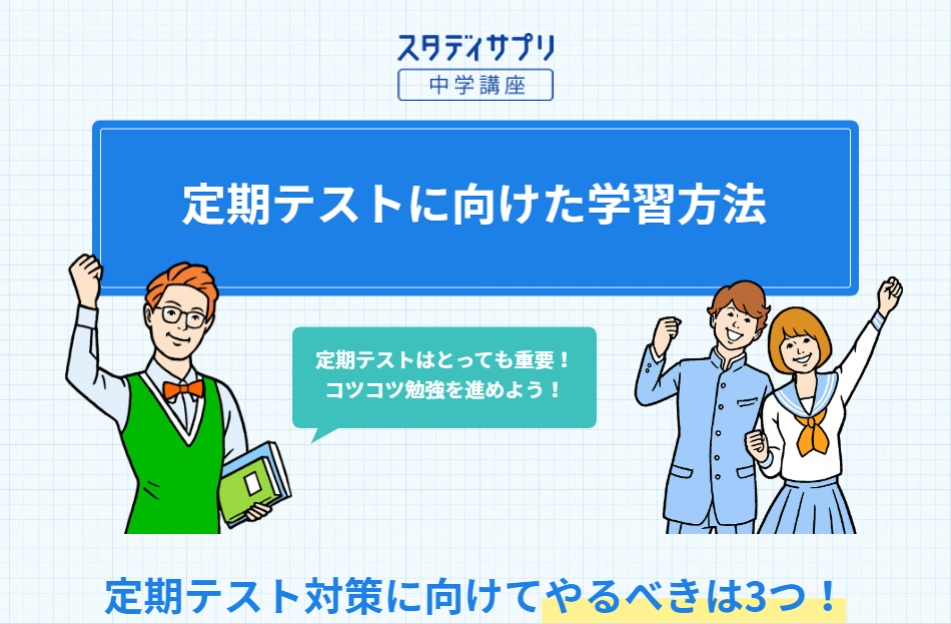
ここではスタディサプリの定期テスト対策講座の使い方について,テスト前に意識したいポイントを中心にまとめてみたいと思います。
学年や教科,時期によってレッスン数は異なりますが,基本的な流れについては変わりません。
以下に,定期テストの3週間前から対策するときの過ごし方をまとめておきました↓
定期テスト直前期の過ごし方
3週間前:徹底暗記マスターを始める。試験に必要な提出物も確認しておく。
2週間前:学校のワークを解く。スタディサプリの厳選予想問題を開始する。
1週間前:学校のワークを何度も解き直す。覚えるべきものはノートにまとめる。
以下でもう少し詳しくみていきましょう!
テスト3週間前にやること
3週間前から徹底暗記マスターを始めますが,全範囲の用語にいち早く慣れておくことで,後でワークの解説などを読んだときの理解力を高められる効果があります↓

一問一答形式であるため10分も経たずに1レッスンを終えられることに加え(英語などでは例外もありますが),全範囲に目を通したことによる安心感もプラスされるので,変に焦らなくなるはずです。
解説内容も読んでおきましょう。

朝食や電車を待つ間に取り組むことも可能です。
もちろん,この時期だと授業で試験範囲が終わっていない科目もあるように思うので,そちらは通年講座を使って通常通り学ぶようにしましょう!
ノートや配布プリントももれなく準備しておくことも忘れないようにしてください。
テスト2週間前にやること
テスト2週間前になったら,徹底暗記マスターの他に厳選予想問題を解き始めます。
厳選予想問題とは定期テスト対策となりうる問題だけを選び出したもので,英数理社の4教科を5時間ほどで復習できてしまうものです↓

なお,英語と数学は問題量が多く時間がかかるため,その他の教科よりも優先的に行うようにしてください。
昔に習った範囲でもう忘れてしまったものについては,復習動画で学び直すこともできます(内容は通年講座と同じなので,解答に付いている解説だけをみてわかるようであれば動画まで観る必要はありません)。
学校のワークですが,書き込む前にあらかじめコピーをとっておくようにすれば,書き込みがない状態で利用できます。
ギリギリまで発表されないのが試験範囲ですが,この時期になれば多くは出揃うことになるでしょう。
捨てる範囲を作らず,まんべんなく対策することが大切です。
テスト1週間前にやること
定期テストまで残り1週間の過ごし方ですが,徹底暗記マスターは継続で,厳選予想問題も理社や実技教科で終わっていないものがあれば利用してください。
学校のワークは2周目以降に入ると思いますが,このとき間違えた問題には必ず×をつけておくかノートに書き写しておくようにし,それらだけを試験前日や当日に復習するようにしましょう。
1週間前ともなれば,別々のノートにバラバラに書き残すのではなく,すべての教科を1冊のノートにまとめてしまうノート術がおすすめです↓

詳しくは令和時代の勉強法の記事などで語っているので,時間があるときに読んでみてください。
ミッション機能について
色々と述べてきましたが,実際にテスト対策を行おうと思った際,以上のことはスタディサプリの方で自動的にやってくれます。
多少大雑把になってしまう感があることは否めませんが,以下のように定期テストの日程を入力するだけで自動的に定期テストミッションが表示されるようになるわけです↓

後はそれに従って勉強していくだけでよいため,単純明快で進めやすいと感じるでしょう↓
この場合,学校のワークを解くことやプリントまたはノートの復習をメインであることを強く意識し,スタサプはあくまで基礎的な知識を確認するだけの補助要員として見なしておくのが良いように思います。
定期テスト対策講座の中身を教科別に紹介
ここでは主に「中学3年生の1学期中間テストの範囲」を題材として,定期テスト対策講座の内容を教科別にレビューしていきたいと思います。
細かく使おうと思えばミッション機能に従わずに自分自身で工夫して使うことになるので,慣れてきた方におすすめです。
英語
まずは英語の徹底暗記マスターについてですが,通年講座である中学英語講座の中にある「単語 意味を覚えよう」と「単語 スペルを覚えよう」と同一の内容となります。
ただし,通常であれば4択問題だったものが,徹底暗記マスターではノートに意味を書く形式になっているなど,難易度自体は上がっていることに気づくでしょう↓

スペリングの方はというと,通常版の時点ですでに難易度が高めだったこともあって形式に変更はありません。
続いて厳選予想問題の説明に移りますが,こちらは問題演習がメインです。
もし問題を頻繁に間違えてしまうようであれば復習動画も観ておきましょう。
本文対策は通常講座で解説動画の後に解いたものと同じです。
「厳選」の意味としては,該当するUnit内で登場した問題演習のうち,特に定期テストに出そうなものを中心に選んだということになります。
ゆえに通年講座の問題演習をすべてやり直す余裕がある方であれば基本的に解く必要はありません。
ところで,文法は英作文の出来にも関係してくるため,ここで間違った文はノートに書き出しておき,日本語だけを見て全文を書けるようになるまで練習しておくと完璧です。
問題の中には,以下のように最初から全てが空欄になっているものもあります↓

もっとも,上の形式であっても,空欄の数から6つの英単語で表現できるとわかってしまうため,やはり日本語だけを書き写しておき,英文にできるかどうか後でチェックする方が無難でしょう。
例えばNew HorizonのUnit1だけを学ぼうと思った際,徹底暗記マスターは96問の目安時間37分が,そして厳選予想問題は全36問の目安時間46分(徹底復習まで含めると全88問の目安時間64分)が必要でした。
数学
続いて数学の定期テスト対策講座ですが,先述したように厳選予想問題のみとなります。
難易度は基本レベル(まずはこれだけ!)の他,応用レベル(さらに応用!)があり,以下の画像で説明すると,上段にある3問が基礎レベルで下段の2つが応用レベルです↓

幅広い範囲を短い時間で学び直せるのが特徴で,通年講座のときと全く同じ問題セットとはなっておらず,分量についても通年講座の単元テストでは42問しかなかったところが,定期テスト対策講座の方では206問になるなど,5倍近くの問題量となっていました。
逆に応用レベルの問題数は60問などと程良くなっているので,素早く数学の総復習を終わらせてしまいたい人(数学が得意な人)はこちらだけを利用するのもありでしょう。
注意点として,応用問題においてはすべての出題パターンを網羅しているとは言えず,証明問題に代表される記述問題のようなものは,穴埋め式でやるには限界があるということです↓

こうした問題は学校のワークに出てくる問題の方が難しいことが多いので,数学で高得点を目指す方は,最終的にワークの記述式問題を中心に復習するようにしてください。
試験前の工夫として,定期テスト対策講座で間違えた問題を学校のワークと関連付けておくのも良いでしょう。
これはどういうことかと言えば,間違えた問題と似た問題を教科書やワーク内で見つけてきては,ページや問題番号をチェックしておくということです。
例えば上の証明問題を間違えてしまった場合に,「教科書p.30の1⃣(3),ワークp.6の4⃣(1)」の問題番号のところを色ペンを使って目立たせておくようにします(わからなければ,スタサプの問題をノートに書き写しておくでも構いません)。
厳選予想問題で間違えた問題と関連付けられた類題というのは自分が苦手とする問題に他なりませんから,試験の1週間前にまとめて解き直すことでより万全な対策が可能です。
国語

国語は光村図書の教科書のみに定期テスト対策講座があるだけですが,まずは本文を制限時間付きで読み終えた後,問題演習を行う流れです。
問題のタイプは普通の読解問題以外に,重要語句の意味を答える問題や漢字にまつわる問題もありました↓

ただし,これらはすべて通年講座の中学国語講座において,講義動画を観た後の確認問題で解いたものと同一です。
国語ではあまり問題の解き直しを行わないものですが,定期テストでは教科書と同じ文章が出されることになるのでこうした作業もしなければなりません。
なお,漢字の問題はワークを使って実際に書く練習をする必要がある他,授業ノートもよくみておく必要があります。
社会・理科
社会は地理・歴史・公民からなりますが,どれも同じ出題形式です。
中3の1学期の中間テストを取り上げるということで第一次世界大戦の問題を紹介しますが,徹底暗記マスターでは通年講座では3択から選ぶはずだった問題が,一問一答形式で直接正解を答える形になっていました↓

すべての知識を等しく覚えていかなければならないのが社会科ですので,特にレベル分けはされていません。
なお,試験前に間違ってしまったものは,説明ごと書き取って,用語を見て詳しい内容を説明できるまでにしておくと良いでしょう(答えを見てから問題文の内容を再現するという意味です)。
例えば上の「三国協商」が不正解だった場合,「第一次世界大戦前のイギリス・ロシア・フランスの結びつきのこと」と説明できるようにしておきます。
一方の厳選予想問題ですが,通常のスタディサプリの中学社会に出てくる「まとめ問題(講義動画の確認として出てくる問題)」そのままでした↓

両者ともあくまで復習用に使う感じですね。
理科の定期テスト対策講座についても構成は社会のそれと同様だったので省略します。
各自ができる工夫としては,間違えた問題の知識を学校のノートに書き足しておく他,まとめられる内容は図や表にしておくことで試験前に要点を一目で確認できるはずです。
まとめ

以上,スタディサプリの中学講座にある定期テスト対策講座の使い方と,3週間前からの過ごし方,そして最後に教科別の特徴についてまとめてきましたが理解は深められたでしょうか。
上の画像は,1週間前から定期テスト対策講座を使う案になりますが,朝起きて布団の中で5分学ぶとか,歯磨き中に理科の徹底暗記マスターを終えるなどと,自分なりにテスト前のルーティンワークを作ってしまうことが重要です。
高い内申点を得るためにはいち早く中学生活に適応し,自分なりの勝ちパターンを構築する必要がありますが,普段は通年講座を使って熱心に学んでいても,肝心の試験前を下手に過ごしてしまったがために思わぬ結果が得られないこともあります。
折角学んだ知識もテスト当日に思い出せる状態にしておかなければそれまでの努力が報われないので注意してください。
なお,前章で紹介した教科別の学び方では,間違えた問題をそのままにせず別の角度から学び直せるように工夫することの大切さに気付いてもらうことについて力説しました。
とはいえ細かな方法論は人それぞれですので,解けない問題を見つけるために定期テスト対策講座を用いる原則からは外れないようにしつつも,後は自分が使いやすいように工夫して使っていってください。
スタディサプリの個別指導コースで学んでいる方は担当コーチの指示に従うだけです。
スケジュールだけでなく理解度のチェックまでしてくれるでしょうから心配は要りません。
これからスタディサプリに申し込まれる方は,スタディサプリのキャンペーンとコードに関する記事に目を通すようにしてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。